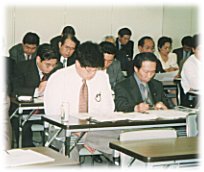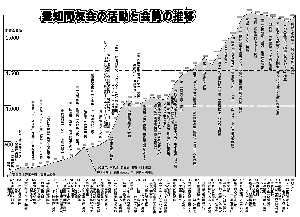愛知同友会第39回定時総会(2000年4月29日)第3分科会
会員三〇〇〇名を展望して!
〜愛知同友会38年の歴史と魅力とは〜

●パネリスト
小瀬木昭三氏(株)富士ツーリスト・監査役(愛知同友会・創立会員)
廣瀬嘉人氏(株)カスク・社長(愛知同友会・副代表理事)
鋤柄修氏(株)エステム・社長(愛知同友会・代表理事)
福島敏司氏愛知同友会・事務局長
●コーディネーター
高岡正昭氏(有)共生都市計画研究所・社長(愛知同友会・副代表理事)
○初心忘るべからず入会の経過と同友会の魅力
(高岡)この分科会では愛知同友会の創立時、発展時、そして今後の展望について四名のパネリストから語っていただくことにより、なぜ「同友会ビジョン」ができてきたのか、その背景を深めていきます。まずパネリストの方の自己紹介からお願いします。
創立以来38年間地区幹事を続けて(小瀬木氏)
現在名古屋支部中村地区の小瀬木です。私が同友会に入会したのは一九六二年で、創立総会へ参加した三十四名の「生き残り」の一人です。入会のきっかけは遠山昌夫氏(菊水化学工業(株)・社長、現愛知同友会・顧問、初代代表理事)との出会いです。当時、私は食料品の卸売業をやっていました。インスタントの料理ダシを開発し、製造を開始する寸前、伊勢湾台風で南区の工場が流されてしまいました。再建すべく大手の食料品メーカーに資金援助を受けましたが、そのものを大手にもって行かれてしまい、大変憤りを感じていた時期でした。発足して一年くらい経った時、四つの地区がスタートしました。その時、第四地区で地区幹事を引き受けて以来、今年三月まで三十八年間ずっと続けています。その間、理事、常任理事、政策委員長などやってきましたが、地区幹事を兼務してきました。今年四月、「地区顧問に」と言われたのですが、顧問というのは同友会にふさわしくないと思いお引き受けせず、現在は「オブザーバー」という肩書きになっています。それと中部同友会協同組合の理事を十二年間、愛知県中小企業研究財団の常務理事を発足以来七年間と、同友会と関係する活動を現在もやっています。私の考える同友会の魅力というのは、他の同業組合などと違い、会社の規模や年齢などによる差別がなく、平等だということです。
遠山氏の講演に共感、その場で入会(廣瀬氏)
新聞などで見て同友会の名前は知っていました。たまたま遠山さんの講演会のチケットをもらい、聴きに行きました。「人間尊重の経営〜共に育つ」という内容のお話で、大変感動し、さっそくその場で入会手続きを済ませてしまいました。一九七七年のことだったと思います。当時の中川地区は食事を取りながらの例会でしたが、何か大変元気がありました。広報委員を二・三年やり、その後あまり熱心ではなかったのですが、八五年、順番で地区会長のお鉢が回ってきました。地区会長をやってみると同友会の重要性が良く判り、その後は支部役員、支部長を経て、現在では増強と財務、そして事務局を担当する副代表理事の立場にあります。
ピンチヒッターで地区会長に
気がついたら代表理事に(鋤柄氏)
会社創業十年目に労働組合ができました。非常に利益が出たので特別賞与を出したのですが、その配分方法をめぐって団体交渉になりました。当時は賃金規定も評価制度もなく、特別賞与だから大雑把でいいと思ったのが間違いのもとでした。このことがきっかけで経営の勉強の必要性を痛感し、私も新聞で見て、同友会に自らすすんで入会しました。そういう事情ですから熱心に出席しました。一年経つと地区役員に、しばらくすると地区の副会長になりました。その一年目は良かったのですが、二年目になったとたんに地区会長の会社が倒産、地区会長職を受けざるを得ない状況になり、それから四年十一カ月延々と続けることになりました。ですから同友会では少々のことでは驚かなくなりました。その後、どういう訳か代表理事までなってしまいました。同友会の魅力の一つは、会員にすがっていけば、どんどん教えてくれるということです。格好をつけて隠していると、誰も教えてくれません。逆に弱みを見せて教えを請えば、本当に親身になって教えてくれます。会社が違えばまったくそのとおりにはなりませんが、ヒントはたくさんいただけます。また多くの会員がいることも魅力の一つです。地区があり、支部があり、オール愛知があります。さらに全国に仲間がいます。この会員同士がうまく交流することができれば、お互いに経営に役立つことのできる無限の知恵の宝庫を持つのです。
前には道なく、後に道ができる(福島氏)
同友会へ入ったのは一九七五年、私が二十五歳で、ちょうど会員数が五百名になったところでした。当時、新卒で同友会へ入ったのは全国でも初めてだと言われました。一九八一年に三十一歳で事務局長になりましたが、当時は会員数が減っている時期でしたので、少しでも減らさないようにしたいと、そのことばかり考えていました。同友会は「俺たちの前に道はなく、俺たちの後に道はできる」みたいな世界です。道しるべは同友会理念だけ、創っていくのは我々、というのが最大の魅力かなと思っています。
○全国に先駆ける愛知同友会の試み
より多くの仲間と連帯し政策提言を
(高岡)愛知同友会の歴史に入る前に、代表理事より今後の愛知同友会がどの方向へ向かうのか、また三千名会員の持つ意味にについてお話していただきたいと思います。
(鋤柄)九○年代に入り、日本の経済構造は激変しました。それに対して私たちは何をやってきたのでしょうか。同友会には、ご存知のように「良い会社になろう」「良い経営者になろう」「良い経営環境をつくろう」という『三つの目的』があります。確かに一番目と二番目の目的については一生懸命やってきました。しかし行政に働きかけるとか、私たち自身で経営環境を改善する運動に取り組むという三番目の目的は、おざなりだったというのが、率直な現状です。この反省の上に立って、昨年四月の総会で「99同友会ビジョン」が出されたのです。会員数については、二千二百名より三千名の方が大きな重みになりますし、会員の数が多いほど、良い会社も良い経営者も出てきます。自分の会社を良くするための自立型企業づくりも大切ですが、私たち中小企業を取り巻く環境を良くしようと考えるなら、より多くの仲間が連帯して政策提言していかないと、相手に訴えられないんです。
会員の増加と組織の発展
(高岡)それでは福島事務局長より三十八年間の愛知同友会の活動を振り返っていただきます。(以下表参照)
(福島)一九六二年、三十四名の発足時には、東別院の「寿藤会館」に事務所を設置しました。翌年(会員百二名、以下は会員数)の時、四つの地区が誕生しました。六五年(百三十名)に事務所を中川区の中日球場前に、七二年(四百十六名)に御器所の朝日生命ビルに移転しました。地区数は十一です。七六年(七百十六名)、三河地区ができ、会の名称を「名古屋同友会」から現在の「愛知同友会」に変更、八○年(千六十三名)に事務所を現在の中区錦の京枝屋ビルに移転しました。その二年後の八二年には、刈谷に三河事務所(地方事務所)を設置しました。この時点で二十地区・会員千百三名となりました。その翌年(八四年)ブロック(現在の支部)制を導入後、地区の細分化が進み、九一年(千九百四十名)にブロックから支部へ組織変更がされました。九二年(二千十六名)の三十周年で五支部・四十地区となり、九七年(二千二百四十二名)の三十五周年では五支部四十一地区に、今年(二千二百七十一名)は尾張、名古屋、三河の三支部で三十九地区の組織となっています。
「経営指針成文化」を75年に提唱〜全国の同友会で活動の大きな柱に
さて全国的な同友会運動の中で愛知同友会がどんな役割を果たしてきたかというお話をしたいと思います。一九六六年の愛知同友会の総会で、同友会の目的を「四つの柱」という形で定式化しました。これは、七年後の七三年、中同協第五回総会で制定された現在の『三つの目的』の基となるものでした。また六七年には「労使関係観」という文章を発表しています。これは七五年に中同協から発表された「労使見解」につながっています。六九年には東京・大阪・名古屋・福岡・神奈川の五同友会(会員計六百四十名)で中同協が設立されます。七一年愛知が設営した中同協第十回総会で初めて分科会方式を採用、また七○年に青年同友会が、七二年には婦人部がスタートし、階層別部会も全国に先駆けてつくってきました。七五年には「経営指針成文化」を提唱しましたが、これは現在、全国・各地の同友会活動の大きな柱になっています。また、七九年、愛知で北海道に次いで共同求人活動をスタートさせ、その翌年に東京同友会が始め、現在、全国で行われています。さらに八二年の愛知同友会二十周年の時、「小さな会社はやる気がすごい」という本を出し、一般書店でも販売され、世間に同友会を知らせていく活動を初めて行いました。
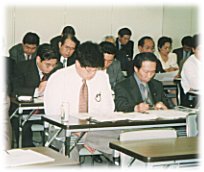
さらに内部充実が求められる地域組織
地区・支部(ブロック)の活動から三十八年間を見てみると、四つの期間に区切れると思います。一つは創立二年目に地区ができ、会員がより身近な交流ができる場ができたことです。第二の時期はブロック制を導入した時です。(1)地区を分割して身近な知り合いの場を確立させながら、一方でさらに広い相互交流の場をつくる。(2)講演会・研究会・レクリェーションなど、一つの地区ではできないことを協力して実行する。(3)ブロック内の地区相互の交流を強めていく。これが導入の目的で、細分化で身近な地区づくりと広域を包括するブロックでのダイナミックな活動をめざした時期でした。三番目は内部充実に伴い、ブロックから支部へと名称変更をおこなった時期です。九二年の第三十一回総会方針の中では、支部の役割として(1)会の方針を浸透させていく、(2)地区の活性化のために支援・援助・調整を行う、(3)役員の育成と増強の推進、(4)委員会と連携して支部内に研究会をつくるとし、ブロックの段階では言われていなかった事が、支部になって入ってきています。最後は三十周年の「リボーン」から始まった活動改善の進展です。「入会に当っての申し合わせ」から始まり、理事定数を削減を行いました。現在は「地域社会と共に」という視点から、地区・支部の編成の見直しに入っています。また事務局の在り方も見直しにも入っています。
○歴史を踏まえ今日的課題は
大都市圏同友会の抱える問題は共通
(高岡)事務局長の話しの中で、「三つの目的」の前の「四つの柱」だとか、全国へ先駆けての経営指針成文化運動だとか、いくつか先駆的な活動があったと報告されましたが、現在も先駆的な活動があると思いますが。(鋤柄)この三月、東京・大阪・愛知・福岡・兵庫という大都市の同友会の代表役員が名古屋に集まって、共通の悩みや問題点を話しあう機会がありました。大都市圏でのドーナツ化の悩みや増強の重要性、「三つの目的」の三番目の目的は運動として取り組まなければならないことなどが、共通の課題として確認されました。その中で愛知は、ビジョンに基づき活動改善がすすみ、事務局を機能別組織にするという事務局活動の改善も行おうとしています。このように大都市圏同友会の中でも一歩先を行こうとしていますし、この考え方や方向に間違いはないと思います。
原点は地区にありだからレベルアップを
(高岡)今後の地区・支部の活動のあり方についてはいかがでしょう。(小瀬木)同友会へ入会して最初に接するのは地区です。地区を通してお互いに知り合いになると言う意味で、その存在は大きいと思います。地区と支部との関係ですが、実質的に地区の活動の質を上げなければ、支部の活動も上がらないと思います。例えば東京の「大田21研」のような質の高い活動をつくっていかなければと思います。(廣瀬)小瀬木さんの地区のレベルアップが必要という指摘は重要です。私は長く増強に関わっていますが、そのお願いで地区へ行こうととすると、「自分たちは仲良くやっているので増強の必要性がない。来なくて良い」と言われてしまうケースもありました。また、地区会長の選出方法にも問題があると思います。同友会に入って少し出席率がいいとすぐ役員になります。それはいいのですが、同友会全体のことがわからず、すぐに地区会長になってしまい、地区の事にしか目を向けなくなってしまいます。本来地区会長は支部役員ですから、知らなかったとか、「支部か、地区か」というような論議はないはずです。しかし支部役員会を欠席する場合に代理を出さなかったり、自分が伝達すべき人々に対し伝えなかったり、かなり無責任な行動もあります。いずれにしても会というものは会員一人ひとりが原点です。会員が何を求めているのかの目線は地区も支部も県も中同協も、全て会員に向けられていなければなりません。
地域に目を向け、研究会の充実を
(高岡)では、レベルアップのためには、なにが求められているのでしょうか。
(福島)「地区・支部活動の手引き」の中では、変化することを前提に、「地区とは基礎的な組織」と言われており、基礎組織とか基本組織とか言わないことを押さえておく必要があります。その上で地区のレベルを上げて行くという問題で二つの課題があると思います。第一に、ここ四〜五年言われている「いい例会づくり」、役員会できちんと準備をして学べる例会づくりです。もう一つはビジョンで言われている地域に目を向けていくということです。東京同友会では行政区の政策審議会に委員を派遣している支部(愛知では地区にあたる)が四つあります。地元行政との間で、長い時間をかけて関係づくりをしてきたということです。こういう展開が二つ目のレベルアップだと思います。同時に地区のレベルを上げていく時に支部の役割はどこにあるかと言うと、一つは支部に研究会をつくっていくことです。一つの地区では二〜三人しか要望のない経営課題でも、支部でまとめれば充分研究会として成立することは、ISO研究会の例を見ても明らかです。もう一つは街をどうしていくのか、この地域の製造業はどうしたら良いかなど、地域の政策を考えるグループは現段階では支部の研究会として存在すべきだと思います。
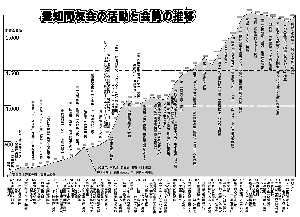
拡大図はこちらをクリックしてください。
○会場からの質問と応答
(Q−H氏)例えば理事会で決ったこと等が、なかなか地区へ伝わらないと言うような、情報がうまく伝わらないという問題をどう改善していけば良しょうか?
(A−廣瀬)発信した方は当然相手に届いていると思っていること自体が、問題だろうと思っています。色々な方法でたびたび告知をしているのに、知られていないという現実があります。これは受け手の側の問題もかなりあります。したがって一挙に解決するのは困難だと思います。役員が常に伝えるということ自体を課題として意識していることが大切だと思います。
(Q−N氏)九二年度に二百三十八名も純増で増えています。なにか特別の事があったのでしょうか。それと、会員を三千名にするのは、いつまでしょうか?
(A−廣瀬)九二年度と言うのはちょうど同友会創立三十周年の年で,「三十周年三千名」を合言葉に、「千名を一年で増やす」という今から考えると途方もない目標ですが、皆で頑張った年です。それに情勢的には、バブル崩壊の波はまだ私たち中小企業のところには、あまり来ていない時期でした。三千名はビジョンの中にも書いてあるように、二〇〇四年に達成することをめざしています。
(Q−K氏)私は当時鋤柄さんに地区会長をお願いした役員の一人であったことが、同友会に対する最大の功績かなと思っています。私はこれまで社長をやっていた会社を昨年末で辞めました。すると会員資格がなくなってしまいます。長年所属をしてきた会ですので(ほとんど創立から)とても去りがたいものがあります。そこで、あえて新会社を興しました。そして死ぬまで会員で居続けようと思っています。ご報告まで。
(高岡)三十八年間の歴史の重さ、普遍的な原則論みたいなものを、ハウツーではなく人間として、経営者としてのあり方まで含めて振り返ることの重要性を感じました。こういう事をやることがこの分科会としてよかったと思っております。本日出された問題はそれぞれが課題としてお持ち帰りいただければと思います。長時間ありがとうございました。
【文責事務局・山田】