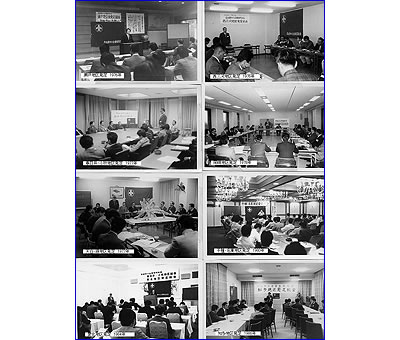創立50周年記念式典 記念講演(7月9日)
創立50周年記念式典 記念講演(7月9日)
愛知同友会50年の歴史から学ぶもの
名城大学教授 渡辺 俊三 氏

先駆性と時代適応性
同友会運動の重点は、経営環境の改善・経営体質の強化・組織強化の3点におかれています。そして愛知同友会の運動史の特徴は、先駆性と時代適応性だと思います。
先駆性とは特に、さまざまな活動において他府県に先駆け、数々の「愛知モデル」と言われるものを実践してきたことです。
例えば地区組織、3つの目的、経営指針、金融アセスメント法制定運動、欧州小企業憲章の現地視察など、枚挙にいとまがありません。
時代適応性については、愛知同友会は会員数増大に伴い、当初から細胞分裂のように地区を増やし、1980年以降は地区・支部体制や委員会についても組織の統廃合を重ね、また90年代には、組織増で100名を超える理事の人数を40名程度までに削減するなど、役員会の大胆なスリム化も行われてきました。
組織というものは一旦つくると硬直化しやすいものですが、愛知同友会では時代に適応できるよう組織を変化させ、活性化を図っています。これは、中小企業家の組織であるからこそ柔軟な変革ができたのだと思います。
「理念確立型」の運動
こうした視点から、愛知同友会の50年を振り返り、どのような事が学びとれるのか見ていきます。
愛知同友会の歴史は、創立から70年代までは運動のあり方を模索した時代、80年代以降は確立されてきた運動を時代に適応させながら展開していった時代でした。
そして80年代以降の運動方向を定める上で大きな役割を果たしているのが愛知同友会のビジョンで、77年に初めてビジョンを発表して以降、ほぼ5年ごとにビジョンが作成され、運動方針に生かされています。
同友会運動とは一言で言って、「理念確立型」の運動であるといえます。つまり、「今どうするか」よりも、「5年後、10年後の企業や同友会はどうあるべきか」、その方向性を打ち立てることを重視しているのです。
同友会の理念や考え方としては、「自主・民主・連帯の精神」「3つの目的」「国民や地域と共に歩む」ですが、その他にも、「共育」「人を生かす経営」「自立型企業」「経営指針の確立」などさまざまあげられます。これらのかなりの部分が、愛知同友会での議論の中から生まれてきたことが、歴史を紐解いていくとわかってくるのです。

歴史的教訓を継承して
例えば「自主・民主・連帯」で言えば、1967年の規約改正で会の目的を「この会は中小企業家のための自主的、民主的な組織として」とするなど、その考え方が創立してから5年後にできています。
「3つの目的」について言えば、1966年に発表した「4つの柱」という方針に「経営者の姿勢を正し、企業活動を発展させ、赤字企業をなくそう」とあり、重要な指摘であると思います。この部分が敷衍され、中同協の「3つの目的」になっていったと考えられます。
また、今年度の愛知同友会総会のテーマとして「同友会らしい黒字企業をめざそう」がスローガンとして掲げられましたが、まさに同じ事が1966年の段階で目標として掲げられていたのです。
このように、同友会理念やその考え方は一朝一夕にできたわけではなく、50年間の歴史の中から生まれてきたものなのです。


環境改善と体質強化 組織強化を一体化
つぎに、同友会運動の重点である、経営環境改善・経営体質強化・組織強化についてまとめてみます。
まず、創立のきっかけでもあった経営環境改善ですが、これが同友会運動の中心に置かれ出したのは90年代後半以降と見られます。いわゆる「失われた10年」を経験するなかで、経営体質強化と経営環境改善を一体化しなければ、双方ともなし得ないことに気付いたからでしょう。
この両者の一体化は、金融アセスメント法制定運動と中小企業憲章制定運動を通して図られ、特筆すべき成果をあげました。
また、経営体質強化は愛知同友会が最も力を入れてきた運動で、70年代後半からの経営指針成文化運動はその最たるものです。経営者自身のたゆまぬ自己変革に重点を置いた経営体質強化の取り組みは、努力すれば成果が目に見える形で現れます。これが同友会運動を50年間持続させている要素だと思います。
最後に組織強化については、創立当初の会員34名から出発して今や3200名に会勢を伸ばした事が、すべてを物語っています。特に2000年以降は景気後退にも関わらず、会員数は増え続けていることに注目すべきです。
この理由は、経営環境改善と企業体質強化を一体化した運動に取り組んできた成果であり、会の存在意義が対外的にそれだけ高まった証左に他なりません。
【文責 事務局・政廣】