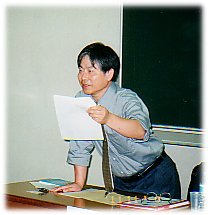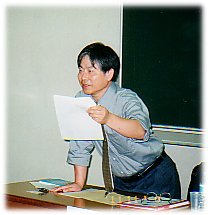第10分科会「産業空洞化を乗り越えるまちづくり〜愛知県の製造業集積をいかに活かすか」
森川章氏名城大学経営学部・教授
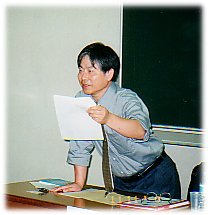
プロフィール
1943年生。京都大学大学院経済学研究科博士課程を経て現職。【著書】「労務管理の生成と展開」(ミネルヴァ書房)共著「アメリカ企業経営史」(共著)他多数。
経済のグローバル化と愛知県の産業空洞化問題
産業空洞化が進行しています。自動車産業で成長を続けてきた愛知県も例外ではありません。トヨタ自動車は、2000年10月21日に、東南アジア地域をとりまとめる統括会社をシンガポールに設立することを発表しました。既に、アメリカ、ヨーロッパにある統括会社に、日本本社を加えた世界四極体制で、生産、販売、いずれは新車開発までをグローバルに展開しようとしています。これらの地域に部品メーカーの進出が相次いでいます。ある部品メーカーは「愛知県の産業空洞化の先棒を担ぐ形になるがやむを得ない」とコメントしています。
各地の空洞化対策
(1)東京大田区、空洞化問題は70年代より始まっていました。大田区の下請け企業も量産部品下請は「大企業の工場移転」に伴い地方(後には海外)へ移転しました。大田区内に残った企業は、周辺の大企業、中企業からの開発や試作業務に重点を移しました。これらの企業が行政支援も受けながら、高度の加工技術をもつネットワークを構築し、地域として対応しようとしています。
(2)大阪・木津川工業団地、住工混在の騒音対策や中小業者の工場適地を求める要望に対し、大阪民主商工連合会が中心となり、造船所跡地を再開発することによってできた工業団地(約200社)です。企業の相互交流を基盤に共同受注、開発のグループが形成されてきました。少ロットや難加工に対応しており、「あそこに頼めばなんとかなる」との評判が定着しています。
(3)他の同友会より、大阪同友会では新製品、新事業開発を目指す「オンリーワン研究会」が中創法認定をめざし、龍谷大学の貸し研究室に共同入所し、製品開発に取り組んでいます。兵庫同友会では、共同受注、共同開発グループ「アドック神戸」が発足し、神戸市、兵庫県などからも支援を受けています。さらに滋賀同友会が製造業部会「Hip滋賀」を立ち上げました。こうした中小企業のグループ化の特徴は次の点です。(A)仕事待ちの姿勢から、仕事を取る、作り出す姿勢への転換(自立化)(B)地域の長所を活かした活動(C)行政をも巻き込んだ活動(D)自己の足りないところは他の地域との連携でカバーするこれらの活動が持続されれば、今後その努力を怠った地域との格差が歴然となってきます。中小企業をめぐる今日の動きのキーワードは「地域間の競争と協調」といえます。
愛知の産業集積の特徴
愛知県の産業集積の特徴は以下の通りです。まず長所として次の3点があげられます。第1に、自動車産業を中心とした機械金属産業の一大集積があることです。自動車産業は多くの産業にまたがる総合・精密機械産業ですから、これらの企業群はあらゆる産業に関係しています。第2に、高度な加工技術を身につけた熟練技能者が多く集積していることです。第3に、デザインに応じる開発力をもった下請け企業も多く存在していることです。これら3つの長所の存在は、愛知県ではあらゆるものづくりが可能なことを意味しています。逆に短所として次の2点があげられます。第1に親企業に連なるタテ系列関係の結びつきは強いが、ヨコの相互協力が弱いことです。第2に概してマーケティングに弱く、仕事待ちの傾向が強いことです。この2つの短所の存在は、それがそのまま放置されるならば先の長所を帳消しにしてしまい当地の将来は開けて来ないことを意味しています。各地の「企業グループ化」の地域的取り組みに比べ、愛知県の地域としての方向性は明瞭でなく、現状では不安が残ります。企業間のヨコの連携、さらに他地域との地域間連携を模索し、長所を活かし短所を補う活動が望まれます。
注目される三河金属部会とエントロピー豊明
(1)三河金属部会の「横請け」
知立機工の豊田氏の呼びかけで13社で発足。お互いの得意分野の余力を提供しあう形でネットワークを形成し、少ロットや難加工でも受注できる体制をめざしています。お互いの企業訪問を重ね、得意分野の把握に努めてきました。「あのグループに頼めば何とかなる」という評判を得ることが当面の目標です。
(2)エントロピー豊明の「異業種交流・製品開発」
サカエの山本氏の呼びかけで9社で発足(現在は10社)。異業種交流は、A交流段階、B開発段階、C事業化段階の3段階に発展していくといえますが、従来の異業種交流の多くが、Aに留まっていたのに対し、山本氏は、B・Cを意識的に追求してきました。そしてその運営ノウハウを次世代のエントロピーに引き継ぐ構想をもっています。これまでの活動の力点は「リサイクル」「社会貢献」「3K職場の改善」の3つに置かれてきました。実際に開発までこぎつけたものには、建設現場で使う治具や、ダイオキシン対策の焼却炉などがあります。第2、第3の「三河金属部会」や「エントロピー豊明」が次々と誕生し、成長するようになれば、愛知県の地域としての将来も展望が開けてくることでしょう。その方向へ向けた産官学一体となった取り組みが望まれるところです。
いくつかの留意点
(1)行政を巻き込む活動
各自治体でも空洞化対策の必要性を感じていますが「どうすればよいか」を模索している最中です。したがって行政との連携を模索し、種々の提案をしている同友会の姿勢は貴重です。更なる研究を重ね、政策提言を行うことが重要です。
(2)他の地域との連携を強める
今の変化スピードを考えると一地域ですべてを揃えることは現実的ではありません。それぞれの地域特性を活かし、自らの地域の特徴を磨き短所は他の地域との連携でカバーする思考が必要です。
(3)日本独自のテーマに着目
東京同友会のメンバーで、コンビニエンスストアで缶コーヒーなどを温める機械を製造している方がみえます。日本のコンビニを相手に開発された商品ですが、アジアでコンビニ出店が進めば、大幅に受注増の可能性があります。
エントロピー豊明の開発テーマ「3K対策、環境対策」も同様の可能性があります。また、高齢化社会を迎える日本は福祉機器開発のチャンスを迎えているともいえます。こうした「今日の日本ならではのテーマ」は今後のアジア的生活様式の中で活きてきます。こうした視点の商品開発に取り組むことも大切です。
【文責事務局・多田】