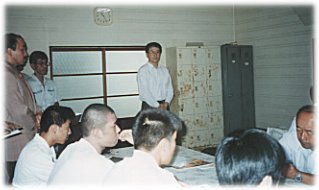青同連協若手研修会8月26日
「私は同友会のここが好き!
「若手研修会」が百名を超える参加者を集め開催され、今年は「私は同友会のここが好き!同友会をこう使う!」のテーマで、4名の青同会員が発表しました。
役を受けることで自らが成長した

第2青同の岸上昌史さん(立基建材工業(株))は新入会員として、入会から現在に至る同友会に対する気持ちを語られました。入会当初は懇親会のほうが目立ち戸惑ったこと、卒業式プロジェクトで感動したこと、今期室長に立候補し例会を成功させたことなど、岸上さんの真正面から物事に取り組む姿勢が伝わり、参加者の共感を得たようでした。第3青同の松井孝治さん(ヒダチ工芸社)は地区役員の立場で、役員になる前と後での考え方の違いを話されました。相手を思いやることの重要性に気付いたこと、副会長になり自分の世界の広がりを実感していることなど、また最後に安心して役員になる秘訣を伝授され、これには安堵した参加者も多かったようです。
学んだことを、自社で実践してきて

連協の活動改善担当として発表された第1青同の山本靖也さん((株)キョウエイ・社長)は「同友会理念」と青同「未来」の自らの解釈を、様々な事例とユーモアを交えながら話されました。最後に「同友会で学んだことを実践してきたからこそ社長としての自分がある」と結ばれ、同友会をまさに活用されてきた山本さんだけに、心に響く言葉でした。青同の枠を超え委員会メンバーとして発表された第4青同の服部勝之さん((株)丸竹・社長)は、「同友会は全会員が平等であり、相互が人として認め合っているからこそ成り立つ」と訴えられました。また、共同求人を続けることにより、自社の制度や教育体制が整うこと、問題にあたっても自ら求めれば解決策は同友会内に見出せることなど、大変参考になる話をされました。グループ討論では、「同友会の知らなかった部分が発見できた」「役員にならなければならないと感じた」などの感想が多く出されました。第2部では4つの青同が一堂に会して交流を深め、その熱気に感化されたのか、その場でオブザーバー2名が入会されました。
藤原電機産業(株)藤原聡之(第2青同)
三河支部8月28日
「99もの申す会」
あなたの会社の近所付き合いは?

今年度の「もの申す会」のテーマは「あなたの会社、近所付き合いは?」で、同友会ビジョンにある「地域社会とともに」の実践について、討論会が行われました。まず「我が町の同友会活動」と題して、三河南地区・前会長の小松英雄氏((株)小松農園・社長)の報告がありました。三河南地区は地区再編の先駈けとして5年前、三河東地区内の西尾・碧南の会員が、「地域密着同友会」をめざして発足した地区で、行政や地域住民にも同友会活動の輪を広げています。詩人として地元で活躍するラーメン屋のご主人を講師に招いた公開例会では、百名以上の地元の市民も参加し、また商工会との連携や地域での清掃活動など、着実に成果をあげている地区です。この小松氏の報告を受けて「あなたの地区、あなたの会社、地域社会とのお付き合いは?」のテーマでグループ討論を開始。グループ発表では、時代の変化に対応した地区再編に理解をしめしながらも、市単位での地区発足で、現状の地域を超えた地区での交流が疎遠にならないか」「現所属地区会員との関係はどうなるのか」などの声もあがっていました。最後に加藤支部長が、自社の本拠地である知立市で以前から取り組んでいる地域や行政への働きかけの実例を披露し、「『地域社会とともに』の実践には地区再編は不可避である」と述べました。参加者が22名と、昨年の半数以下でしたが、「地域密着型同友会」を見詰め直す絶好の機会になりました。
(株)ドライバーサービス徳升忍(三河西地区)
女性部会8月2日
公的助成金を活用しよう(パート2)
自立型企業をめざす第一歩
両津隆氏(株)エフ・アンド・エム
会社の経理を預かることの多い私達、女性部会にとって、大変為になる勉強が出来ました。公的助成金とは、国や地方自治体が中心になって、企業に交付するお金で、返済する必要がないものです。でも、交付を受けられる事柄があっても、就業規則の不整備などで、せっかくの給付金が貰えないケースが出てきます。だから、良く知ることが必要になります。自社の方向が国の方針に当てはまれば、助成金をただで使うことができる。自社にとって有利になる。こんな助成金が、70種類もあると聞きました。肝心なのは、「国の予算である助成金」が8割しか使われていないことです。まだ、4千数億円もの助成金が使われずに残っており、大企業が取りたい放題になっています。助成金は早い者勝ちで、予算額を使ってしまえば終りになります。あてはまれば、1社でも70種類の内何種類でも利用できます。知らないと損です。もっと知らなくてはいけません。活発な意見や質問が出ました。すでに利用している方も、その種類は1〜2種類。もっと活用したい、活用できるものはないかとの思いが口を開かせます。私も、その一人です。助成金が受けられない会社は、受けられる会社と、どこが違うのか、自社をもう一度掘り起こしてみる必要があります。その原因がわかったら、改善に着手する。これこそが経営です。助成金が受けられないと嘆いているだけでは「受けられない体制」を自分で選んでいる事になるのではないかと反省させられました。
(有)魚こう林百合恵
各務原養護学校が雇用企業を見学(株)若菜(海部:津島地区)8月9日
人を大切にする企業を地元で見つけたい

昨年10月の「第9回障害者問題全国交流会」で同友会会員の経営姿勢に接した各務原養護学校から、「ぜひ雇用企業を見学したい」との申し入れがあり、今回の催しとなりました。各務原養護は就職率のたいへん高い、知的障害をもつ人達の学校です。当日は学生本人・親・先生、総勢百名が参加されました。現場では既に就職している先輩とあいさつをかわし、元気にのびのびと働く姿に触れ、新たな気持ちをもたれたようです。PTA会長は「人が大切にされていると肌で感じた。今後は親も一緒になって地元で人間尊重企業を発見していきたい」との感想を述べられました。障害者問題委員会では、「障害者の就職には親が企業に対する正しい理解を持つことが大切」だと考えており、今回もよい機会となりました。
【記事務局・岩附】
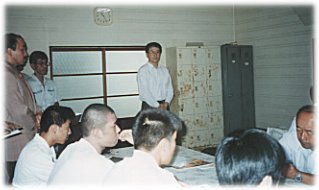
「励まし、励まされて」(見学を終えて)山田謹一(株)若菜・社長
当日は暑い日でしたが、遠い所を元気に皆さん到着され、興味深げに見学して下さいました。現在、養護学校の卒業生が2名働いています。入社5年目の鈴木君は、生産部とパッケージ部の大事な橋渡し役を元気に駆け回って、やってくれています。2年目の山田君も、根気が必要な奈良漬部の仕事をコツコツと真面目に、勤めています。弊社は同業の他社と違い手作りの工程が多いのですが、地道にやり続けること、物を作ることの大切さ、そしてその中で一所懸命働いている二人の先輩の姿をしっかり見ていただけたと思います。質問も活発に飛び出し、私達もさわやかな、なごやかな気持ちになった1日でした。