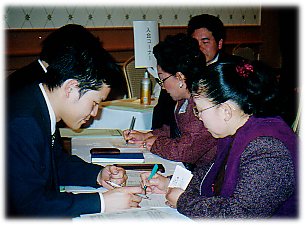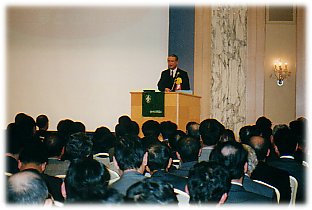名古屋支部(1月31日)
新春セミナー&賀詞交換会
367名が集う

1月31日、名古屋支部主催の「新春セミナー&賀詞交換会」が開催され、久々の好天にも恵まれたこの日、会外経営者53名を含む367名が参加しました。21世紀の幕開けを記念したこの講演会では、大阪・兵庫・滋賀の各同友会で活躍され、最近では中同協行事にも登場される大槻眞一氏(阪南大学経営情報学部教授)に登場していただきました。「見つけよう、21世紀の中小企業の夢と戦略」と題して、「市場のニーズを敏感に捉え、身の回りの経営資源も最大限に利用しながら、中小企業の得意技を活かした経営をめざそう」と講演されました。引き続いて、実際に身の回りの些細なヒントを大学の支援も受けつつ、ヒット商品を開発した大阪同友会の2名の会員経営者に、事例報告をして頂きました。実際の体験に基づいた報告内容だけに、参加者全員が真剣に耳を傾けていました。会場を移しての賀詞交換会では、今年度発足した名古屋支部として初めての行事とあって、業種別のテーブル分けがされ、会場では盛んに名刺交換が行われていました。また、会場内に設けられた入会コーナーにはこの日入会を希望された経営者の方が続々と集まり、六名の方が入会の申し込みを行いました。


記念講演「見つけよう21世紀の中小企業の夢と戦略」
大槻眞一氏阪南大学経営情報学部・教授

●国際的にも高まる中小企業への期待
21世紀を迎え、情勢はますます不透明です。今、企業戦略を立てる上で、2つの潮流を見ておく必要があると思います。一つは中小企業への期待が国際的に高まっていることです。ここ10年くらいの国際的な会議の場では、「中小企業が景気の要ではないか」というようなことが、ささやかれて来ました。その声がだんだん大きくなった1996年、OECDで「中小企業こそ雇用、イノベーション、経済成長の要である」という勧告文を出しました。日本もこのOECDには加盟しているわけですから、当然、知っているわけです。翌97年には、今度はILOが「雇用の問題では、中小企業の活性化が不可欠。各国は充分な中小企業対策を」という決議をしています。最近では、EU首脳会議で「小企業のためのヨーロッパ憲章」が採択され、「小企業はヨーロッパ経済の柱だ」と言っています。日本でも、大阪府の産業再生プログラムの前文に「大阪の産業再生の主役は中小企業である」と書かれています。つまり、21世紀は日本を含めた世界中で、中小企業が最も重要視される時となっているのです。
●日本経済を見る視点
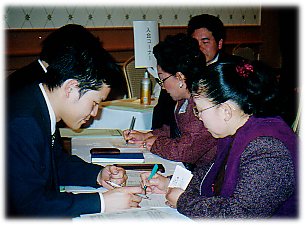
もう一つの潮流、これはあまり芳しくない話ですが、1月21日、日本政府は景気観測を下方修正しました。「回復速度が少し遅い」というわけです。これには3つの要因があると思います。まずはアメリカ経済の影響です。90年代に好況を続けてきたアメリカ経済に翳りが見え、国民が消費を手控えるようになりました。GEやGMといった大手企業が20%近い生産調整をやろうとしています。アメリカの経済が停滞してきますと日本の貿易が伸びませんので、日本経済も足を引っ張られるという結果になります。2つ目は日本の国債・地方債が666兆円という膨大な額になろうとしている問題です。このような国家財政が、収入と支出が均衡するのは大変難しい問題です。国債発行残高はどんどん増えると言われており、いずれどこかでキャンセルしないといけないという大きな負担が残っています。3つ目はIT革命です。IT革命は新しいビジネスチャンスであると同時に、現在の仕事がなくなる危険があります。一例を挙げますと、部品調達を世界のネットでやろうという計画があり、「エブリシング・オーバー・ジ・インターネット」、つまり「全部インターネットでやる」ということが言われています。1社が始めたら、業界全部が後を追うことは確実です。全企業がネット上で部品調達をすることはないと思いますが、今まであった仕事のかなりの部分が減るでしょう。中小企業の役割が大きくなり、世界各国で期待される一方で、日本経済をめぐるさまざまな問題点がある、こういう時代の流れです。ではこの中で、私たちがどう夢を追いかけ、戦略を立てればいいのかについて、一つの事例として、大阪産構研の話をさせていただきます。
●景況調査から研究会が発足
大阪の景気は非常に変わった動きをします。全国的に景気が悪くなると、大阪の景気は真っ先に下がり、景気が回復してきますと、今度は一番遅れて回復するのです。90年代の大不況の中、産業構造がどう変わろうとしているのか、産業はどうなっているのか、これを同友会として調べようではないかと、93年に「大阪産業構造研究会」ができました。会員企業300社を対象に景況調査(定点観測)を行い、学者が加わって、会員と検討会をやっていました。そのうち会員から、「調査が大事なのはわかるが、もう少し突っ込んで対策もやれないだろうか」という意見が出て、業種別に3つの研究会が生まれました。後にこれらの研究会は課題別に4つに再編され、この中の「新製品開発と公的資金利用」のチームが発展して、『オンリーワン研究会』が発足しました。
●公的利用なんて簡単や

研究会発足の初日の事件です。10数人の会員が集まり、「公的制度の利用をどうするか」と口火を切ろうとすると、ある会員さんが前に出てきて「公的利用なんて簡単や。中小企業創造活動促進法(中創法)をとれば、融資も含めて多様なサービスが受けられる。皆でこの施策を取ったらええ」と言うのです。いきなり研究会の方向が決まったわけです。中創法は各都道府県に申請し、提案されたテーマを知事が見て、「まったく新しい事業だ、商品の開発だ」ということで認定します。認定を受けると、府から銀行に、「お宅が取引きしている会社は知事が認定しました」という連絡が入ります。これだけで信用量が違います。信用保証協会の保証を受けながら、融資を受けることができます。他にもいろいろなサービスメニューがあります。それから続々と中創法にメンバーが挑戦しました。新商品の開発というと機械金属加工メーカーなどイメージされますが、二番目にとったのはは植木屋さん、3番目はパーマ屋さんといった具合です。
●大学の研究室に8社が入る
さて98年の年末の忘年会のことです。忘年会といってもドンチャン騒ぎをするのではなく、「泊まり込みで呑むけれど、その前にちゃんと勉強しよう。龍谷大学や立命館大学、県立研究所を見学し、そこの代表者を呼んでいっしょに飲もう」という、いたってまじめな忘年会です。見学先の龍谷大学にはREC(龍谷大学エクステンションセンター)という施設があり、十幾つのレンタルラボを持っていました。先生は大変親切だし、部屋代も安い、地下のレストランは大学なのに生ビールも出るし、既に入室しているメンバーもいて内情も分かり、見学者たちはたちまち気に入ってしまいました。その夜、一杯飲んでいる最中、「一室6万4千円だけど何社かで入ったら割勘にならへんか」という人があり、大学も「一回検討してみましょう」ということになり、結果「何社かで入ってもいい」という話になりました。ただし、知事の認定をとった企業、つまり「何を商品化するか」というネタをもった企業に限るという条件と、その卵を龍谷大学の理工学部の先生が指導するという二点の確約を取ったら良い、ということになり、ともかく八社が入りました。
●大阪から全国に飛び火
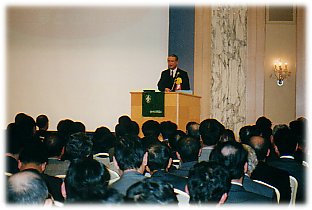
こういった動きは、周囲の同友会にも飛び火しつつあり、兵庫同友会では「アドック神戸」というグループがつくられました。これは兵庫同友会の「製造部会」の中に、特に共同受注・共同開発をやろうというメンバーが集まったものです。この「アドック神戸」の特徴は、準備会の時から神戸市の方が複数で参加していたことで、市の中小企業振興公社の方や県の工業技術センターの方も一緒になって準備が進められ、一昨年42社で旗揚げされました。最初の仕事は製薬会社の分包機で、この試作機が好評で、二号機、三号機と注文が入っています。滋賀同友会にも「Hip滋賀」が発足しました。「大阪同友会の九社が滋賀県下の龍谷大学にレンタルラボを借りている。しかも華々しくやっている」というので、「我々もやろう」と昨年21社で発足しました。今はまだ方向性を模索している段階ですが、こういった「公的制度を使う」とか、「グループで共同受注をする」とかいった動きが、全国に広がりつつあるのです。
●経営環境をつくりあげていく弾みに
さて一番初めにできた大阪のオンリーワン研究会も、例えば、大学や研究機関や行政とのパイプはもっと太くしていくといった仕事がまだまだあります。今後大勢の会員が認定を受け、助成策を積極的に使いながら、「フォーマットを簡潔ににして欲しい」とか、「大勢が助成金の申請をしていますから、もっと枠を広げて欲しい」とか、制度自体の内容を変える要望を出すといったことも必要になるでしょう。それは単に補助金が取れるかどうかの問題ではなく、実は、日本中の中小企業が補助金を受けやすくするという経営環境をつくり上げていく弾みにもなります。もう一つ、龍谷大のレンタルラボに入ったグループの中で、「一緒に仕事をしよう」というグループが出てきました。仲間との連携です。ここから、大阪同友会の中だけではなく、他府県の同友会と一緒に仕事をするような全国的な動きになってもいいではないかと思います。このように見てきますと、「大阪の例は偶然ではないか」と思われるかもしれませんが、私は偶然ではないと思いますし、法則性があります。
●ヒントは身の回りに

経営者の皆さんは、自分の仕事をしている時、やはり自分の本業のことを考えます。「こうしたらお客さんが喜ぶのではないか」「これは不便だから、なんとかならないか」ということを絶えず考えています。自分の技術分野には自分が一番詳しいはずですから、その中で「どうしたらもっとよくなるのか」を絶えず考えています。しかし、アイデアが浮かんだとしても毎日忙しく、実験してみたりどこかに聞きに行ったりする時間がない、いつのまにかせっかくのアイデアが眠ってしまうことが多々あります。こうならないためには、積極的に外部の力を使うことです。最近は大学も敷居が低くなり、相談しやすくなりました。大学の知恵を借りる、行政から支援金を出してもらう、いろんな外部の力を借りて、そのアイデアを実現していくことです。
●見極めたい「時代のトレンド」
しかし一方では、アイデアを出す時「時代のトレンド」を考えて頂きたい。世の中には、いつの時代でも「このことだけは確実に実現する」というトレンドがあります。今でいうと高齢化です。景気に関わりなく高齢化します。女性の社会進出、情報化、豊かさの追求、環境、国際化、都市化などなど、考えていくと、人々の行動が解ってきます。そういうことが「本業とのかかわりで何かヒントにならないか」という見方で、時代のトレンドをきっちり見るということが大切です。さらに大切なことは、グループ化を図ることです。一社だけでは難しいと思うようなことでも皆で議論し、「あそこはこうした」「こんな知恵を働かせた」「大学とはこんなつきあいができる」、こういった情報交換をすることがとても大切なのです。そういう観点で、最初に現代の2つの潮流と言いましたが、この潮流を乗り切って、21世紀の中小企業家の夢を実現するための戦略を立てていただきたいと思います。
【文責事務局・井上一馬】
開発事例(●大槻先生の講演の中に出てきた「開発事例」)
【事例1】発泡スチロールで作った門柱(造園業)
阪神淡路大震災でブロック塀が倒れて怪我をした方がいます。「重いから怪我をするわけで、発泡スチロールなら安全じゃないか」という発想で、発泡スチロールの両側の表面に「FRP」という強化繊維の入ったプラスチックを入れました。そして燃えたり、倒れたりしない工夫をして、それでいて10分の1の費用でできました。
【事例2】二系統水圧バランサーの開発(配水管工事)
深夜電力を利用する貯湯式給湯器は、法律により水圧を低く押さえられているため、湯水混合時には、湯と水の圧力の差により水温が安定しない上、シャワーなどの水圧も低く、2階への設置が不可能な場合もありました。この製品は、個々の湯水混合栓ごとに設置する小型のもので、他に電気などのエネルギーや、その他の付属設備などは一切使用せずに、2系統の水圧を平均化することで、解決をはかりました。
【事例3】EM菌を使った排水処理システム(切削加工業)
有用微生物群「EM」は、その抗酸化作用が、土地改良材などに活用されますが、加工用機械の切削後、洗浄液の中にEMを入れておくと、液がほとんど腐敗しないという特徴を生かしています。
【事例4】木目調ハンドバッグ製造(服飾デザイン)
グッチやシャネルなどのブランドメーカーに、自分の企画した商品を見せ、そのブランド名で販売しています。ある時、木を薄くむいて、木目を生かした、ハンドバックや時計のベルトのデザインができないかと思い、龍谷大学のプラスチックの先生の指導を受けます。シリコン樹脂を流したら扱えるようになり、商品化に成功しています。
【事例5】圧力を加えたマグネシウム合金の鋳造(鋳造業)
最近、携帯電話の液晶部分が大きくなってきました。ボディとしての高い強度が求められ、軽くないといけない。それにはマグネシウム合金が最適ですが、この合金は冷えるときに収縮が大きく、ひび割れを起こしたり、形が歪んだりします。そこで、圧力を加えてそのまま冷やすというやり方を研究中です。
【事例6】トイレット用のペーパーホルダー(金属加工業)
身障者の方で、手が不自由で、トイレで紙を取り出すのに引っ張り出してちぎるのが困難な場合があります。そこで、モーターで紙が出て、ボタンを押せば水分含くんだプラスチックが紙にあたってそこが切れる、そういったプラスチックの研究をしている方もいます。
事例報告(1)
産学連携でインパクトのあるものをつくりたい
小野逸二氏レイシスソフトウェアーサービス(株)社長

●4〜5年間、失敗を繰り返して
当社はソフト開発をやっています。これまで、人をたくさん採用し、「人×売上」という形態で、業績をあげてきました。製品を作るとか、サービスを高めるとかということは、それまでまったく考えていませんでした。10年程前、人材銀行に行きましたら、たくさんの人材リストがありました。その人たちを活用し、「私達も世の中に便利になるような製品やサービスを提供できないだろうか」と思い始めました。製品を作っていく段階で、「どんな製品を作ればいいのか」と考えました。大企業と同じものをつくっても勝てません。何かトップシェアのもの、日本初のもの、あるいはインパクトのあるもの、そういうものをつくっていきたいと思いました。4〜5年間、失敗を繰り返しましたが、「どうしても製品を世の中に出していきたい」という強い思い入れがありました。
●RECに入室研究生の協力も得て
そんな時、同友会から大阪産構研の案内があり、さっそく勉強会に参加しました。産構研で「産学連携」の勉強会に参加しました。しかし東大の教授と日立製作所の社長の講演で、話を聞いても「うちにはとても無理だ、できるわけがない」とあきらめました。ところが、龍谷大学を見学した時、龍谷大学のRECの方に懇意にしていただき、「一度やってみたらどうだ」ということで、入室させていただきました。教授のサポートのみならず、研究生の皆さんにも開発の援助や完成品のチェックをお願いしました。さて、当社が開発したソフトは手話学習辞典のソフトで、聾唖連盟のサポートを受けて開発させて頂きました。このソフトをつくる為に、教授のほうから「音声と映像の融合」についてのサポートをいただきました。またこのソフトには、2000の例文が入っており、声は龍谷大学アナウンサー部の学生の協力で、音楽も龍谷大学の卒業生に協力していただきました。
●2008年には株式公開をめざす
次に、「オフィス内の仕事で疲れた人がリフレッシュできるソフトを」ということで、ストレッチ体操のソフトをつくりました。技術的には、「ある動作と次の動作の間を動画でつなぐ」という技術を教授と相談したり、ストレッチのノウハウを大阪体育大学の教授から教わったりもしました。今、IT時代といわれています。当社ではこういうサービスを商品化していきたいと思います。当社の21世紀のビジョンは、現在40名の社員を100名にし、売上高を百億円に、2008年に株式を公開したいといっております。当社にとってまだまだ大きな夢ですが、皆さんと共に発展していければと思っています。
事例報告(2)
誇れる財産を持ち、世界一のメーカーに
吉田信隆氏メディカルデータバンク(株)社長

●20人の会社でも世界一になれる
当社は、歯医者の下請けをやる「入れ歯屋さん」をやっていました。ある日、テレビで、社員20人の企業を「世界一の企業」といって取り上げていました。私は、それまで「世界一」というのはホンダとか、松下とか、トヨタとか、そういう大企業のことだと思っていました。その会社は、技術が世界一で、ある部品が世界の8割のシェアを持っているということでした。「そうか、20人の会社でも世界一になれるんやな」と思い、さっそく「メーカーになろう」と決意したんです。
●ヒントは日常にある
私が最初に入ったのは、入れ歯に名前(ネーム)を入れる技術です。病院や老人ホームでは夜中に入れ歯を洗いますが、形が似ているのでよく間違うんです。間違えてはめると、間接病を起こすことがあります。入れ歯には、普通は削って名前を入れますが、私は転写印刷してコーティングする技術で特許を取っています。ここに「フィットネス」という商品があります。これまでのマウスピースは上の歯にはめていましたが、これは下の奥歯にはめます。この商品は、女性が「噛むことで頬が引き締まって小顔になる、ダイエットになる」ということで、話題になっていますが、実際は奥歯を保護するものです。皆さん「新しい商品のタネなんかない」と言いますが、本当は自分の仕事の延長線上に全部あります。社長なら「こんな商品あったらいいな」と、考えたことがあるはずです。それが商品のネタです。これは何がネタになったかと言いますと、ある野球選手が引退した時、「奥歯がガタガタや」という話を聞いて、その奥歯を保護するものはないか、ということで開発しました。これからは、リハビリ用や身体障害者向けのマウスピースを開発していきます。噛むことで頭を活性化することができ、ボケを防止できるとも言われています。
●積年の悩みがたったの1分で解決
大学との連携はどこにあるかというと、この商品は、湯に入れて柔らかくして歯形を取ります。この時に頭に浮かんだのは、どうしてもゴムの匂いがするということです。匂いを消すために「味を入れる」ということは、どうしても分からなかったんです。たまたま先生に聞きましたら、1分で解決です。私達だけだったら、何年もかかって開発しなければいけないものが、大学の教授とコミュニケーションで、たった一分で解決。これだけなんです。大事なことは特許を出すということです。特許を出さないと、中小企業はどんないい商品を作っても必ず盗まれます。特許が通れば、その商品は日本に一つ、世界特許が通れば世界に一つになります。これが、仕事に対していちばんの自信を与えてくれます。自分にも自信が持てます。「これは私の発明だ、財産だ」ということを誇れます。それが、産学連携なのではないかと思います。
【文責事務局・井上誠一】