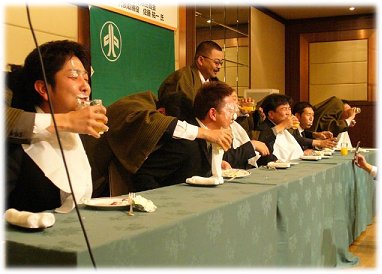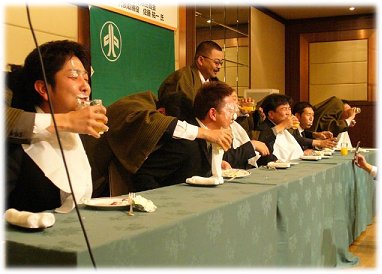青同連協・2月合同例会
2月23日
集え!学べ!掴み取れ!〜青年経営者307名が集う

分科会形式で開催
青年同友会の2月度合同例会が2月23日に開催されました。1995年から6年間続けた「産学アカデミー」(日本福祉大学と共催)以来となる分科会形式の合同例会とあって、7月から実行委員会を組んで半年以上の準備が重ねられてきました。5つの分科会の概要が固まった11月以降は、実行委員会も分科会ごとに分かれて打合せを行い、プレ報告も回数を重ね、前日まで念入りな準備が重ねられました。当日は307名の会員が会場に集い、メインテーマにある通り、学び、掴み取る例会となりました。

身近な会員企業から学ぶ
記念講演は「経営者に必要なモチベーション」と題し、(株)羽根田商会の佐藤祐一氏が報告しました。第1分科会では、「こんな会社はいやだ」というテーマで、(株)誠和の東栄賢氏が人材採用の目的について報告しました。第2分科会では、「家業から企業への脱皮」というテーマで、(株)まるはの坂野豊和氏が永続的に発展する会社を目指す報告がありました。第3分科会では、「おもいの継承」というテーマで、真和建装(株)の杉浦昭男会長と晴英社長による、創業者から後継者へのバトンリレーの話がありました。第4分科会では、「出来ていますか、会社のしくみ」というテーマで、(有)大矢設備の大矢静生氏より、経営指針の浸透の秘訣についての報告でした。第5分科会では、「現状維持は後退、前進なき企業は縮小するのみ」というパネル討論形式で、(有)トレネッツの藤掛誠一郎氏、(株)CRMの松村祐輔氏から、新たなビジネス創出に向けて実践事例を報告しました。懇親会では、8つの青年同友会の新旧地区会長が、二人羽織で息の合ったところを披露。スムーズなバトンタッチを占うユニークな企画に会場が笑いの渦に包まれました。

青年同友会連絡協議会
合同例会
2月23日
基調報告
基調報告の(株)羽根田商会の佐藤氏の話は、何のために会社を経営し、何を目的とするのか。その目的のためには何をしなければならないのかについて報告頂きました。「お客さんの喜ぶ顔を見たい」そのための戦略、方針を作り上げ実戦する姿は、私たちの心に強く感じました。また、各分科会も盛り上がった事は言うまでもありません。これらの学びを今度は自社に生かしたいと思います。(有)丸安 伊奈 幸洋(尾張南青同)基調報告者の佐藤氏は「あなたは、生まれ変わってもこの仕事を、やりますか」と問いかけます。最初は、社員に見向きもされなかった経営指針発表会。回を重ね、社員・取引先・銀行・同友会のメンバーを交え良い雰囲気の中で開催されたことで、社長の想いが少しずつ会社に浸透し始めました。結果として、佐藤氏が社長就任後に採用した社員数が、全体の半数を超えた時に、戦略の浸透が数字として現れるようになりました。自社・自身の位置を確認するためにも、より同友会活動に参加することを認識した基調報告でした。
(株)高橋技建 佐藤 裕之(名古屋第3青同)
第1分科会
第1分科会は、経営者と社員のコミュニケーションできる環境が報告者の東氏の会社には仕組みとしてあることを知りました。人を採用するのは、経営者としてはその人の人生を背負うことになります。採用の目的は、仕事や組織の活性化のためだと思いますが、経営者が社員さんに年をとっても働け、やりがいを持たせられる環境を提供することが必要で、これも共育の一つの形なのかとも感じました。
東海EC(株)石井 元博(名古屋第2青同)
第2分科会
第2分科会のテーマは「家業から企業への脱皮」、報告者はまるはの坂野氏でした。家業とは自分がいなくなったら衰退してしまう会社、企業とは自分がいなくても永続的に維持発展していける会社だといいます。我が社は家業で、企業の感覚がわかりません。自分がいなくても永続的に維持発展できるのなら、自分の存在意義はどうなるのか。どちらがいいのかグループ討論しました。会社を大きく発展させたいのなら、やはり企業化を目指したい。ならば、自分がいなくても維持発展していくように会社・社員を育てる事が今からの仕事だと思いました。田中モータース(有)田中 啓貴(名古屋第3青同)第2分科会の報告内容は、「まるは」創業者である梅さん(豊和氏の祖母)の創業当時のお話などを導入に、成長過程での家業的な経営がもたらした問題点や取り組んだ改善策などを、時系列に沿って説明頂きました。坂野氏は、経営者が突然いなくなっても、衰退することなく永続的に維持・発展をしていける会社を企業と位置づけました。また、同友会での学びの実践として、理念をわかりやすくまとめた社員全員配布のカードを披露されるなど、家業を企業にかえるため同友会を最大限生かされている実践報告を語って頂きました
(株)リプラス 柳町 正樹(尾張西青同)
第3分科会
第3分科会では、事業継承の成功例として、新鮮で沢山のキーワードを頂きました。印象に残ったのは、「継承であり、交代ではない」という会長の言葉でした。継承とは理念の継承であり、スタイルはどうでもいいが大切なものは譲れない。それを伝えるため、仕事のやり方については、一切口出しはしないが、お客様や職人さんの悪口を言った時には、本気で叱ったそうです。また、社長はコミュニケーションを大切にし、仕事の話は何でもして、「立てるところは立てる」を常に意識してきたそうです。報告から、素晴らしい理念の引継ぎだと感じました。
(株)丸二商店 岩田 竹生(名古屋第2青同)
第4分科会
第4分科会の報告者は、尾張東青同の大矢会長でした。「出来ていますか?会社の仕組み」をテーマに経営指針の重要性を報告していただきました。実際の大矢設備の来期経営指針書をサンプルに、各テーブル配って頂きました。その指針書のユニークな例は、社員に意識調査を匿名で書いてもらい、その結果を掲載したり行動指針書に対してどれだけ功績があったかを表彰し、社員のモチベーションを高める仕組みを構築されていることです。大矢氏は、同友会から勉強したことを自分なりにビジュアル化したそうです。それを社員さんと作り上げることによって、もっとすばらしい指針書が出来る。そんな学びがあ合った分科会でした。
カニエ電機(株) 蟹江 晃男(尾張南青同)

第5分科会
第5分科会では、新規顧客開拓・新規事業立ち上げについてパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、テーマに沿って様々な角度から切り込み、パネリストの現在に至るまで、社業発展のためどのような取り組みをしてきたかを聞きました。大切なことは、経済状況を踏まえお客様が本当に求めるもの、一番喜んで頂ける方法を考えること。そして、それに自社の強みをあてはめ、事業として成り立たせ、新規顧客・新規事業につながっていくことです。今例会を通して、新たな出会いと新たな気付きを得ることができ、自社の発展につながる有意義な時間を過ごせたと思います。プラスアルテ 松山 一郎(名古屋第1青同)第5分科会で学んだことは、市場の分析(お客は何を求めているのか)と自社の得意技(自社は何を提供できるのか)のマッチングが重要なポイントであり、他社がやらないことを積極的にやることが大切だということです。パネラーへ今後の夢について質問があった時、「理念の追求です」と答えた言葉が心に残っています。
会社を継続的に発展させて行くには、何事も「理念ありき」「目的ありき」「ビジョンありき」これが重要だと思いました。
ラックプロジェクト 日比野 弘章(名古屋第3青同)