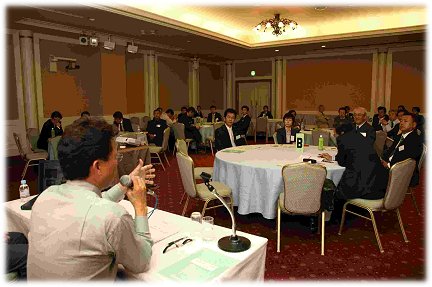第48回定時総会・全体会
4月21日
『知りあい、学びあい、励ましあい』の活動を展開
4つの分科会で会方針を深める

あるべき姿を議論
第48回定時総会が4月21日、メルパルクNAGOYAで開催され、会員や来賓、行政関係者等を含め360名が参加しました。総会議事に先立ち、①「中小企業憲章制定の『語り部』に」、②「地域力を活用した自立型企業づくり」、③「『企業変革支援プログラム』で経営課題を浮き彫りに」、④「経営に誇りと喜びを〜経営指針と社員共育」をテーマにした四つの分科会が行われ、会方針を深めました。特に第1分科会では、今年7月に開催される中同協創立40周年の総会で発表される「中小企業憲章草案」に到る経過と同友会理念の深化について中同協相談役幹事(前会長)の赤石義博氏より、地域の自立的な発展のために、経営者や中小企業のあるべき姿の報告がありました。また中同協「企業変革支援プログラム」(同友会のめざす『よい会社・経営者』の姿と経営者がすべき事を述べた「労使見解」の視点で、自社経営を診断し、課題を明らかにするためのツール)についての報告と活用方法が語られました。
支部再編成で会員と地域に密着
引き続き行われた総会議事では、「経過報告」「決算報告」「会計監査報告」の承認と新年度役員の選出が行われ、会長に山本栄男氏/(株)サカエ、代表理事に新井敏男氏/(株)アライ等44名の新しい理事が選出されました。新年度方針として厳しい経営環境の中、『知りあい、学びあい、励ましあい』の同友会精神の原点にかえること、中小企業憲章や中小企業地域活性化条例の制定、支部再編成(9支部・48地区)による会員と地域に密着した活動づくりなどが提案され、承認されました。

第48回定時総会分科会
いまこそ同友会理念の本質を掴み実践
第1分科会《同友会運動への期待》
幸せの見える社会づくり
赤石義博氏中同協相談役幹事
人間の素朴な願い
第1分科会では「中小企業憲章制定運動の『語り部』になろう〜幸せの見える社会づくり」と題して、中同協相談役幹事の赤石義博氏に報告していただきました。赤石氏は全体を通して中小企業憲章にとっての3つの課題を「人間としての素朴な願いを実現できる社会をめざす」、「現実の地域、人々のくらしの繁栄を確かにしていく社会をめざす」、「すべての生命の母体である地球環境の保全、資源の節減、人類永遠の存続と繁栄を頭においた経済社会の実現をめざす」ことであるとのべました。そして、自社での「全社一丸体制づくり」の経験を通して、「生きる・くらしを守る・人間らしく生きる」ということが「人間としての素朴な願い」であることを学びました。それは「労使見解」に一貫して流れる「人間尊重の精神」にもつながっており、時代が推移した今でも国民的課題となっています。
かつての厳しい時代
またオイルショックや1930年前後の世界恐慌の頃を例に出して、「現在の厳しい経済状況は、決して100年に1度の不況ではない」と述べました。そして、「こうした不況がたびたび起きるからこそ中小企業憲章が必要」と強調しました。「今後は地域が1つの産業に依存することなく、地場の産業を盛り上げ、地域内で循環する経済にしていくことが重要」と締めくくりました。参加者各自が「語り部」となって制定運動を推進していくための「中小企業憲章」の意義について学びを深める分科会となりました。

第2分科会《地域力の活用》
地域力を活用した自立型企業
山口義行氏立教大学経済学部教授
野長瀬裕二氏山形大学理工学研究科教授
小出宗昭氏(株)イドム社長
自社のあり方を見直す
第2分科会では、山口義行氏、野長瀬裕二氏、小出宗昭氏の3名をパネリストにお招きし、中小企業の次の一手を考えるパネル討論をお聞きしました。まず、山口氏から国内外の情勢変化と、中小企業の置かれている現状を専門家の切り口からお話いただきました。現状を踏まえた上で、今なすべきことを明確にし、マクロの視点を持って、長期化する不況に立ち向かうべきだと山口氏は言います。そして、この不況をチャンスと捉えて、もう1度自社のあり方を見直す必要性があると、提起しました。一方、多くの中小企業は、自社製品をどう売ってよいのかなど、マーケティングに課題を抱えていると小出氏は言います。また繰り返し「どんな企業も他社にはない強み、セールスポイントが必ずある」と指摘します。第3者の目をうまく活用することで会社の強みを発見し、自分1人では見い出せなかった市場が確立できることを実例を挙げて紹介しました。
人的ネットワークを
多くの企業に接している野長瀬氏は、自身の見てきた「生きた情報」から成功している会社の実例を紹介しました。「モノ作り」とは、人と人とのぶつかり合いが不可欠であり、足りないものを補いながら業種の枠を越えて知恵を繋いでいくことだと野長瀬氏は言います。
最終的に重要となるのは、会社の規模だけではなく、人間力です。人的ネットワークこそが全てをつなぐキーワードであると感じました。今回3名のパネリストの報告に対し、「経営の参考になった。明日から実践したい」といった前向きな感想が寄せられました。厳しい中でも、広い視野で、行動していけばおのずと進むべき道は開けるという確信の持てた分科会となりました。

第3分科会《企業づくり》
自社発展の確かなステップ
加藤明彦氏エイベックス(株)社長
徳升忍氏(株)ドライバーサービス社長
自社を分析する
第3分科会では、コーディネーターの説明のもと「企業変革支援プログラム」の設問に回答して、自社の経営成熟度を6段階で自己診断することから始まりました。診断結果から、自社の現状を5項目(①経営者の責任、②経営理念を実践する過程、③人を動かす経営の実践、④市場・顧客及び自社の理解と対応状況、⑤付加価値を高める)で分析し、レーダーグラフで視覚化することにより、経営課題の抽出をしました。パネル討論では、パネリストの加藤氏と徳升氏がプログラムを実施した結果、自社の経営課題に対して、どのように取り組み実践してきたか、経営指針から社内での人を生かす組織作りの観点で事例報告を頂きました。経営理念・指針を含めて、できている所とできていない所をもう1度見直して経営課題の抽出を行い、計画が悪いのか、方針が悪いのか見極めて対応しなければならないとのことでした。
同友会理念に沿った経営分析ツール
パネリストへの質疑応答の後、各テーブルにて自社の経営課題の気づきとこのプログラムを自地区で今後どのように活用していくかをテーマにグループ討論が行われました。本プログラムは、自社の成熟度がどのレベルにあるのか確認する入門編(ステップ1)で、次にどのように経営課題を克服していけばよいのか経営分析をする本編(ステップ2)は現在作成中とのことでした。同友会理念に沿った経営分析ツールとして、自社分析ができるプログラムを実際に体験することにより、現在の自社の立ち位置を確認することができました。また、将来の自社のあるべき姿を目指すためには、どうしたら次のレベルにいけるのかを知るきっかけとなりました。

第4分科会《同友会を自社に生かす》
経営に誇りと喜びを
新井敏男氏(株)アライ社長
経営指針に衝撃
第4分科会では、同友会での学び方、実践方法を知ると共に、経営指針作成の意義を深めました。新井氏は仲間の経営指針書を見て衝撃を受け、指針勉強会に参加しますが難しくて挫折します。指針ができない理由は、自分に理念がないからでした。しかし、当時3期連続の赤字が続き、指針は必須だと思いました。結局新井氏は、借りてきた言葉をつなぎ合わせて作成しました。ところが、指針発表をした際、腕のある社員ほど辞めていきました。それでも指針を貫けたのは同友会があったからと報告されました。
指針作成後の変化
指針を作り、発表をすることで指針のような会社になっていくことを実感しました。支部長時代、尾張、名古屋、三河それぞれの支部長の指針発表会に参加し合い、ライバルとして刺激を受けました。そして、お互いの良いところを取り入れ社内で実践しました。さらに現在では、毎朝30分間社員との面談を実施しています。面談では、社員の良さを見つけ、指針に沿って話をしています。社員を認めることで社員も社長を認めてくれるようになり、定着率も良くなりました。社員との関係を確立し、社員がやりがいを感じ、自己実現のできる経営をしていく必要があると強調されました。最後に座長より、「労使見解をベースにした三位一体の経営を回していくことが同友会の学びです。また、個々の企業を強くすることを通して中小企業の社会的環境を良くする活動を行っています」とのまとめがありました。
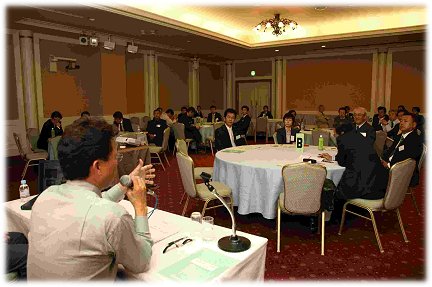
第1分科会詳細
「中小企業憲章」制定運動の『語り部』に〜幸せの見える社会づくり
赤石義博氏(中同協相談役幹事)
中小企業家同友会(47都道府県で組織、中小企業経営者約4万名が加盟)では「国民や地域と共に歩む」ことをめざしており、中小企業憲章の制定を広く国民運動として提起しています。現在、「中小企業憲章」の草案づくりが進んでおり、今年7月9・10日東京で開催される中同協総会で『会内資料』として発表される予定です愛知同友会では憲章草案やその背景を学ぼうと、4月21日の定時総会に中同協相談役幹事(前会長)の赤石義博氏を招いて、「中小企業憲章制定運動の『語り部』になろう〜幸せの見える社会づくり」をテーマにした分科会を設けました。

◆「中小企業憲章」とは
日本の経済・社会・文化及び国民生活における中小企業・自営業の役割を正当に評価し、豊かな国づくりの柱にすえることを国会が決議し、憲章の精神を実現するために、現行の中小企業基本法をはじめ、諸法令を整備・充実させる道筋を指し示すものです。詳細は以下のホームページ参照。http://www.doyu.jp/kensyou/
中小企業憲章でめざすもの
憲章の課題
中小企業憲章が何をめざしているか、第1に、「人間としての素朴な願いを実現できる社会をめざす」です。第2に、「現実の地域やくらしの繁栄を確かにしていく社会のあり方の実現をめざす」ことです。そして最後に、「すべての生命の母体である地球環境の保全や資源の節減、つまり人類永遠の存続と繁栄を頭に置いた経済社会の実現をめざす」ことです。この3つが憲章制定の目的であり、私たち同友会では制定することによって、これらを確かなものにしようとしています。
憲章の理念とは
この3つのことをひとくくりにして中小企業憲章の理念のあり方を明確に示す必要があると思います。第1の「人間としての素朴な願いを実現できる社会をめざす」ということは、「市民的な権利」を実現すること、人間としての尊厳、自由、平等、連帯といった基本的な願望を形にすることです。第2の「具体的な地域経済やくらしが守られていく仕組みをきちんとしていく」ということは、「政治的・経済的な権利」の確保です。第3の地球環境の保全、資源の保全を図って子々孫々にまでつないでいこうということは、「社会的権利」といえます。
働く権利を保証する
これらの「権利」をひとつの憲章で実現していくということですが、逆に言うと日本は基本的人権が尊重されるはずなのに最も重要な基本的人権のひとつである「労働権」、働いて生きていくという権利が充分に保証されていません。縦社会で縦型の政治や法律だと言われていますが、横の生命線がなくなっています。そういう縦になっている壁を中小企業憲章で突き破っていくという特徴がある訳です。
挑戦できる土壌をつくる
このように中小企業憲章は極めて普遍性があるだけでなく、縦になっているものの整合性を常に確かめていくという特徴があり、総合性があると言えます。また、中小企業経営者のみならず個人が様々な分野へ挑戦できるような土壌をつくる力にもなります。これらは全ての国民の前で白日に晒された議論の中から生まれてくるものですから、公開性を持っているという側面も大きな特徴になっています。これらのことから中小企業憲章は、その壁を突き崩すような整合性のある存在として役割を果たすものであると考えられるのです。

同友会理念「人間尊重の経営」
社員の要望を聞いて
私は1959年に東亜通信工業に入社、26歳の時でした。入社の動機は創業者に乞われたからです。当時、東亜通信工業は社員が100名近くいましたが、創業者の社長以下、幹部全員が技術屋でしたので、義理もありどうしてもと頼まれて上京しました。当時は労働運動が盛んでしたが、そんな中どうすれば全社一丸となって仕事に打ち込めるかという取り組みを始めました。私からは、ただ質問することだけにして、意見とか評価をまったく言わずに社員の話を聞き出しました。そのときの質問で「働く上で何が1番大切な課題なのか、どういうときに働きがいを感じるのか」ということについて聞くと、圧倒的に「子供の教育」という答えが多かったのです。
「自主・民主・連帯」
これらのことは同友会理念のひとつである「自主・民主・連帯」の「民主」につながる「生命の尊厳性の尊重」、「あらゆる人間は平等な存在である」という人間として極めて素朴な願いです。それから「かけがえのない人生を悔いのない内容で生きたい」という答えが聞き出せました。「本当に自分に合っているのか、これでいいのか」と悩みながら働いているのが本当の姿なのです。これは「自主」の深いところの意味を表しています。その次に「だからといって、仲間からつまはじきにされるようにはなりたくない」という答えが出てきました。お客さんや仲間からも認められるようになりたいし、仲間はずれにはなりたくないのです。実はこういうことが整理できたのは、30年ほど後になってのことですが、よく考えてみると、自分自身が自主性を大事にしたいとか、民主的なあり方を大切にしたいということを願ってきたのは結果として、「人間尊重」ということをずっと考えてきました。
「大企業に追いつく」
入社後、私は社員と対話したり業界や技術的なことを考えながら1年かけて経営計画をつくりました。入社当時年商1億5千万円ほどでしたが、25年後、グループ全体で100億円を突破しました。「とにかく大企業に追いつこう」と一生懸命ひとりあたりの付加価値を高める努力をしていきました。そして77年には完全週休2日制も実施しました。私がまず取り組んだのは、中小企業が成り立っていくためには、理屈抜きに全社が一丸となって頑張っていくことが必要である、そのためには「人間尊重」の経営が必要であり、その精神は「労使見解」に脈々と流れているということです。
企業内での努力だけでは限界
しかしそういうことを私達が企業内努力だけでやっていても限界が出てきます。経営環境と言いますと、すぐに金融や税制や法的な育成政策などを考えますが、もう一方では医療・教育・社会福祉などの充実が、第3の賃金として非常に大きな力となります。自分で動いていくということを確かにするためにも、そして中小企業憲章にあります「市民的な権利」を強めていくためにも、必要なことなのです。

今日的状況から「中小企業憲章」を考える
「100年に1度」ではなく危機はたびたび訪れる
「現実の地域やくらしの繁栄」ということへの課題については、昨年のサブプライムローンの証券化による問題が起きてから大変なことになっていて、「100年に1度の危機」といわれています。しかしこうした不況は、日本でいうと第1次オイルショックや1929年アメリカ発の世界的大不況など、たびたび起きています。このように何度も起きていることを考えると「100年に1度しかこないのだから仕方がないのだ」とあきらめるわけにはいきません。ですから、中小企業憲章が必要になってくるのです。
全国1位を誇る愛知
実は愛知県は他地域と比べると大変良い条件を持っています。産業生産額と工業生産額が全国1位です。自動車機器類の製造業も全国第1位です。それから農業生産額は全国6位ですし、瀬戸物や友禅など様々なものが幅広く生産されています。可住地面積は57%以上あります。ではなぜこんなに大変な状況なのかというと、愛知県は輸送機械産業が51%で依存度が高いのです。金額はこのままでいいですが、比率は30%ぐらいにして他のことをもっとやらなければいけません。
地場での循環産業
このあいだテレビで二酸化炭素の排出の問題を取り上げた番組を見ていたら、「そんなことを考えていたら日本の国際競争力が落ちていく」という人がいました。しかし国際競争力が高まっても地球が無くなったらどうにもなりません。これでは本末転倒といえます。国際競争力と地球の命のどっちが大切か考えなければいけませんが、同時に飯を食べなければいけません。そのためには地場で循環する産業をどれだけ工夫して確立していくかが大切な時期に来ています。
地域経済をどう見るか
このように現状の問題から考えていきますと、冒頭の3つの課題を2つの側面から見ていただきたいのです。ひとつは「地域経済をどう考えるか」です。既存の中小企業の繁栄、活性化です。私は大企業や企業誘致をだめだとは申し上げていません。素材産業など長期に渡って高額な投資をする場合や、発電所などのように膨大な投資をして長期に渡って回収する場合は大企業か国家でないとできません。しかし名古屋城の石垣が大きな石の間に小さな石がきっちりと噛み合っているように、中小企業でなければできない仕事もたくさんあります。
地球環境の問題
また「地球環境」について考えてみますと、大企業は国際競争力の観点から見込み生産をしますが、それによる資源の濫費があります。20世紀は15億の人口が60億と4倍になりました。そして原油の1人あたりの消費量は5倍に増えていますので、全体では20倍の消費量になっているのです。自然の再生力を国連が調査して換算したところ、1999年の数字で再生可能な経済規模、資源消費規模を超えていたのです。だから中小企業憲章の課題として「環境問題」を絶対に外すことはできません。
中小企業だからこそ
このことを自分たちのこととして日常の仕事でやれるのは、地元にしっかり足を付けている中小企業だけです。ですから3つの課題を実現していかないと地球も人間も危なくなるのです。人類が絶滅してもいいと言うのなら、私はこれ以上なにも申し上げません。そうでないということなら、もう1度、中小企業憲章について考えてみましょう。
(文責:事務局・黒田)