第13回あいち経営フォーラム分科会(2)
【第4分科会】理念経営が地域と未来を創る
〜経営理念で「競う」から「つながる」へ
石田 篤則氏 三敬(株)(豊川・蒲郡地区)

経営理念を持ってはいても、実践できているでしょうか。その理念は自社・周囲に浸透しているでしょうか。
衰退する地場産業の中で、もがき苦しむ悪循環の日々から、同友会に出会い経営指針を作って大きく変わった石田氏。「経営って何」「働くって何」「人って何」など、根本的なことを考え抜いた時に「幸せの創造」という揺るぎない経営理念を確立します。こだわりの商品で顧客から支持を獲得し発展していく経緯や背景が報告されました。
理念への共感、社員が評価される喜び、士気高い職場、より良い商品づくり。そして地域から必要とされる企業へと、理念経営のスパイラルに大きな成果を感じました。
討論では、わが社の社会的役割と存在意義(使命)は何か、それは周囲に伝わっているかを話し合い、理念の実践こそが経営者の仕事であることを再確認しました。
(株)深谷鐵工所 深谷 貴久(尾張南青同)
【第5分科会】何をどう次代へつないでいくのか
〜永続企業の条件とは
杉浦 昭男氏 真和建装(株)(岡崎地区)

日本の中小企業は創業から30年を境に、廃業か倒産をする傾向があると統計上いわれています。永続企業を築くためにも創業の精神を受け継ぐことが大切です。そして改革のためには後継者が若いうちに渡すことが必要だと杉浦氏は考え実行しました。
若いエネルギーは、事業改革も社内改革も意欲的に進めます。先代は後継者への協力ができ、早い段階から継承すれば急な外部環境の変化にも対応できるといいます。創業以来社員と培ってきた「理念」「方針」「計画」、それら共有する財産のすべてを次代に繋ぐことが、永続企業の条件であることを学びました。
杉浦氏は最後に、事業継承を「箱根駅伝」に例え、血と汗と涙をタスキでつないでいくことが必要だと話しました。私自身も5年後に事業継承をする計画を立てています。後継者には、真和建装のように「同友会での学びが共有できる人材」であることを望みます。
(有)児玉工業 児玉 直樹(港地区)
【第6分科会】人が育つ職場づくり
〜信頼関係を築く就業規則
佐藤 邦男氏 アジアクリエイト(株)(豊川・蒲郡地区)

就業規則作成の過程を通じて社員との絆を深め、「共育」を実践している佐藤氏。その報告を聞き、「社員との信頼関係を築くための工夫」「社員の力をいかに発揮させるか」をグループ討論しました。
報告では、活用され、社員に周知されてこその「生きた就業規則」であること。作成の過程を通じて「理念を共有し、理解して文書に落とし込むこと」ができ、社員同士、また社員と会社との信頼関係が深まったことが語られました。トラブルも減り、会社風土も変化したそうです。
討論では、信頼は相互関係の証であり、社員にとって安心・安全に働くことができる環境作りがその第一歩であることを確認しました。
また、社員の力を発揮させるためには「あてにし、あてにされる」関係が土壌にあることが必要で、役割や期待を明確に周知することがポイントとの意見が出ました。
社会保険労務士山嶋事務所 山嶋 紀之(愛北地区)
【第7分科会】あなたもできる新卒採用
磯村 太郎氏 (有)サン樹脂加工(愛北地区)

サン樹脂加工は、社員数26名の樹脂加工会社です。社員の高齢化を解消しようと始めた中途採用では、社員が定着せず悩んだといいます。社員の「仕事は面白いけど、この会社は面白くない」の一言が磯村氏を動かします。
このままでは会社が行き詰ってしまうことを自覚し、会社の将来像を描くために経営指針を作成しました。できた経営理念をもとに同友会の共同求人で新卒採用に取り組みますが、失敗も多く、苦難が続きます。社員に経営理念が浸透するには時間がかかるのです。
その間、社長の考え方も社員を尊重する方向へと変わります。新卒採用活動が3年目を迎える頃には、社員が積極的に採用や新人の育成にも関わるようになりました。
中小企業にとって経営者の思いが共有できる新卒採用の意味や、採用活動によって会社が変革していく様子が伝えられ、将来の夢の実現への取り組みも報告されました。
(株)ヒューマンリンク 和田 康伯(中区北地区)
【第8分科会】自主性を発揮できる環境
〜共に生き・育つために
出分 洋之氏 (株)昭和写真工業所(名古屋第1青同)
植田 健男氏 名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授
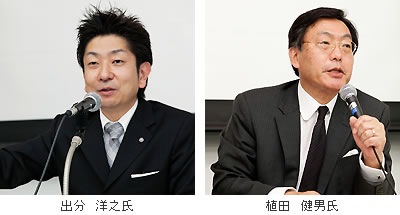
出分氏は家業を継いでからの数年、結果が出ないことを社員のせいにしていましたが、実は自分(経営者)に原因があったと気づきます。そして人間関係の苦労、古参社員との衝突からどう会社を立て直したかを報告しました。すべてのベースは「人」であることに気づいて以来、自ら率先して指針書を作成、行動し社員との信頼関係を築いています。
植田先生は、人間の発達と教育の観点から「人の育ち(人間的な自立)」について何が重要かを研究しています。生きることは学ぶことであり、働くことである。学習とは、自分で生きるために考える力を付けること。「共育」「人材こそ最大の資源」等から、「教育とは何か」と「何のために経営するのか」に共通点を感じました。
最後に映画「学校」の1シーンの鑑賞があり、「本当の幸福とは何か」を改めて考えさせられました。
(有)ワコー 山田 文信(名古屋第1青同)
【第9分科会 見学】働くことで社会とつながる
〜「働きたい」を応援する企業へ
タイヨー機械(株) (稲沢地区)

今回の見学分科会は稲沢市内のタイヨー機械にお邪魔しました。小ロットの自動車部品・事務用機械部品の組立を手工業で生産している工場です。バスの移動中、会社概要の説明とともに生産されている部品が回覧されました。
到着後、まずは工場見学。従業員約120名のうち13名が障害のある人でしたが、それとわからないくらい皆さん黙々と作業に集中していました。
工場見学の後、小出社長、佐織養護学校の進路指導の近藤先生、障害のある子を就職させたお母様の話が続き、あっという間に時間が過ぎていました。
小出氏の「生きることは社会と繋がること。働くことで社会と繋がる」「夢を実現させるために、その手段として利益を上げる」という言葉が印象的でした。働くこと、育むことの楽しさに満ち、清々しい余韻が残りました。
弁護士法人 名古屋E&J法律事務所 吉江 仁子(昭和地区)
【第10分科会】時代に流される経営から脱出
〜地域に新しい流れを創ろう
大竹 路恵氏 hair & beauty 路美容室(瀬戸地区)
森 靖雄氏 愛知東邦大学地域創造研究所顧問

最初に森氏より「汎グローバル化」の意味の説明があり、既に日本はグローバル化が生活の中に入ってしまっていることがわかりました。そのために今後、日本での経営も海外進出も、スタンスがしっかりしていないと大変なことになると感じました。
また、今は米国式競争戦略の時代ではなく、EU式の共創時代であるといい、それは同友会の理念にも共通するものです。イタリアのブランドバッグの話は佐藤氏の基調講演に通じる部分もあり、わかりやすい報告でした。
大竹氏は、特に意識して中小企業憲章を実行してきたわけではないといいます。自分の家族や社員を守るために行動してきたことが憲章の項目のいくつかに則っており、地域の関わりが条例につながり、憲章にもつながっていくという報告でした。
条例、憲章がこれから生活に必要で、身近なものと感じられた分科会でした。
コットンアリス 川合 裕史(港地区)

