第13回あいち経営フォーラム分科会(3)
【第11分科会】ポスト震災復興の経営戦略
〜国内外の経済環境の変化を読む
瓜田 靖氏 中小企業家同友会全国協議会政策局長

「ポスト震災復興」と題して、日々目まぐるしく変わる国内外の経済環境につき、瓜田氏より被災地の中小企業の現状から最新の経済環境まで幅広い報告をいただきました。震災後の情報が氾濫する中で実際に被災地をまわり、生の声を聞いた氏の報告には説得力があり、疲弊する日本経済の中で中小企業の見地に立った今後の戦略などは参考になりました。
グループ討論では、震災後に明らかになった自社の弱みを交流し、現在までの自社の景況から業界の状況まで意見交換をし、自社事業の将来性、業態の見直しといった「時代を味方にできる経営戦略」について討論しました。
今日、時代のテンポが速すぎるため、それに対応しながら自社のオリジナリティーをどう出すかなど、変化に対応した勝ち残る体制作りをしなければ取り残されると感じました。
(有)ミズノ企画 水野 淳司郎(名古屋第3青同)
【第12分科会】自分の会社を好きになると 弱みが強みに見えてくる
小林 真作氏 (株)小林ゴールドエッグ(徳島同友会)

「自社の宝の活かし方を変えた。他にやっていない強みがあるはず」。小林氏は、大きな気づきが生まれた2つのきっかけを語りました。
1つ目は、経営指針書を作成したこと。同友会に出会い経営指針書を作成したことで視野が広がり、たまごを食べると健康寿命が延びるという論文を発見します。健康寿命を深く知ったことで初めて自社の理念が腑に落ち、会社が好きになったといいます。
2つ目は、他社との違いを追求したこと。鶏を飼っていないのは弱みだと思っていましたが、たくさんの農場と取引を行い、たまごの種類も豊富なため、料理によって使い分けができることを社員の意見から知りました。
物事の見方や磨き方を変える事で、それまで気づかなかった大きな発見があり、強みに変えられる。「社員は会社にとって宝であり、たまごを通して元気になることが喜び」と語る姿が輝いていました。
クリアリレーション(有) 柴田 佳苗(尾張東青同)
【第13分科会】縮小する市場で生き残る
〜顧客は創る、戦う市場は探し出す
宇佐見 孝氏 宇佐見合板(株)(中川地区)

少子高齢化で市場縮小といわれていますが、日本全体が委縮しても、すべての企業が縮小するわけではありません。合板業界という紛れもなく縮小した業界に立ち向かってきた宇佐見氏の報告は、まさにそれを証明してくれました。参加者からは100年企業の条件への質問などが相次ぎました。
グループ討論では、参加者が自社の抱える縮小のリスクに際して、環境適応企業として生き残るために今日から何に挑戦するかを話し合いました。異業種同士だからこそ感じる率直な意見が交わされ、変革への第一歩を踏み出す後押しになりました。
宇佐見氏の「会社は、縮小という外からの圧力でつぶされるのではない。内圧でつぶれる」という言葉も印象的でした。同友会の人間尊重の経営の大切さを感じた内容になりました。
人事労務マネジメントひととき 水野 由里(熱田地区)
【第14分科会】新商品・新サービスへのチャレンジ
〜何のためか本質を見失わない戦略
花井 義一氏 (株)亀屋芳広(熱田地区)
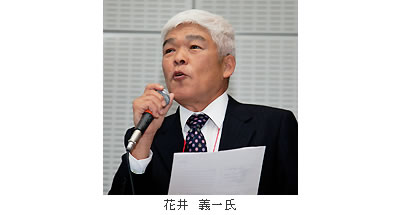
売上低下を食い止める新商品・新サービスの開発とはどうあるべきかというテーマに対して、花井氏の答えは単純明快、「やってみること」でした。気力・体力・根性で乗り切れた昭和60年代までとは違い、創造型・提案型の経営戦略がないと生き残れない。しかし、それを発想・実現できるのはやはり「人」であり、「人」を動かす力になるのが「経営指針」である。このような本質からのお話には説得的がありました。
また「経営指針」について、作ったという自己満足で終わるのではなく、指針のもと常に自社分析を繰り返すことこそがチャレンジの原動力となるのだということにも、改めて気づかされました。
グループ討論では、新商品・新サービスの創造、提案を従業員から汲み上げるための姿勢が討論がされました。
弁護士法人 名古屋南部法律事務所 岡村 晴美(熱田地区)
【第15分科会】付加価値の創造
〜小さな市場の小さな需要を大切に
三品 富康氏 (株)浅井歯科技研(知多北部地区)

この分科会には「付加価値」という甘美な響きに吸い寄せられた80名近い参加者が集いました。
報告者の三品氏は、自身の経営体験から、付加価値は「人」であるとの答えを導き出しました。社員一人ひとりが「何のために仕事をしているのか」を日常の業務の中で問いただし、組織的に学びあう風土が大切だと語ります。
三品氏の報告には、同友会で伝え続けている「経営指針」「人間尊重」などが盛り込まれていました。特別なことではなく、それらを実践することで付加価値は創造できるのだと納得がいきました。
参加者からは「良い意味で期待を裏切られた」「勇気を頂いた」「理念が大切」などの感想が出されました。
付加価値を見出すことは実は簡単で、それは日常の業務の中に潜んでいます。しかしそれは常に変化し、だからこそ学び続ける必要があるのです。この分科会で商売の原点を見た思いがしました。
専門館LLP 岩田 公貴(尾張西青年同友会)
【第16分科会】出会いを力に 仲間と共に
〜思いの共有から生まれる新市場
畑野 吉雄氏 (株)中央電機計器製作所(大阪同友会)

連携できる人間は「出会い」を大切にします。例えば、移動中の電車や飛行機、仕事帰りの居酒屋でも、隣に座った方との「一期一会」を大切にします。見知らぬ方にも気軽に声をかけ、もし名刺交換をすることができれば、ビジネスの可能性も生まれます。ネットワークづくりなくして連携は生まれません。
ビジネスとしての成功を求めるならば、それを意識し現実を改善する強い意志と、成功を手繰り寄せる信念が必要です。「ダメもと」で連携しても成功はできません。ただ、「金儲け」だけの連携は、途中まではうまくいっても、ほとんどが金銭問題で破綻してしまうそうです。
仕事は連携なくして成立しません。人と人のつながり、情熱と行動力、頑張り続ける忍耐力、そしてなにより成功させるという強い「信念」が大切であるのだと改めて感じました。
古澤デザイン事務所 古澤 毅 (北地区)
【第17分科会】農業の新時代
〜新たな価値の創造
坂上 隆氏 農業生産法人(株)さかうえ(鹿児島同友会)

「農業というキーワードを通して、不明確な時代の中で閉塞感から脱却し、新たなビジネスモデル構築のヒントを得る」という趣旨に興味を引かれて、農業以外の業種から多くの方がこの分科会に参加しました。
10年の試行錯誤と現在の成功を可能にしたのは、「自分は農業で生きる。ここ鹿児島でやる」という坂上氏の決心でした。「幸せは自分の心にしかない」「自分でルールを決める」「最終的なお客さんのことを考え、求められるホットストライクをどう作るか、どう見せるか」といった言葉から、哲学を持ち、お客様のニーズに応えるため不可能を可能にしてきた歴史と、これからの力強い未来を感じました。
グループ討論では「自分がやりたいことではなく、いかに必要とされる仕事をするか」に注力している人が多いことを知りました。武士のような坂上氏のあり方に触れ、胸が熱くなりました。
アプリオリ(有) 冨田 高子(豊川・蒲郡地区)

