第14回あいち経営フォーラム
第14回あいち経営フォーラム 基調講演(11月12日)
感動のオンリーワン企業を目指して
十河 孝男氏 徳武産業(株) (香川同友会)
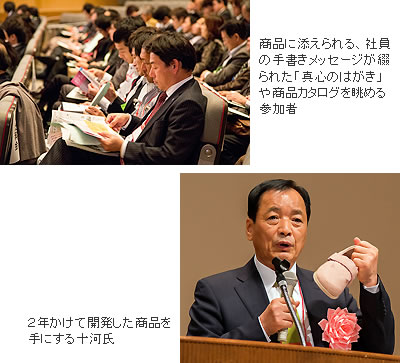
義父への感謝
徳武産業は、1957年、私の家内の両親が手袋の縫製の下請けとして創業したのが始まりです。私と家内が結婚してから15年程経った頃、義父から「徳武産業を継いでほしい」と申し出があり、承諾しました。
それから間もなく義父が倒れ、急逝します。義父の意を汲み社長に就任した私は、会社を成長させようと新事業に挑戦しますが、古参社員たちは否定的な返答ばかりで、先代の売上を超えることもできず、次第に社長としての自信を失っていきました。
転機は3回忌の時です。寺の住職に弱音を吐くと、「心の中で義父を追い越してやれと思っとるやろ。先代社長はあなたに会社を託し、命をかけて事業継承をしたんやから、感謝の気持ちを忘れたらあかん」と諭されました。それからというもの、毎日仏壇の前で感謝の言葉とともに、会社での出来事を報告するようになりました。
将来をかけた事業転換
その数カ月後、新しい仕事を社員に持ちかけると、肯定的な答えが返ってきて、ルームシューズなどのOEMビジネスが進んでいきました。売上も増え、若い社員も入り、会社が活性化し始めます。
ところが、取引先である大手通販会社の担当者が変わった途端、当社に対する風向きが変わりました。
そんな矢先、高齢者施設を経営する友人から「高齢者のための靴を作ってほしい」と相談を受け、OEMビジネスに限界を感じ始めていた私は挑戦することに決めました。そして、神戸の技術者に指導を仰ぎながら、2年かけて高齢者用ケアシューズ「あゆみ」を開発しました。
ピンクの靴の奇跡
ある時、高齢者施設の方から「徳武産業は、歩けもしない人にシューズを売るのか」と、クレームを頂きました。その靴の持ち主は、3年間寝たきりだったのです。施設内でピンク色の靴を履いている人を見かけ、「自分も歩きたい」との願いを込めて買ってくれたものでした。
それから半年後、施設から「おばあさんが歩いています」と連絡が入りました。さっそく駆けつけ、おばあさんの手を取り「おめでとう」と言うと、「ありがとうございます。死ぬ前にピンクの靴で歩きたいと神様にお願いしたら、願いを叶えてくださったの」と、涙を流しながら話す姿に、この仕事をしていて本当に良かったと思いました。
その方にとってピンクの靴は、布とゴムでできた履物ではなく、歩くことを通じて人や自然と触れ合い、生き甲斐を取り戻すための大切な道具になっていたのです。これからもお客様の役に立つ靴を作り続け、地球上で一番感謝を頂く靴メーカーになりたいと思います。
経営フォーラム分科会
【第1分科会】
必要とされる社長の自己変革
〜社長のリーダーシップで会社は変わる
加藤 三基男氏 サン食品(株)(瑞穂地区)

加藤氏は、「親孝行」と「世界中に蒟蒻を広める」という夢を持って入社し、会社の売上も右肩上がり、社業拡大の一途でトントン拍子でした。しかし、2008年に原材料費の高騰で経営の危機に直面し、社員との関係もギクシャクし始めます。
そんな中、父親が糖尿病を患い、糖尿病患者を救いたいとの思いから、蒟蒻の特性を活かし血糖値を上げない商品開発に挑戦。業績が悪化していた社内からの反発は大きいものの、夢と希望と「決めたことはやりぬく」信念を持って社員と対話を重ねます。次第に社内に理解が広がり、雰囲気も好転していきました。
社内が混乱していた頃は、うまくいかないことは全て他人や環境のせいにしていたと加藤氏は振り返ります。全てを受け入れ、自己を見つめ直してからは、周囲の見方に変化が感じられるようになったとの報告に、自分が変わらないと社内は変わらないと痛感した分科会でした。
(株)共栄産業 手縄 実
【第2分科会】
ピンチの時に、あなたの社員はそばにいてくれますか
〜社員から信頼される社長をめざして
明石 耕作氏 (株)豊梱 (豊川・蒲郡地区)

明石氏は10年前、38歳で父親から社長業を引き継ぎました。ある日、入社5年目ぐらいの、信頼していた優秀な社員が突然、2人も辞めてしまいます。明石氏は、自分が社長として社員から信頼されていたかを振り返り、1つの誓いを立てました。それは、「行動をして意識を変えよう」ということです。
社員は社長のことを、見ていないようで見ています。明石氏は、なるべく社員と共に行動するようにしたところ、いろいろな問題点などが耳に入るようになり、今では問題点を一緒に解決し、だんだんと良い信頼関係を築けるようになったとの報告でした。
グループ討論では「信頼関係」をテーマに90分かけて討議し、コミュニケーションの大切さや、社長に意見を伝えられる環境づくり等の意見が交わされました。座長からの締めの言葉「信頼関係とは、永遠のテーマ」との言葉が、印象深く響きました。
(有)テクノヒート 井手 義人
【第3分科会】
右腕(No.2)との育ち合い、高めあい
〜共に学び合う風土
濱垣 一郎氏 師勝化成(株) (西春日井地区)

「一郎君は今後、会社をどうしていきたいの」。ほぼ同期入社の彼に言われた突然の質問に、濱垣氏は全く答えられなかったそうです。その彼というのが現在の右腕です。
このままでは非常にまずいと思った濱垣氏は、それを機に経営について真剣に考え、熱心に勉強するようになりました。経営理念の成文化から指針の作成、ISOの取得など、同友会での学びの実践にも励みました。いつもそばには彼がいて、色々な話し合いをし、想いに呼応してくれたそうです。
右腕は誰でもなれるわけではなく、共に育つ組織づくりの中で頭角を現す主体性を持った社員こそ資質があり、右腕になり得るのではないかと濱垣氏はいいます。また、その土壌として会社の方向性、指針、役割分担等を経営者が明確にする必要性にも触れました。
最後に座長から、「社員が育つ環境をどう作り上げていくかが重要」との言葉があり、締めくくられました。
(株)ナカシマ 中島 圭
【第4分科会】
「しあわせ」な事業継承のために
〜継続企業への挑戦
石黒 俊朗氏 (株)サカエ (豊明地区)
菅原 直樹氏 (株)菅原設備 (名古屋第4青同)

「他人継承」で社長を継いだ石黒氏。入社6年目に現会長より「次はお前だ」と言われ、新卒採用や新技術の開発、商品化に取り組み、同友会へも入会しました。「会社は社会の公器」と常々言っている会長の12年をかけた事業継承は、双方が「理念を共有できている」同友会らしい事業継承だったと振り返ります。石黒氏自身も、16年後に次の後継者にバトンを繋げるべく実践をしています。
「同族継承」「M&A」の報告をした菅原氏。職人気質な社長である父とぶつかり合い、同友会で学べば学ぶほど現状に不満が募る中、相手の立場に立つことを学び、社長を「担ぎ上げる」大切さを痛感し実践。M&Aでは、前経営者・社員との信頼関係に苦戦しながらも、「相手が人生を賭けてきた会社である故、敬意を払い、全てを引き受ける」と覚悟し経営をしているとの力強い報告でした。
グループ討論では、同友会らしい事業継承の実現のため活発な討議が行われました。
(株)みつわ 近並 崇
【第5分科会】
作った経営指針、やれないのは何故
〜社内での展開と実践するための課題を考える
伊藤 智啓氏 (株)蒲郡製作所 (豊川・蒲郡地区)

人工衛星の部品製造などでマスコミの話題になる蒲郡製作所も、経営指針の実践では紆余曲折があったと知り、身近に感じながら学び合える分科会でした。
創業者はワンマンで、伊藤氏は「社員とは一線を画す」ように育てられたそうです。引き継いだ直後に会社は危機に陥り、同友会に入会後、経営指針と共育の学びが始まりました。しかし、経営理念を作っても社員は「理念より給料だ」と反発、さまざまな学びを導入しても場当たりで継続しない状態が続きました。
ある時、会員企業で学んだ社員が「3Sをやりたい」と言い始めたのを転機に社内が変わります。トップダウンではない社員の自発性が持つ力の大きさを実感しました。またリーマンショックの危機で社員間に一体感が生まれ、社長の指針からみんなの指針へと進化中との報告でした。
会社の進むべき道を明確にすると同時に、社員との信頼関係を構築することがいかに大切かを共有し合いました。
生興(株) 古谷 晴義
【第6分科会】
生きたビジョンでこれからの時代を切り拓く
〜経営理念からのビジョンづくりへ。5年後、10年後の我々の姿は
水戸 勤夢氏 (有)アーティストリー(中村地区)

第6分科会では、まず「同友会の目指すべき経営ビジョン」について議論をし、「ビジョンの定義」を行いました。水戸氏からは自社の経営ビジョンとして、「イノベーションで夢の実現」を目指し、「対応力、完成度、協力体制」で業界のトップランナーになる、オリジナル家具を消費者の身近なものにする、が発表されました。
グループ討論では、「5年後、10年後に何を目指し、どのような姿になりたいか」「描いたビジョンを社内でどう伝えていくか」をテーマに討議しました。経営ビジョンを持っておらず、5年や10年後の将来が見えない参加者が多い中、自社の目指す方向性について考えました。
この分科会で、経営ビジョンとは経営方針の前提となる具体的な会社の将来像であり、ビジョンを社員と共に話し合い、共有し、方針の細部を見つめ直していく経営が必要であることを学びました。
(有)忠圀鋏製作所 磯村 幸男
【第7分科会】
金融機関に評価される経営指針とは
〜具体的な実例に学ぶ計画作り
中嶋 修氏 板橋区立企業活性化センター・センター長
徳島 孝志氏 徳島興業(株) (南地区)

中嶋氏は、自社の倒産を経験した元中小企業経営者です。それゆえ、企業活性化センターのアドバイスでは常に企業に寄り添い、「一緒に再生への道を探そう」という思いで、経営難に陥った企業を救済しています。
まず、中嶋氏はトップが資金繰りを熟知することが大事であるといいます。また、金融庁の方針が経営改善・事業再生の支援に大きく舵を切ったことで銀行も変わりつつあるといい、「我々のような支援拠点に相談して情報を得てほしい。自分自身が変わらなければ会社は変わらない」と呼びかけました。
徳島氏は金属リサイクルの会社を経営しています。鉄の売り買いは相場に左右されるため、売上計画書を作っても意味がないと以前は思っていたそうです。
しかし、自社の格付を知り愕然とした徳島氏は一念発起し、管理会計に基づいた5カ年計画を作成します。「作って分かったのは、計画書は銀行との共通言語だということ。数字をベースに話ができる」と実感を込めて話しました。
(株)まるぜん 野々山 達也

