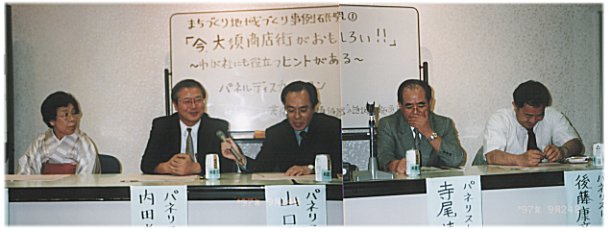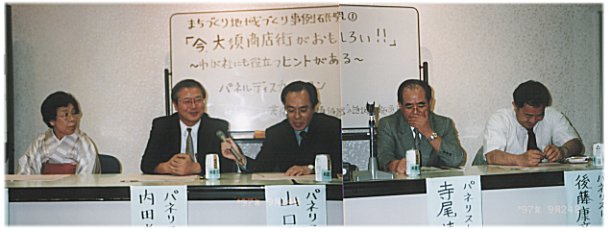地域開発委員会大須地区共催9月24日
今、なぜか大須がおもしろい中野 俊治氏(大須商店街連盟会長)
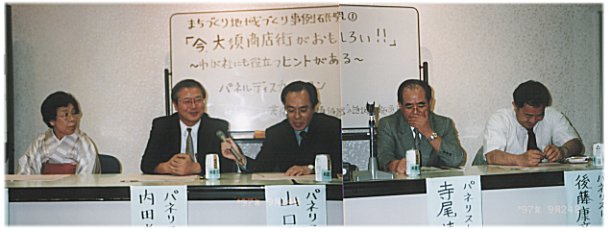
パネリストの皆さん(左から杉野氏、内田氏、山口氏、寺尾氏、後藤氏)
地域開発委員会では九月二十四日名古屋中郵便局会議室で、今年度第一回目の「まちづくり・地域づくり研究会」を大須地区と共催で開催し、七十名の方が参加しました。大須在住の五名の方より「自社と大須」を語っていただいた後、「今、大須商店街がおもしろい!」と題して、大須商店街連盟会長の中野俊治氏より、約七十分間の講演を頂きました。(以下は講演要旨) なお当日の、パネリストは次の方々でした。
● 杉野美代子氏㈱やっこ●内田孝行氏 九十九電機㈱●山口哲氏㈱スタジオスピーク
● 寺尾清氏㈱メガネの愛光●後藤康文氏(有)嘉木

中野 俊治氏
団塊の世代、がんばる
大須の歴史は古く、門前町として栄え、芝居小屋や寄席、芸能や娯楽、飲食など、普段の暮らしとはちょっと違うおもしろさがあり、名古屋一の繁華街でした。しかし戦後、人々の生活が大きく変わり、幹線道路と交通網のおかげで「陸の孤島」となり、スーパーなどの大型店全盛の頃はまったく客がいなくなり、本当にひどい有様でした。そのどん底の昭和五十年、「何とかしなくては、何とかしたい」と、当時三十代の私達団塊の世代の熱い想いが「アクション大須」と結びつき、これが今日の「大道町人祭り」と発展したのです。
熱意と知恵と汗と
アクション大須の一番の成果は、「何かやればこんなにも人は来るんだ」という意識が、まちの人間の中にできたことでした。初回の大道町人祭りでは、個人的に銀行から借金する人もいたりして、「絶対に失敗できない」という状況で、計画を練りました。名古屋祭りの日に当て込み、手づくりの「参加する」を全面に打ち出してマスコミをうまく利用。「官の祭りより生き生きしている」と大反響を呼びました。以来、まちの保守的な長老達からも認められ、サマーカーニバルや春まつり、縁日催事と、四季おりおり「年中大須はおもしろい」というまちづくりをやっています。
大須の強みは「人」
イベントの一番のねらいは街に人が来る事です。そしてもっと大切なのは人を育てる事です。若い人達を手足に使うのではなく、自分達で知恵を出し合いながら、やる気を持って積極的に参加できる様な仕掛を作って乗せていく。町人まつりは二十回すべて実行委員長は違います。トップを経験する事により責任感が芽生え、視野が広がり、物事に前向きに取り組む様になる。人間が一回りも二回りも大きくなるわけです。大須の強みは「人」です。何か困ったことがあったら助け合い、情報交換し、刺激し合う関係で、勢いも出てきます。そうした約二十人を中心に四十人程が取り巻き、ガヤガヤと賑やかにやっています。人を育てる、内部的な結束を固める、できることはすぐ手掛け、一つ成功したら更に次へ拡大して。そういう積み重ねを二十年間かけて、ここまでの形になりました。
各店の繁栄が地域全体の繁栄に
川に魚が沢山泳いでいるのを釣るのは腕次第です。あれだけ人が出ているのですから売れないわけがありません。しかし、現実には各店で格差が生まれ、約六十の店舗が入れ替わるなど、競争が激しくなっています。今、大須の土地は大変な人気です。現金でポンと買い取ってしまうのです。常に最前線情報を発信したり、若者の指向を先取りして店に客を呼びこむことで地域も潤います。店の繁盛が大須地域全体の繁栄につながります。私達は朝から夜まで休みもなかなか取れず、父ちゃん、母ちゃん、婆ちゃんで、パートも使っていないところが半分以上です。後継者もいないと非常に厳しく、皆必死で努力しています。大須らしく助け合いながら、よい競争的共存共栄の関係にしていきたいと思います。
人が大勢きても商売できない!
よく商店街の四大問題として、①後継者、②空き店舗、③駐車場、④大型店の進出が挙げられます。これらは全てお客さんが来れば解決できるのです。しかし、一店だけで何とかしようとしたってどうしても無理です。やはりまち全体を何とかしなくては。これは一年や二年では全然できません。お祭ではまちの人がはっぴを着て、ビラ配りや案内役をやります。バイトでなく、地元の人がやるから味がでます。しかし一番辛いのは、「苦しい時から頑張ってきてやっと人が出るようになったのに、今儲けなくて何時儲けるの?」「頼むから儲けさせてくれよ」と言われることです。暇なときは皆も集まりますが、一番人手の欲しい時には忙しくてなかなか出てこないという悩みがあります。まちづくりはソフトとハードと二段階構えでうまく取り上げるのが大切ですが、ハードにはお金が必要です。アーケードも看板もアーチにも、そして道路や案内板にもお金がかかります。来ていただいたお客さんに、気持ちよく喜んでもらい、「また来よう」と思わせるまちにするにはお金が必要です。出したら出した以上に商売でもとを取る、それでまた熱心になる、だから投資は大事というクセをつけて、意識改革を行っていかなければなりません。
人情、ぬくもり、ふれあい、そして楽しさ
我々商店街のもう一つの強みは「住んでいる」ということです。栄や他の地区にはない強さです。半分以上の人がここに住み、大須を愛し、学校のPTA活動や交通安全、近所付き合いなど、日常的にいろいろな地域のことをやっています。阪神大震災でも「どこそこのお婆ちゃんがいた」などの情報を持っていたのは、商店街の人達でした。そうしたすべての要素が絡み合って、この大須のまちの魅力ができているのです。しかし、今の状態がベストだとは思っていません。若者はガラッと変わります。古着屋はもう飽和状態で、最先端の情報関連機器店の進出もこのくらいにして、飲食店やファーストフードを呼びたいと思います。もう少しいろいろな変わったお店があった方が若者の関心もひき、安定したまちになります。子供からお年寄りまですべての人が安心して買い物ができ、食事が楽しめる、来るたびに違う楽しさがあるというまちが目標です。画一的な大型店とは違った「人情、ぬくもり、ふれあい、楽しさ」の味を打ち出して勝ち残りたいと思います。
【文責事務局・加藤】
二〇〇五年の万博を考える
地元の瀬戸で地域開発研究会(仮)が発足
舟越信三名東保険事務所

今年のせともの祭り(写真提供:小林健一氏・(有)大阪電気工業)
五月から瀬戸地区を中心とした会員有志で「二〇〇五年万博が開催されたなら、地元の会員企業の将来や行方はどうなるのか」について、討論の場が持たれ始めました。参加者各自が自由な論議を繰り返し、そこから瀬戸の将来像が生まれて来ればと、すでに五回の会合が持たれました。十月七日には今までのまとめを行ない、「三五周年の事業である『フォーラム』と『記念出版』に参加する」との結論を見い出しました。
夢を語れば「瀬戸小江戸構想」も
今、全国的にも注目されている瀬戸市。多くの経済団体や色々なグループが万博に向けて、街づくりやイベントを提案したり、都市改革のビジョンを発表したりしています。しかし、いずれもそこに住む人間の本音が生かされているのでしょうか。夢を語れば「瀬戸小江戸構想」や「瀬戸おかげ横町」で古い街並みと陶器の技術やガラス工芸の館、参加型観光都市構想などなど、まさに言いたい放題です。私達は同友会の「地域と共に」の声のもと、自身のビジョンを創り上げたいのです。万博跡地の利用を含め、今後の発展に私達中小企業家が関わりたいのです。
学者・研究者の協力も
道路整備や拡張工事だけでなく、中部全体の中での枠組みや、いわゆる「四全総」も見すえた幅広い知識と視野の広い討論が必要です。そこには会員の英知だけではおぼつかない点もあり、学者や専門家の助言が必要となってきます。当面は基礎学力を身につけるための学習が中心です。月一回の開催で参加自由、まさに研究会にふさわしいのでは。