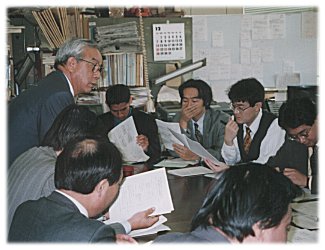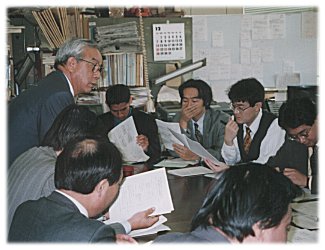「銀行の貸し渋り」実態調査
七割強が「すでに経験」「今後に不安」
十一月期の「景況調査」と同時に行なわれた「銀行の貸し渋り」実態特別調査(情報ネットワーク委員会、政策委員会主催)では、景況調査対象の六百十六社から一五六社に回答をいただきました。ここでは「貸し渋り」とは「自社の経営内容が変わらないのに、銀行の貸し出し態度が厳しくなった」と定義し、回答していただきました。
結果は「すでに経験」が二十一件(一三・四%)、「今はないが今後心配」九十二件(五八・九%)、「今後も心配ない」二十六件(一六・六%)、「同業者には聞いている」十七件(一〇・八%)、その他七件(四・四%)という結果(複数回答)がでました。
公的金融機関への期待が一層高まる
特徴的には回答した会員の約六割が「今はないが、今後は心配」と答えており、来年三月までの早期是正措置(金融ビッグバン)に向けて、会員企業の先行きに対する不安感をうかがわせる結果となっています。また「今後の資金調達について」では、「公的機関(国金、信用保証協会など)にシフトする」という回答が圧倒的に多く、公的金融機関への期待の高まりが、率直に出ている結果となりました。回答の五分の四、百二十名近い方々から「銀行の最近の変化」や「国や自治体の施策に望むもの」での文書回答を頂きました。(以下一部を紹介)
最近、銀行の態度が変わった
◆「物、金でしか見なかったのに、近頃は経営の姿勢を見るようになってきた」
◆「業績を見ながらの態度が変化している。また、ハッキリと担保なしの融資はできないと」
◆最近は,きちんと数字をいうようになった。『いくらでもいいから借りて欲しい』が『御社の抵当では限度が○○円だから、これ以上は無理』とはっきり言う」
◆「最近、支店長が来るようになった。当社の景況調査と思われる」
◆「ある銀行で、融資申込書の保証人が、銀行窓口にて連帯記入及び捺印を求められた(今までは、社内で記入捺印を提出していた)」
◆「決算時の提出書類が、以前は損益計算書と貸借対照数だけで良かったが、前年度より、税務所へ提出するものをすべて要求されるようになった」
◆「『借りてくれ』との言葉が消えた」
長期・低利の融資を(国や自治体へ)
◆「保証融資の枠を増やしてほしい。零細企業に低利息で長期返済をしてほしい」(圧倒的多数の方より)
◆「保証協会の枠拡大、審査基準の緩和、国金など政府金融関係や制度融資に不況対策の新基準や新制度融資を創設すること」
◆「連帯保証人の基準が厳しく、政府系資金が借りられない」
◆「公的資金も、有担保、有保証人であるため利用しにくい。公的資金の借入限度額の引き上げを望む」
中小企業の現実を広く世間にマスコミも注目
中部通産局内で記者会見(12月10日)
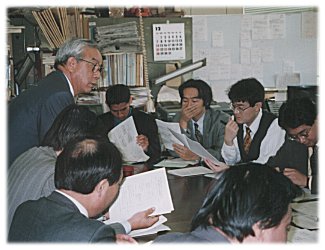
中部通産局記者クラブで(12/10)
愛知同友会では、十一月末に実施した「景況調査」と「銀行の貸し渋り」実態特別調査の結果を受け、十二月十日、中部通産局記者クラブで記者会見を行い、NHKやCBC、中日新聞、朝日新聞、日経新聞など、八社の記者が参加しました。同友会からは佐々木会長、村上情報ネットワーク委員長、斎藤政策委員長の他、舟越報道部長と福島事務局長が同席しました。(調査結果は本紙参照)翌日の新聞では、中日新聞や読売新聞が大きく紙面を割いて報道するほか、朝日、毎日、日経、中経の各紙で取り上げられました。一方、テレビ局では、東海テレビが佐々木会長に取材を申込んだり、NHKからも年末の特集番組の取材の申込があるなど、大きな反響を呼んでいます。

東海テレビによるインタビュー風景
国民金融公庫との懇談会(12月8日)
年末を迎え、景況の悪化や銀行の貸し渋りによる経営者マインドの冷え込みが心配される中、十二月八日、国民金融公庫との懇談会が行なわれました。国金からは名古屋相談センター所長の生田茂樹氏、名古屋支店次長の金森潤氏、同じく融資第二課長の山中康裕氏の三氏が出席。同友会からは佐々木正喜会長、村上秀樹情報ネットワーク委員長、斎藤泰政策委員長など九名が出席し、懇談を行ないました。
率直な疑問や要望を
政策委員会ではかねてから会員の金融アンケートを実施し、その中で寄せられた国金への要望について、斎藤政策委員長が説明しました。①借入申し込みの際、提出書類が多すぎないか。②可否判断に時間がかかりすぎないか。③保証人の人数や資格要件をもっと柔軟にできないか。④借入と返済の窓口機能が分離されている事は改善できないか。⑤一般的資金調達が困難な中小企業を対象にしているはずなのに、一般の金融機関とそう違わないのではないか。⑥経営改善貸付の審査が厳しく、利用しにくくなってはいないか。などの質問をしました。

会員から寄せられた率直な要望を紹介
国金の「緊急対策」
懇談会の後半では、十一月末に行なわれた愛知同友会の景況調査と銀行の貸し渋り特別調査を村上情報ネットワーク委員長が説明。政府系金融機関への期待の高まりを報告しました。これに対し、金森次長は「東海地区中小企業の景況」として国金が九月に調査した景況と、十一月十六日に閣議決定された「二十一世紀を切りひらく緊急経済対策」における中小企業対策の概要を説明しました。①特別相談窓口の設置(済)②代理店(一般金融機関の窓口)の拡大(未定)③十二月一日から「別枠三千万円」の融資制度創設④経営改善貸付の別枠(百万円)を四百五十万円に引き上げ、取り扱い期間を延長(詳細未定)など。最後に、政策委員の小瀬木氏よりの閉会のあいさつで、約一時間半の懇談会を終了しました。
景況感急速な悪化見通しも弱気(愛知同友会11月期景況会議より)
業況が急速に厳しくなってきています。業況判断を「よい」と答える企業はついに全体の一〇%にまで落ち込み、「悪い」とする企業の割合は四〇%にまで達しました。前者から後者を差し引いた「業況判断」DI値は今回△32を示し、本年二月以降四期連続で悪化する(昨年十一月4↓二月△5↓五月△10↓八月△18↓十一月△32)結果となり、調査開始(一九九四年二月)以来最悪です。こうした調査結果には消費需要の落ち込みが強く影響しているものと思われます。本年四月以降の税負担増大、七月以降の天候不順の影響などから個人消費は低迷を続けてきましたが、十一月に入ってから四つの金融機関が破綻するという金融不安問題の影響もあって、その冷え込みはさらに深刻化しつつあります。また緊縮財政政策への転換による公的部門の需要減が見込まれ、官民両面から需要が縮小しつつある状況です。(以下、省略)*詳細は同封した「景況調査報告(第十六号)」をご覧ください。十二月二十二日、三塚蔵相は貸し渋りの要因となっている「早期是正措置」を一部先送りする方針を明らかにしました。
詳細については「調査・研究・提言」の「愛知同友景況調査(97.11月)をご覧ください。