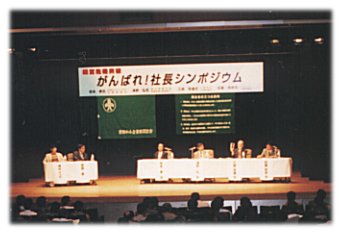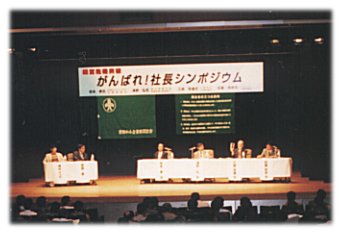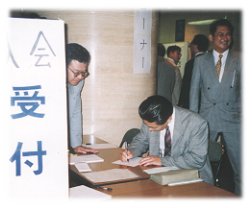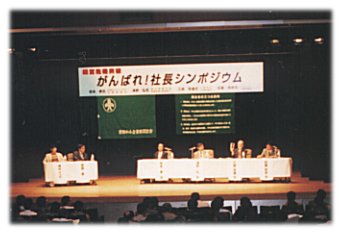
がんばれ社長シンポジウム
450名が参加アピールも採択会外経営者八十四名も参加
六月十二日、中小企業振興会館で「がんばれ!社長シンポジウム」が開催され、会外参加者を含め、四百五十名が参加しました。「政策不況」と言われ、経営環境が一層厳しさを増している中、銀行の貸し渋りへの具体的な対策を含め、どう乗りきるのか、「一社だけで悩んでいないで、一緒に考えていこう」という主旨で今回行われたものです。シンポジウムでは、金融機関の貸し渋り対策や、今後の経営戦略などについて、元大手都銀融資課長で、現在下部(株)日本ビジネスクラブ社長の宮本孝氏(東京同友会会員)、現役銀行マンである浦野弘氏(銀行産業労働組合・副委員長)、愛知同友会会員の江崎信雄氏((株)江崎本店・社長)と加藤明彦氏(エイベックス(株)・社長)の四人をパネリストに迎え、会場からの発言を含め、三時間にわたる熱心なパネルディスカッションが行われました。
「銀行依存から脱却を」宮本氏浦野氏「自社の将来に確信を」
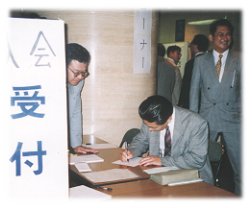
「借金整理マニュアル」などの著書があり、リスケジュール(銀行への返済計画変更)の専門家である宮本孝氏は「貸し渋りは今後一層ひどくなる。中小企業は自衛のためには銀行に依存する経営からの脱却が必要」と述べるとともに、生活と経営を守る観点から、具体的なリスケジュールの手法を約四十分間にわたって報告しました。浦野弘氏は銀行労働者として金融機関の社会的責任を問う立場から発言。ある都市銀行の例として十二段階の信用格付ランクを紹介しました。そのうえで「中小企業向け融資は金利が高く、銀行はいじめながらも、不要とは思っていないはず」と述べ、「銀行としっかり議論できる会社になってほしい」と、経営者の学びと企業指針の必要性を強調しました。現役社長である江崎氏と加藤氏からは、それぞれの立場での企業経営の現状と、今後の経営戦略が語られました。五月末に行なわれた経営状況をたずねたアンケートの結果も紹介され、「貸し渋り」を経験、心配している経営者が合計で四〇・七%、新規融資をことわられたのが五九・五%、消費税率アップが不況に大きな影響を与えたとする人が六六・四%などの結果も報告されました。最後にアピール文(下記参照)を採択し、閉会しました。なお当日は、報道五社が取材。会外経営者も八十四名参加し、その場で四名の方々が入会されました。
シンポジウム当日参加者にお配りした小冊子を有料で配布しています。
<内容>
①「生活と経営を護る究極の資金繰り『リスケジュール』」宮本孝氏((株)日本ビジネスクラブ・社長)
②「中小企業の金融対策」佐藤澄男氏(名南経営センターグループ・代表)
③「予断を許さぬ東海の景気動向」(株)帝国データバンク・名古屋支店情報部
④「金融機関の社会的責任を問う〜銀行労働者の立場から」浦野弘氏(銀行産業労働組合・副委員長)
●A四判五十四ページ
●頒価千円
●お問い合せは事務局まで
アピール
中小企業は国の宝である。それは日本の経済の中で確たる位置を占め、生産と技術を支え、きめ細かい流通を確保し、国民に多大な富とサービスを提供している。
全労働者の約八十%を擁する中小企業は国内最大の雇用者であり、一方で地域社会の文化の重要な担い手でもある。自らの理念を勤勉と努力で実践し、「自立・自助の企業家精神」で世界に賞賛される現在の地位を築いてきた。
今、この中小企業が、戦後最大の不況の中で倒産、廃業、整理に揺らいでいる。消えていく企業の数は、生まれる企業の数を上回り、先行きの見えない経済は企業家精神を萎縮させようとしている。
私たちは、中小企業の活性化こそ日本経済再生の道であることを信じている。すでに先進各国は中小企業振興を経済政策の重要な柱とした。
本日ここに参加した中小企業家は、「自立・自助の企業家精神」を奮い立たせるための四つの政策を緊急に要望する。
一、消費税五%を三%に見直し、国民の消費意欲を生み出すに足る減税をすること。
二、三十兆円もの、中小企業を含む国民の財産を、本来経営の自己責任を持つべき民間金融機関に投入する以上、けっして「貸し渋り」などを起こさないように銀行を指導すること。
三、公的金融機関の貸付規模を拡大し、担保主義をやめる等、融資条件を中小企業の現在置かれている実態に沿って緩和すること。
四、公共投資十六兆円を、在来の大型開発にとらわれず、地域・生活密着型に投資し、その五○%以上を中小企業が直接受注できるよう、幅広く参加できるシステムに創り上げること。
一九九八年六月十二日愛知中小企業家同友会がんばれ社長シンポジウム参加者一同
メッセージを寄せられた皆様(以下到着順)
・社会民主党愛知県連合殿
・公明愛知県本部本部長武藤辰男殿
・自由党愛知県総支部連合会会長青山丘殿
・日本共産党愛知県委員会文教福祉部長八田ひろ子殿
・民主党愛知代表さとう泰介殿
・自由民主党愛知県支部連合会殿
・中小企業家同友会全国協議会会長赤石義博殿
・青木雄二殿(元漫画家「ナニワ金融道」著者)
どうゆうき

昨年九月、愛知同友会の中では、今後の景気動向をについての「年末に向けてかなり落ち込むのでは」という予測をたてた。その頃、日銀等は「ゆるやかな回復にある」と発表し、私達の実感との間に大きなギャップを感じさせた。金融機関の貸し渋りはこの頃から徴候を見せ始め、昨年末には会内の調査でその体験者は十三%を越え、今回五月の調査では十七%台に達している。
四月の経営フォーラムの第一分科会ではこの問題が取り上げられ、さらに六月十二日の「がんばれ!社長シンポジウム」では約四百五十名が参加し、会外にも大きな反響を与えた。
バブル経済崩壊後に露呈された日本経済のもろさが、ついに、企業への融資を見あわせという異常事態にまでなってしまった。「貸し渋りとは何か」という定義は大変難しい。いつの時代にも、金融機関から融資を受けられなくなった企業はあったが、今回のそれと同一視することはできない。企業にとって融資の停止は、手の施しようによって助かる患者への輸血を、医師が確固たる理由も示さず拒否し、見殺しにするようなものである。
経営に影響を与える事柄について、いろいろな対応策がある。貸し渋り対応策も同様で「がんばれ!社長シンポジウム」に参加した人たちはそれを確実つかんだものと思う。パネリストの報告の中にもあったように、大切なことは経営者の確固たる時代を視る目が今更ながら求められており、同友会が提起続けてきた経営指針の確立こそ、まず企業に必要なのである。
会長 佐々木正喜