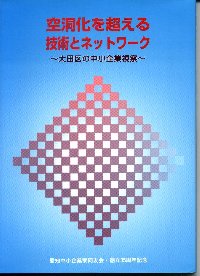「日本で初めて」がいっぱい「設楽キラリンとーぷ」竣工式に出席して(9月26日)
竹内郁雄㈱八木一(愛知同友会副会長)

社会福祉法人ゆたか福祉会が第二の「ゆたか希望の家」として、奥三河の設楽町に建設を進めてきた「設楽キラリンとーぷ」の第一期工事が完成。九月二十六日の竣工式に愛知同友会から私と福島事務局長が出席しました。
人間らしい生活の場を
開会のあいさつで秦安雄氏(ゆたか福祉会理事長、日本福祉大学教授)は、「幾十万の個人や団体の支援と協力、そして励ましがありました。一九六九年、無認可の共同作業所としてスタートして以来、三十年の歴史は関係者の協力と共同の力で事業を起してきた歴史でした」と経過を紹介。「障害の重い人達が親の介護を得られなくても、一人の人間として大切にされ、いきいきと人間らしい生活のできる場を求めて事業を進めてきました」と発表されました。
豊かな生活の場として
「人間らしく安心して暮す」ことを前提にした施設づくりは、熱田地区会員である〓中央設計さんが設計し、完成した知的障害者更生施設は定員五十名、ショート・ステイ五名の収容能力があり、五名単位の小舎(グループハウス)・完全個室制、十一棟で、居室面積は一人あたり約七・五畳(国の基準の約三倍)にもなっています。

過疎地域で新しい村づくり
「名古屋市よりもやや狭い地域(二百二十三平方キロ)に五千七百人の人達が生活する設楽町は、六十五歳以上の人口が三十四%を占めており、過疎化と高齢化が同時進行しています。「林業といっても木材が安くて手がつかず、農業でも都市生活者並みの収入はとても得られません。これからは福祉で村おこしを考えていたところだった」(後藤米治設楽町長)というように、過疎地の高齢者の皆さんの生きがいづくりとも関連し、都市と山村が提携して、自然を豊かに守りながら、山村の新しい村づくりに貢献します。
共生の舞台として
「キラリンとーぷ」の中には軽作業のできる施設、さらには芸術・文化・趣味の活動やリハビリのできるセンターも創られます。周辺には農産物加工場や養鶏場、花や野菜づくりの農場もつくられ、仕事場に出かけて地域の人達と共に働く職場づくりをすすめ、地域社会の活性化をめざしています。ここで生産された農産物は安全で安心して食べられる商品として「JAやまびこ」や「生協」を通じて名古屋を始め、大都市部に供給される予定になっています。将来的には障害者八十名・職員四十名になり、リハビリセンター、高齢者ホーム、レストランや給食センター、そして地域交流センターなど、総合的な施設づくりも進められ、設楽における障害者と高齢者(地域)の交流・共生の拠点になり、全国に誇る施設の竣工式になりました。
「一人の人間として大切にされたい」そんな想いに支援を
浅海正義氏(社)ゆたか福祉会副理事長(創立会員・千種地区)

国の基準を大きく上回って
「設楽キラリンとーぷ」は社会福祉法人ゆたか福祉会が「障害者・高齢者の人間らしい生活の実現をめざす福祉村」として、どんなに重い障害をもっていても一人の人間として大切にされ、いきいきと暮したい、そんな想いを具体化しようとする計画です。敷地約一万坪で、第一期は知的障害者更生施設(定員五十名),第二期には五名単位の小舎・完全個室制で十一棟の身体障害者療護施設(定員三十名・ショートステイ五名)が建設され、総工費十七億円となります。財源は国と県の補助が七億円、借入金が五億円、自己資金五億円で、いわゆる障害者の収容施設ではなく、障害者自身の想いを形にした生活施設です。そんな新しい事業を先駆的に進めています。自己資金五億円のうち二・五億円は障害者や家族自らが、また福祉会の事業活動から捻出し、後の二・五億円を多くの支援者から援助していただけるように、お願いしています。
全国に先駆けて
「ゆたか福祉会」が愛知同友会の心暖まる支援のもと、十人程の無認可で、日本で初めての共同作業所として発足したのが三十年前の一九六九年三月。今では全国的に五千カ所の作業所ができる直接の発端となりました。七二年二月、社会福祉法人として法人認可となり、以後三〜四年ごとに施設が増え、制度のないものでも、障害者の要求にしたがって創り出し、それを制度化していく。そんな運動のなかで、作業所やグループホームは二十カ所にもなり、利用している障害者の仲間は約四百名、職員も二百名近くにもなる大きな法人となっています。その三十年の成果の上にたっての大事業です。私も人生の締めくくりとして、微力ながらこの事業に、全力を尽くしたいと想っております。
●問合せは「あいち福祉協同組合」(tel052・876・4151)まで
書評「空洞化を超える技術とネットワーク〜大田区の中小企業視察」
「大田の町工場」に学ぶ技術活用型経営
森靖雄氏(日本福祉大学教授)
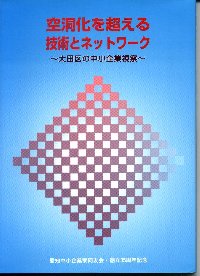
自動車など工業生産額では全国一を誇る愛知県には機械関連工場も多く、トヨタなどの海外進出とともに受注が落ち込んでいる。そのため愛知同友会では、同じ様に機械関連工場が集中している大田区に早くから注目し、勉強会を重ねてきた。その成果を踏まえて、昨年十一月二十六・二十七日、三人の研究者を含む視察団を編成し、東京同友会大田支部の協力を得て現地視察した。本書はその視察記である。A五判百三十八ページの本書は、自らも旋盤技術者である作家小関智弘氏による講演「日本の未来は、人間を大切にするモノづくりから」の記録。四つの工場の見学記。二篇の視察成果と、参加研究者による三篇のレポート、それに鋤柄代表理事の総括と資料集から成っている。本書を通読すると、改めて日本の「町工場」の技術レベルの高さとその誇りがひしひしと伝わって来る。同時に、発注企業の相つぐ海外工場移転により受注が激減して、こうした技術が支えられなくなっている現状と、技術伝承の糸を絶やしたら大変だという危機感が迫ってくる。本書によれば、大田の工業地帯ではその対応として独自製品の開発や、高い技術を持った工場どうしのネットワークを利用した、地域内共同開発などに取り組まれている。その具体的手法や成果について、いろいろと示唆に富んだ事例が報告されている。大田区でも、愛知県でも、さらに同様の特徴を持つ大阪府の東大阪市そのほかでも、関係業者の減少は避けられないであろうが、同時に、永年培った高レベルの技術を活かす道もある。本書にはそうした希望を拓くヒントが満載されている。
◆問合せは同友会事務局まで