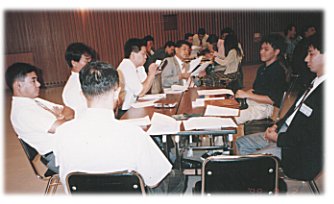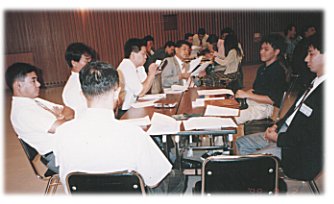過去、現在、そして将来を考える
第26回青年経営者全国交流会(静岡)(9月10・11日)
30年の歴史を経て、今、新しい活動に挑む高橋政彦氏㈱高橋技建(青同連協・前代表)
青年部会から四つの青年同友会に
愛知の青年同友会(以下、青同)は、一九七〇年に「青年部会」として三十二名で発足しました。七八年には「青年同友会」と改称し、同友会の基礎組織(地区)の一つになります。大きな転機が八四年に訪れます。前年、愛知同友会の地区を五つのブロック(現在の支部)に分割する方針が打ち出されました。当時百名だった青同も四つに分かれ、青同間の連絡組織として連絡協議会(以下、連協)を置きました。個々の青同が一つの地区として活動し、連協は年数回のイベントを主催する程度でした。
「激論」で惨敗「学び」を考え直す
五年が過ぎた八九年、分割前は順調に増えていた会員が、この五年間まったく増えていないことが随分と問題になりました。連協では(1)連協会員を毎月開催する、(2)連協主催の例会を増やし、組織を強化する、この二つを大きな方針として掲げました。翌九〇、九一年と、「激論」という青同の二代目会員と、同友会の創業者会員のパネル討論を試みました。結果は、二代目の甘さを鋭く突かれ、われわれには発言の機会すらありませんでした。青同の惨敗でした。これで目が覚めました。われわれは何を学んできたのかを、もう一度考え直す機会になりました。
達成感は満たしたが
折りしも愛知同友会三十周年の年でした。実行委員長を青同から出し、周年行事の推進役として存在を大きくアピールできました。この年、小栗崇資先生を招き、三十周年の出版である「小さな会社が日本を変える」を記念した講演会を主催し、成功させたことは大きな自信につながりました。翌九四年には、会員の劇団「俳優館」のミュージカル・カレーライス物語を後援、市民二千三百名が、ホールを埋めました。九五年、野口誠一氏、山口義行氏と船井幸夫氏を講師にした例会を二回行いました。満員のホールを目の当たりにして、達成感で満たされていました。
イベントからの脱皮産学アカデミーの開催
しかし、この年に同友会を辞めていったメンバーからは「青同はイベントばかりで、運営だけで大変だし、学べない」という厳しい声も聞かれました。過去にイベントばかりやっていて、会員が増えなかった経験を忘れかかっていたのです。あらためて、学べる例会への模索が始まりました。「こういう内容がいい」、「あの時の例会が良かった」。そんな会議を繰り返しました。そして、一定の形がまとまったころ、事務局に相談し、小栗先生を紹介されました。先生との話の中で「産学協同で経営者も理論を学び、学者も実践を学べる会合をしよう」と夢が膨らみました。九五年の秋、日本福祉大学のキャンパスを借り切り、「もう一度学生に戻って、経営の理論をじっくり学ぼう」という会合「産学アカデミー」が開催されました。昨年までで三回継続し、ゼミ内容はより濃いものになっています。二年目からは、市民団体の代表にも講師を依頼、昨年は青同メンバーや学生の皆さんも報告に立つようになりました。今年度はさらに発展させ、当日限りの行事にせず、先生方と一緒に事前研究会を発足させ、当日は「研究発表の場」にする試みが話し合われています。
自分達の会だ!
「なぜ愛知の青同がこういう活動ができるのか」。私なりに考えてみますと、メンバー一人ひとりが同友会会員として会に関わってきたこと、また、青同が四つに分かれた後も連協を通じて連係を保ち、諸課題を青同全体で成功させてきたことが、挙げられると思います。四十歳前の若いうちに、二百数十名からの組識をまとめ、何百人というお客さんの前に立つ、ということが、われわれ青同メンバーを成長させてくれたとも言えます。全国には部会のところが多いと思いますが、まず「自分たちの会だ」と思ってやって下さい。それから、「会をどうしたいか、どういう活動を目指すのか」を考えればいいと思います。愛知の青年同友会はそうして三百名に近い会員に発展してきたのだと思います。
【文責事務局・井上】
青同連協(9月2日)「活動改善経過報告+プレ青全交」
九月二日、青同連協主催で「活動改善報告+プレ青全交」が行われました。まず第二十六回青全交第十分科会での高橋前連協代表の報告リハーサルが行われました。あわせて会ビジョン(素案)を受けて、連協でも幾度となく「青同の将来ビジョン」についての討議が行われた中間的なまとめとして「これからの青年同友会」について、竹田連協代表が報告しました。
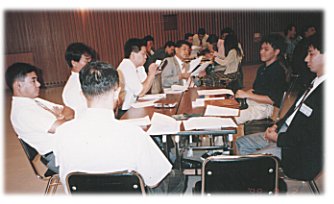
会ビジョンを青同進化の契機に
ビジョン(素案)では、「自立型企業をめざし地域社会とともに歩む企業」を会の企業像として掲げ、その旗印として「自立型の企業づくり」「人口百万人以上の地域に一拠点」が提唱されています。私達青同もこのビジョンをよく理解した上で、変革に対応して行かなければなりません。では、実際どのような対応が必要でしょうか。①愛知同友会の抱える問題点とその改善の方向、方法を正確に理解する。②青同の活動の足跡を整理・確認し、問題点を明確にし、解決していく。③青同の存在意義を会全体に明示し、同時に青同の目的・活動目標を未来へ向けたものへと一新していく。④ビジョン素案に対する対応を青同の進化の一つの通過点ととらえ、素早く実行する。⑤全青同会員が「進化」へ深い理解を示す。以上を推進し実行するには、愛知同友会の問題点もさる事ながら、青同のもつ問題点も、早期に解決する必要があります。

解決できない問題はない
①現在青同の抱える問題点としては、②「青年部」時代からのなごりで、別途活動費を徴収している(二重会費の問題)、③卒業後のスリーピングや退会の問題、〓現状は年齢別で地域別編成組織ではない、④三河に「青年同友会」がない、⑤青同会員が委員会や研究会で活躍していない、⑥青年経営者が全国で活躍していない等です。なお三番目の問題については、現在大きな地域単位である支部に各青同が対応しているため大きな問題点とは思いませんが、同友会全体から見ると、問題点の一つとして、とらえられるようです。過去の経緯を振り返っても、私達青同の能力で上記問題点を解決することはさほど難しいものではなく、また、解決しながら進化を遂げるという考え方に立ち、青同と、青同連協の存在意義を確立していきます。
竹田代表の報告の後、各グループで、青同で学ぶ意義や、青同の存在意義についてディスカッションが行われ、それぞれが青同の必要性を再認識しました。また、回収されたアンケートでは、「自立型企業」への理解度も深く、これからの同友会を索引していく力を強く感じました。
助川鉄工(㈱)助川雄(第二青同)