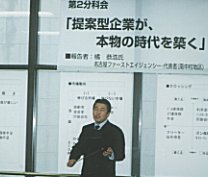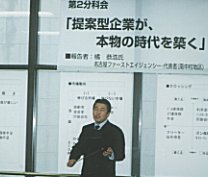第4支部・秋の研究集会(11月21日)
21世紀を生き抜く「智恵と力」を
川村繁生(有)花繁(実行委員長)
第四支部では、昨年に引続き研究集会を開催しました。昨年の「理想的な経営内容の報告が多く、共感が得にくかった」という会員の意見があり、厳しい環境の中で真剣に頑張っている身近な会員の経営姿勢を学べる内容に変えました。地域密着と同業種ネットワーク、本物の時代と提案型企業、業種転換の三つのテーマで分科会を設定、約百名の会員が参加し、学びあいました。
第2分科会「提案型企業が、本物の時代を築く」
橘恭浩氏名古屋ファーストエイジェンシー
「攻め」「育て」「守る」
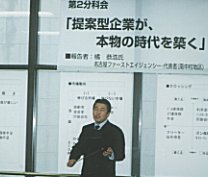
私は外資系の保険会社から業務委託を受け、オフィスマネージャーという立場で、社員と組織を任され、現在、四十六名のスタッフをかかえています。経営理念は(1)人間的成長と経済的成功、(2)業界の発展と改革に寄与する、(3)保険を通じての社会貢献です。「提案型企業」であるためには、まず企業としての考えや意見をしっかり持ち、その上で自社を分析し、社会の動き・人間の心理の動き・お客様のニーズをとらえる必要があります。顧客満足というものを企業がどう認識し、本物の顧客満足を名目どおり提供できるかが重要なのです。このことを踏まえて営業方針・経営計画・経営指針を成文化すると、指針がより鮮明になります。そしてそれを社員一人一人が知ることで、本当の意味の提案ができるのです。具体的には(1)まず自社の強み・弱みを商品と管理の面から見る、(2)次に伸びる市場と伸びない市場を当面と二〜三年に分けてみる、(3)以上を統合して自社の攻める部分、育てる部分、守る部分、捨てる部分を明確にするです。ここでいう「攻める部分」とは「提案できる部分」であり、年度方針になるところです。また「育てる部分」は「将来の攻める部分」であり、中期計画になるところです。
 「与える」が「提案」に
「与える」が「提案」に
私は「魅は与によって生じ、求によって滅す」という言葉を人生哲学にしています。「どんな情報・知識・言葉・表情をお客様に与えられるかを考えなさい。契約や金銭を求めた瞬間、お客様は去っていきます」と社員に言っています。この「与える」姿勢が「提案」につながるのではないでしょうか。市場のニーズにあったものをいかに提供できるか、そのものが独自のものであるか。これらをクリアした真の意味での提案型企業が、この激動の時代を生き残っていくのではないでしょうか。
(資)岡田屋山本康弘
第3分科会「溢れる知恵が事業転換へ〜そのスピードとパワー〜」
渡辺素三氏(有)テレコムコーポレイション

最初の転機はオイルショック
私は学生時代の飲食店でのアルバイト経験を生かし、喫茶学校を開きました。当時の喫茶店ブームに乗って生徒も集まりましたが、オイルショック後、改装費や食材の高騰でブームも去り、生徒が集まらなくなりました。当時、組合の事務所が東京にありましたが、人を置く余裕がなく、チェスコムの転送電話で名古屋と結んでいました。これが、NTTが民営化され、通信の自由化が叫ばれ始めた時期と重なりました。これからは、通信の時代であると直感し、電話関係の仕事をしようと思いました。ちょうど組合でも使っていた関係で、チェスコムの転送電話の販売を始めました。東京進出や地域事務所の開設を戦略にする企業が増えはじめた時期でもあり、飛ぶように売れました。
NTTのサービスと競合しながら
しばらくすると、NTTも転送サービスを始め、全く売れなくなってしまいました。そんな時、チェスコムを買っていただいたお客様から、「転送先も不在で、困ることがある」という相談を受けました。これに目を付け、「従来の転送先に代わって転送電話を受ける」業務を始め、ヒットしました。するとNTTも子会社を作って、電話受付代行業を始めました。この仕事は常に、NTTという最大手と競合しなければなりません。
将来に向けて夢が広がる
今は、「ベルコール」という、留守番電話と転送電話を複合したサービスに力を入れています。また、インターネットにも注目しています。今は通話料だけで接続できますが、もし有料であればどうでしょう。具体的には、高齢者向けのサービスとして「定期的に電話をかけ、応答がなかったら、予め指定された連絡先へ連絡する」ソフトが完成しています。商売は、そのときの世の中に合わせていかなければなりません。社会が必要とすることならば、必ず商売として成り立つと思います。私の商売の信条は、「二つの楽:楽で楽しい」「二つの意:創意と誠意」です。
吉岡昌成氏ヨシックスグループ
大学は出たけれど
ヨシックスグループは、飲食店店舗の設計施工をするヨシオカ建装、経理事務と飲食店を経営するヨシックス、弁当ショップFC本部の飯蔵の三社で構成されています。一九七三年、高校の機械科を卒業。当時、日本列島改造論で建築ブームでしたが、大学を卒業した七七年は、第二次オイルショックで大変な就職難で、大手電機メーカーの系列会社に就職しました。そこでは、八百屋や魚屋を小型のスーパーに改装する新規部門に配属され、三年半の間、営業だけでなく現場監督もやり、図面も自分で書きました。
「かまどや」と共に全国展開
そこを退職し、しばらくして、古い縁から「本家かまどや」の内装を請け負うことになりました。その全国進出に合わせて全国各地に営業所をつくり、その縁で名古屋に来ることになりました。一九八三年には年商で五十億を売り上げましたが、弁当ショップのブームが去ると、パッタリと仕事がなくなり、年商も三億六千万にまで落ちました。しかし、幸い借金がなかったので、仕事を続けることができました。
夢は株式上場
今では、コンサルタントとして、土地探しから出店計画、営業や労務管理まで、幅広い分野で経営のアドバイスをしています。また、「かまどや」から引き継いだFC店を飯蔵としてFC展開していますが、まずは、価格決定権を持つことです。一〇〇〓下請の場合は、相手のいうことを聞かなくてはなりません。これでは企業といえません。グループの理念として「子供からお年寄りまで楽しめる食住空間を提供する」を掲げています。最終的には株式公開まで行きたいと考えています。そのためには、いい社員を集め、誇れる企業を目指したい。ヨシックスの社員像として「すべての面で一人前になりましょう」と言っています。一人一人と対話を続けています。
大野公認会計士事務所大野伸幸