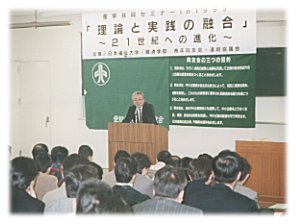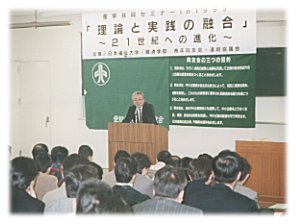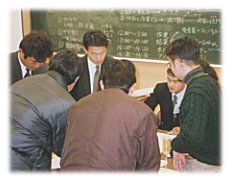産と学、共同の力の深化
=事前の学習会や調査活動を重視して=
2月14日産学共同セミナー青同連協
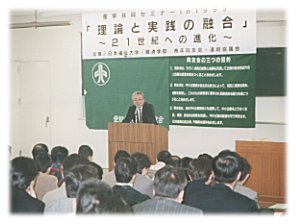
青同連協と日本福祉大学経済学部とが共催するこの催しも、今年で四回目となりました。今回のセミナーでは日本福祉大学の半田キャンパスで九つのゼミが行われ、大学の職員・学生を含め、百七十三名が参加しました。今回のセミナーは、過去三回の経験を生かして、当日一日だけのイベントとせず、各ゼミが「事前学習の成果発表の場」と位置づけられました。
視察旅行、アンケート教官の事前取材も

森靖雄先生のゼミでは「小売・流通業の自立と共生」をテーマに取り上げました。三回の事前学習会を開き、そのうち一回は、年末の日曜日を利用し、滋賀県の草津市と長浜町を視察しました。小栗崇資先生のゼミでは、事前に同友会会員企業を対象にした「社会貢献に関するアンケート」が行われ、当日、大学の学生から集計結果の報告が行われました。また三年連続してゼミを受け持った関口和雄先生は、事前に企業訪問し、レポートを作成。「二十一世紀に生き残る経営戦略」のテーマで、中小企業ならではの経営戦略の実例を報告しました。
他団体とも協力し新しい取り組みも
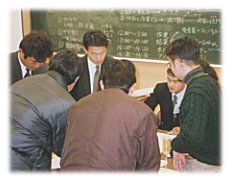
やはり三年連続となる、萩原喜之先生(中部リサイクル運動市民の会)のゼミでは、昨年後半に同友会も協力して実施した「事業所系紙ゴミのリサイクル実験」に基づく成果発表と、これからの環境ビジネスの可能性を、KJ方式によって深めました。いくつかのゼミでは今後も継続して、各テーマを深める研究会活動が行なわれ、さらに産と学の提携が深められていきます。ゼミの内容は、次月の「同友Aichi」に掲載します。
どうゆうき
▼最近の会員の声より。「かつて八ミリ映写機の部品加工をしていたが、ビデオに転換が進んだときには三カ月で九○パーセントの仕事がなくなった」「ファッション業界では勝ち組みと負け組みの区分けが鮮明になりつつある」「立派な製造設備を持っていたり、海外生産に乗り出しているかどうかということではなく、製造と販売の両翼をチャンと確立しているかどうかだ」▼一月末に自動車のプラスチック部品メーカーの会員は「十二月比三○パーセントのダウンになってしまった」とこぼしていた。「部品のアッセンブル納品がこの一月から導入されI社系列の仕事がT社系列に集約されてしまったため」というモジュール化の動きだ▼運送業界は一九九○年二月に物流二法が改定されて規制緩和が進んだ。その後三年間に七千件が新規参入して業界は競争が激化した。トラック協会は「その後も状況は変わらない」と言う。従来二十両のトラックを保有していなければ認可されなかった業界が現在は十両、新年度からは七両でよくなり、二○○○年度からは全国一律五両で営業許可がおりる。早い話が、五台以上を保有して配送部門を持っている会社は、全部、「運送会社」の申請が許可されることになる▼昨年末から中小企業の航空会社がスタートした。しかし、アメリカの経験ではこういう試みがことごとく失敗し、逆に大手の寡占化が進行してしまった。中小企業の翼が飛ぶか落ちるかなのである▼構造変化や規制緩和が進行する中で中小企業が時代をリードする存在になれるかどうか、各社の経営戦略の確立と自立型企業づくりが問われている。
事務局長福島敏司