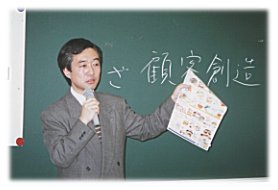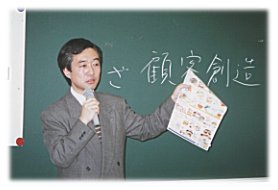事例紹介(講演で小栗先生が報告された事例から、一部を要約して紹介します)
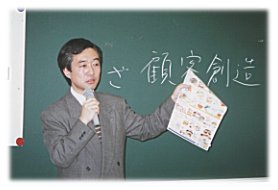
事例(1)現代生活のウィークポイントを発見して
<D社(福岡)元家電販売>
N社長は家電販売店をやっていて、お客さんの話を聞いて、一番困っていることは家電の「故障」だということに気づく。量販店に持っていけば、「買い替えた方が安いです」と言われるが、捨てがたい愛用品もあり、環境問題も発生します。
「修理をビジネスにしよう」と、(1)買い替えるよりも非常に安い修理料金の設定、(2)その場で修理費を提示、(3)48時間以内に修理、(4)その期間は代替機を貸す、(5)48時間以上かかる場合は罰金としてさらに料金を下げる、(6)製品の保証をする、以上6つをお客様と約束する。ファーストフード並みの奇麗な店で、お客様が家電製品をカウンターに載せると係員が来て診断し、カウンターの向こう側で修理する。料金表もあり、安心できる。きっかけは、大手家電メーカーのT社がリストラした技術者を1人雇用したこと。技術の分かる人が1人いれば、修理のポイントは全部分かる。また現在、脱サラしたい人を見習いにしている。店とカウンター、ハンダゴテとテスターと検索装置があればいい。だから設備投資も要らないし、目の前で修理しているから、子どもたちが遊びに来ても見飽きない。家電製品に囲まれた現代生活のウイークポイントを発見し、それを徹底して考え抜いて見事なコンセプトをつくり、1号店には行列が。修理は利益率が高く、利益率70%で、1カ月に千件くらい持ち込みがある。T社からは「更にリストラしたいので、技術員を受入れて欲しい」(?)と申し入れも。「資金も出すから営業展開しないか」ということで、今春8店舗を同時オープンした。
事例(2)熱意があれば、知恵も集まる
<K社(岐阜)タイル製造>
K社の地元はタイル生産日本一の地域である。K社長は窯業関係の産業廃棄物を「何とかしなければいけない」し、「これを何とかビジネスにできないか」と考え、「ブロックタイルのようなモノ」をつくってみようと思いつく。普通は余った土といろいろな廃棄物を混ぜて焼くわけだが、もう少し問題意識が高く、「熱を出してしまったのではまた環境問題ではないか」ということで、「焼かないでつくってみよう」という大冒険を、社運を賭けて、「志」高くはじめる。熱意を持てば知恵も集まる。K社長の熱意に動かされ大学も知恵を出し、2年間かけ、焼かないでタイトルをつくるという特殊な硬化技術を完成する。敷石や歩道に使われるタイルとして、ガーデニング用のブロックとしては強度も良いし、肌合いもいい。何よりもコストが安くできる。名古屋大学病院の前の歩道や敷石はすべてK社のブロックでできている。これに注目したのはT自動車メーカーの住宅部門。これを「ぜひ採用したい、使いたい、できれば住宅の中にも使いたい」という話にもなり、今、爆発的に売れている。これも1つの問題解決、「困ったと時にヒントがある」というケース。
事例(3)「お客様の声」を日報に、そして社内報で
<A社(北海道)印刷業>
日報を上手に使っている企業として、北海道にA社という20名の倒産寸前の印刷会社をK社長が建て直して、現在社員数300名にもなったすごい会社がある。A社の日報は「今日何軒まわった」「今日いくら売った」ではなく、「お客さんの声」を日報に書き、「誰が、どんなことを言っているか」「お客さんの観察すること」が主眼に書かれている。その情報で社内ニュースを発行し、それを上手に使って製品開発をしている。つまり、売り手側の一方的な売りつけではなく、お客様のニーズをどう拾ってくるかがポイント。
事例(4)「私が大切にされた」
<M生協(宮崎)生活協同組合>
生協にも苦情はある。M生協はお客様に、苦情カードを書いてもらい,苦情がどんどん来る。「お客様の観察記録を」「あなたがどう思ったかを書きなさい」というのがここの日報。どんな会話をしたかが書かれている。結果、職員の日報が毎年1万通、苦情カードが2万通、アンケートが2万件、年間で5万件近い情報が寄せられいるが、苦情カードには、解決策を付けた返事を必ず出している。一人ひとりの名前の書かれた「こういう商品が良かったから扱って欲しい」という提案カードがもあり、これをもとに商品開発を行っている。「1人が欲しいと思ったものが、皆に売れるか」疑問があったが、「こういう理由で欲しかった」と書いてあるのを見て、「私も買ってみた」という感じで奥さん方の共感もあって、結構売れている。ここから爆発的に売れるものが出てき、定番商品に昇格していく。「あの生協は、私の提案をすぐに取り上げてくれた」「私が大切にされた」という共感が、抜群の信頼感を生み、そこからまた大ヒット商品が生まれていく。

事例(5)フォローを徹底的して
<M社(宮崎)工務店>
M社のM社長は、前社長から経営を譲り受けるが、社長になって一番ショックだったのは、今までのお客さんをまわったら、苦情だらけだったこと。「あなたのところにいろいろな修理を頼んだけれど、その後一度も来ないではないか。その後、こんなことで困っているんだ」と、苦情と不満をぶつけられて、大ショックをうける。M社長は同友会に入り、その時のショックの体験を使って、「これからはアフターフォローしよう」という経営指針を作成する。お客様を年4回訪問。協力業者が年4回、ホームレディーが年4回まわり、それだけで注文が来るようになる。7名の工務店だが、きめ細かく回ることによって、抜群の信頼感がある。そのことでは利益にならなくても、くぎ1本、網戸1枚でも修理に飛び出して行き、それによってまた修理だとか、紹介だとか、「あそこはいいよ」という口コミが伝わる。リフォームは非常に利益率が高く、持続的な顧客創造で、売上は伸びていなくても利益率がガーンと伸びている。
事例(6)問題意識を持ち常識に挑戦
<I社(愛媛)鉄工所>
またM社長は非常に志が高く、12社の同業者によるネットワークで、協力業者・大工さんとも共にやって行こうと、木造住宅にこだわった研究会を始めている。
I社は福祉産業で非常に注目されているメーカーで、I社長はある大手農機メーカーの元技術部長。お父さんが寝たきり、いろいろなこともあり、脱サラして、下請鉄工所を創業。歳をとったお母さんが、お父さんをベットから抱き起こしたり、立たせたり、すごい力が要る介護を見て、駄目だと思う。高齢化社会では年寄りが年寄りを介護する。邪魔になっている車輪がスライド装置でバックし、肘掛けが倒れる、イスの高さが調整装置でベットとおなじ高さまで来る、背もたれが倒れ、ベット状態になる等、技術的には「これだけのこと」という新しい車椅子を考えた。これは特許。100年間の車椅子のコンセプトを覆してしまった。問題意識を持てば、常識に挑戦できる。さらにI社長は背もたれが起き、足も立ち、90度になり、そのまま足をつけて歩き出せる等の「介護ベット」を考案。日経の優秀商品賞を受賞する。某大手ベットメーカーが提携を求めてきて、そこの介護ベットはすべて、I社でつくっている。「問題意識を持って発明をする」ことの事例。
事例(7)ハードだけでなく、ソフトも乗せて
<F社(福岡)不動産>
「我社の新商品は、人が困っていること、地域社会の役に立つこと以外は取組みません」と豪語するH社長。町外れの土地をうまく使って、民間ベースでの「異業種交流団地」をつくった最初の人ではないか。また一括した不動産管理システムを開発し、ソフトもつくり、社員を訓練する。つくり出した業務のノウハウを公開、研修も受け入れ、勉強した人が各地で不動産をやる。その人たちに呼びかけ、年1回「全国不動産業成功事例シンポジウム」を行い、毎年400名もが参加。分科会方式でやっている。最近では、慶応大学の湘南キャンパスと組んで、「ぼけない有料老人ホーム」というものをつくり、厚生省の高齢者の住宅事情の審議会からも呼ばれる。次々と、一番困っていること、問題になっていることから、非常に見事に形を作り、不動産というハードを扱うだけではなく、ソフトも乗せて、もうすぐ店頭公開という不動産屋さん。