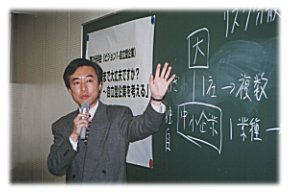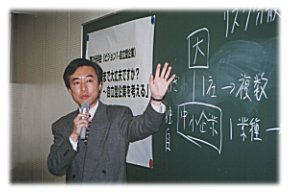愛知同友会第38回定時総会−第2分科会(「99同友会ビジョン」をめぐって)
今のままで大丈夫ですか〜自立型企業を考える〜
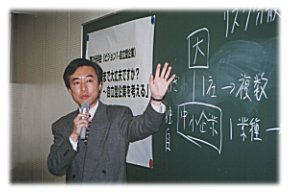
小栗崇資氏 日本福祉大学経済学部・教授
愛知同友会の30周年記念で私が書いた『小さな会社が日本を変える』という本の中で、21世紀の企業像として、「問題解決型」「学習型」「ネットワーク型」という3つの視点を提起し、同友会の皆さんにも受け止めていただきました。今回の「99同友会ビジョン」では、さらに「自立型企業」に発展させています。「99同友会ビジョン」の中では「環境変化の中で得意技を持って、独自の戦略を持てる企業」と定義しており、以前の「〜型」では混乱するので、整理して「能力」と置き換えますと、「問題解決能力、学習能力、ネットワーク能力」となります。これを存分に発揮して発展させると、それは独自戦略になります。独自戦略と得意技はワンセットです。得意技があるから独自戦略ができる、得意技によって独自戦略を発展させるという関係ができます。そして、めざすところは自立型企業となります。
リーダー企業の後追い戦略から得意技を生かせる独自戦略へ

20世紀における「正しい」企業戦略
ここでは「独自戦略をどう作るか」ということを切り口に話を進めます。各企業が持っている経営資源を量と質で切って見ましょう。人・物・金・情報など、いろいろな経営資源をたくさん持っている企業、少ししか持っていない企業。そして、経営資源の質が高い企業、低い企業といったように縦軸・横軸でつくってみました。【図1参照】右上のグループは、質の高い経営資源をたくさん持っているリーダー企業です。これまでの大企業でしょう。そして、左下に経営資源が少ない、質も残念ながら低いグループ。恐らく日本の中小企業の圧倒的多数はこのフォロワー(後追い)企業ではなかったでしょうか。後を追いかけていく企業の戦略と言えば模倣戦略です。大量生産の時代には、リーダー企業が、新しい製品(自動車や電気製品)や、色々なサービスの製品を開発する。その後を追いかけて、部品の一部を任されるとか、似たようなものを作るとか。これが、中小企業が20世紀を生きていくための「正しい」戦略でした。だからたくさんの中小企業が生きてこられたわけです。
「ニッチ」は「くぼみ」「隙間」ではない
しかし、情勢が変化し、非常な低成長の時代に入っています。市場のタイプが変わり、独自的で、個性的なものになると、モノマネ戦略は通用しません。図で言えば、左上のニッチ戦略(独自戦略)をめざすしかありません。「ニッチ」とは中小企業白書に出てくる言葉です。今、皆さんは白い壁に囲まれたレストランにいます。壁にくぼみがあって、花や絵が飾ってある。そのくぼみを「ニッチ」と言います。そこにスポットライトがパッと当たる様子を考えて下さい。「くぼみ」は「隙間」ではなく、皆の心を和ませる個性です。ですから、ニッチ戦略は「独自戦略」と訳し、正しい戦略としてのニッチ戦略をどうつくっていくのかを考えていきます。
持っている「技」を独自市場に結びつけて
昨日までモノマネをしてきた企業が、「今日から独自戦略で」と簡単に舵が切れるわけではありません。そこに自分の得意技(オリジナリティ)をどう生かすかです。下請企業も「技」は持っています。しかし、大企業の下で、同じような技で生き延びてきた下請企業は、得意技を発揮することに慣れていないのです。これからは技を上手に出して、独自市場と結びつける独自戦略を考えていただきたいと思います。
問題を解決する6つのヒント
独自戦略をつくるには、自分の技に気づくこと。そのためには独自市場に気づき、独自市場をつかんでくることです。お客様のニーズをつかみ、ニーズと技とが噛み合う、ここがポイントです。さらに自立型企業に進むには、基礎的な能力である問題解決能力、学習能力、ネットワーク能力が必要になります。そして、自立型企業に変えるには、それなりの覚悟と努力が必要です。この問題解決・学習・ネットワークを組み合わせていけば、おのずから独自戦略ができ上がってきます。問題解決能力ということを、以下の6つのヒントにまとめました。
(1)市場のささやきを聞き取っているか。苦情やお客様の悩みを大切にしているか。
(2)信頼や満足などのソフトを提供しているか。
(3)情報コミュニケーションを上手に使っているか。
(4)経営理念(ロマンやビジョン)を持っているか。
(5)常識にとらわれずに、発想豊かに行動しているか。
(6)儲け本位ではなく、お客様本位、社会本位になっているか。
この6つのヒントを物差しに使いながら、ケーススタディをしていきます。
独自戦略づくりの一歩は、市場のささやきを聞くことから

市場の『ささやき』とは
耳を澄まさなければ聞こえない市場のささやき(ブロックサイン)をどうつかむか。大企業は外注でマーケットリサーチをかけていますが、中小企業にはそれだけの資源はありません。『ささやき』というのは、実は、苦情やクレームという形で存在しています。消費者の感覚で言いますと、不便なことや困ることがたくさんあります。そういうものが全部ニーズなんです。ですから皆さんはお客様にとって、苦情やクレームを言いやすい企業になり、苦情・クレーム・悩みごとを宝物のようにして、そこから独自市場を探して下さい。
【事例紹介1―D社】【事例紹介2―K社】
お客様の満足と信頼を
第2に「すべてがサービス業」です。製造業の方は「製品」に、流通・小売業の方は「売るモノ」にこだわりがちですが、やはり「すべてがサービス業」だと思います。これからの時代は、商品そのものもさることながら、満足感や信頼感をどうやって提供していくかです。企業が生き残っていくためには、どうやったら信頼していただけるかが大きなポイントです。ドラッカーは「企業は利益を追求していては生き残れない」と言っています。利益だけを見ると儲からないときもありますが、顧客を見ていれば、お客様を生み出し続けることができます。お客様さえ離れずに増え続ければ、生き残れます。お客様が増えていくかどうかは、満足感、信頼感というソフトが提供できているかどうかです。そして、お客様からの声をどう聞き取るか。日報や苦情カードというアイテムを、情報として上手に使い、一人ひとりを大切にするということを、どう経営の中に取り込むかということです。
【事例紹介3―A社】【事例紹介4―M生協】【事例紹介5―M社】
現状に甘んじず、問題に立ち向かう志を
問題意識がないと市場はつかめません。問題意識というのは感性です。観察力と何よりも改革意識です。目の前で何が起きても、「こんなものだ」と現状に甘んじてはだめです。何とかできるのではないかという改革意識と高い志を持つことだと思います。「お客さんにとっていいこととは何か」という一種の哲学、そして、常識にとらわれないということです。問題解決は経営者1人ではできません。まず、社員に市場のささやきを聞くアンテナになり、判断者になってもらう。ですから、社員に判断の権限を与えれば、ネットワーク型の企業はできます。そのためには失敗から学んだり、成功事例から学んだりの学習がポイントになります。1つの企業では解決できないネットワークをどうするかという問題です。
【事例紹介6―I社】
技と技を結びつけるネットワークを発展させるカギは?

技と技とのネットワーク
今度は、ネットワーク能力の問題です。自立型企業は孤立型企業ではありません。自立型企業はネットワークに強い企業です。今、中小企業のネットワークは広がっています。自立型企業はネットワークに強い企業です。ただし、日本の中小企業はネットワークに弱い。従来のモノマネ戦略では、皆似たようなことをやっていますので、同業者が潰れてくれなくては困るわけです。どうやって足を引っ張るかが今までの戦略だったわけです。しかしこれからは違います。自立型企業になって得意技があるから、相手が「組んで欲しい」と言って来ます。得意技が組み合わさって、新しい製品になるのですから、このネットワークをどうつくるかなのです。
結局は、「人」のネットワークが
重要なのは人間的信頼感です。お互いを良く知る、利益を求めない、長い目で付き合う。成功しているネットワークはみんなこうです。「何かいい話はないか」ではだめです。全国に2000以上の異業種交流会がありますが、半分以上が開店休業です。行政がやっている異業種交流も、どうしても受身になってしまい、うまく行きません。そうではなく、ネットワークのポイントも問題解決なのです。コーディネート役も必要です。大風呂敷を広げて企画を持ってくれるような人も必要です。そして、みんなが技を持ち込む。なかなか難しいのですが、「みんなで考えようと」いって、自分から問題を持ち込む。すぐに製品やサービスに直結しなくてもいいので、情報交流する、勉強する。そういうことが、ネットワークの基本です。そのうち、自分のアイディアが湧く。儲け口の数探しではなく、お互いの信頼感。そこには夢が必要です。
【事例紹介7―F社】
緊急を要する社会制度の整備
問題解決に着目した企業は、すでにいろいろなスタイルで、自分のネットワークを持っています。これからネットワークをつくるには、中小企業の皆さんだけではできません。それを支える社会的システムが必要です。自立型企業が生まれ、それが生きていくためには、アメリカのように、自立型企業を応援する社会の仕組み(例えば、街の人が株を買ってくれる)をつくる必要があります。大学内に産業支援の事務所があって、中小企業経営者たちが経営の相談に来る、そういうシステムもつくらなければなりません。日本福祉大学と同友会の皆さんとはネットワークができはじめています。福祉大では、青年同友会さんと協同で1日セミナーを毎年開催しています。毎年、200名近い青年経営者の方が集まって、恒例になりました。そこから、研究が発達し、すばらしい経営が生まれると思っています。これからは、行政や大学を巻き込み、自立型企業がのびのびと自分たちの経営を展開していく仕組みを作ることが、大きなポイントだと思います。これはお互いの宿題にしたいと思います。
もう一度「自立型企業」をまとめてみると

下請ではいけないか?
最後に、皆さんのご質問にお答えする形で、今日のまとめをします。「下請では悪いのか」という問題ですが、これは実は、技が鍛えられないモノマネ戦略ではなく、どうやって技を鍛えながら持っていくかという問題なのです。下請を続けながらでも独自戦略を磨いていくしかありません。その方法としては、相手先を1社依存から複数に増やしリスクを分散するやり方もあるし、複数業種を相手にしたビジネスを展開していく方法もあります。これは、ただ「広げる」ことではなく、技を持って、独自の戦略で広げていき、それでリスクを分散する。それ以外にも独自製品の独自開発を進めていくのが、リアルな戦略だと思います。つきあいは残るけれど、大企業から見ても「あそこには技があるぞ、あの技を買いたい」という形で、技で勝負する。下請をしたたかに続けながら、リアルな戦略を取っていくことになるのではないかと思います。
個性と個性のコーディネイトを
イタリアでは、1つの服を作るときでも、糸の業者、布の業者、染めの業者、デザインの業者などがいます。同じ糸でも、細い糸が得意な業者も、太い糸が得意な業者もいます。布も、ざっくり織るのが得意な業者も、緻密に織ることが得意な業者もいます。これが全部「技イコール個性」なんです。また、コーディネイト専門の業者がいます。いろいろな技を組み合わせると、最終製品は個性の塊のようなものができるんです。こうして生まれた商品はグローバルな市場に出ていきます。日本の場合は、太い糸であろうと細い糸であろうと全部大手企業から注文が来ますので、今の量産品では技の生かしようがない。大手企業からすれば、同じような糸を作らせ、同じような布を折らせ、得意技など関係ないというように一律になっています。また、特に愛知の場合は縦系列になっていますから、お互いの技を知らない。違うのは大田区のような職人さんがいるところです。
今ある「技」を活かすために
イタリア型では何がポイントかというと、行政がコーディネート役を育てる仕掛けをやっているんです。支援するシステムもあります。技もしっかりしている。情報も横に行き渡っている。コーディネーターがいて「こんなことをやろう」と思えばできます。特に、愛知の場合は技があるのです。製造の技があります。その使いこなし方が私たちにはまだよく分っていない。その支援システムがもう一歩何かあれば、という段階にまで来ています。下請も続けながら、ぜひこういうことも考えてみてはいかがでしょうか。
【文責事務局・井上】