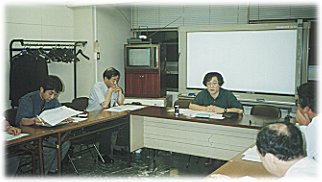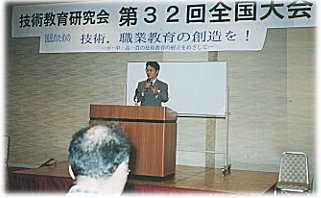地域活性化委員会主催7月2日
未来と地域をつくる金融システム「コミュニティバンク研究会」発足に向けて

遠州尋美氏(えんしゅうひろみ)
日本福祉大学経済学部助教授・工学博士1949年生まれ
【主な研究課題】発展途上国の大都市問題と地域改善/都市の成長管理と公民パートナーシップ/社会的生産基盤と地域コミュニティ
【著書】『都市再生の政治経済学』(共編著、東洋経済新報社・1993年)など
貸し渋りや選別融資など、銀行のあり方が問われています。地域活性化委員会では、地域振興やまちづくりの視点からアメリカのCRA法(地域再投資法)を勉強し、さらに今回「コミュニティバンク」の勉強会を行いました。日本の銀行は、融資審査で企業業績や将来見通しを正しく評価できず、担保主義に陥っています。それを乗り越えていく可能性を探りました。以下は遠州尋美先生(日本福祉大学助教授)の報告要旨です。
銀行の身勝手さに左右されない
信金はそもそも会員相互扶助のために生まれたにもかかわらず、その役割を忘れ、不動産などの投資に走って失敗し、大問題となりました。そしてニュースでも報道されましたが、和歌山県田辺市では銀行の支店がすべて撤退してしまい、地元の人がたいへん困っています。これから各地でますますこのような状況が深刻に進むことでしょう。そこで課題となるのが、コミュニティバンク、つまり中小企業家自身が生き残るため自分たちの会員制銀行をつくろうということです。現在、金融ビッグバンでさまざまな規制が取りはらわれ、新しいシステムを再生しようという流れにあります。今がチャンスであり、可能性があります。
自らの金融ソースで地域づくりを
昔、関東大震災の復興に、信金の原型である頼母子講(たのもしこう)が大きな役割を果たしました。頼母子講というのは、自分達で浄財を出しあって貯蓄し、必要な時に資金を貸しあう活動です。コミュニティバンクとはそのようなことなのです。既存の金融機関は大きな負の遺産があり、利益競争に巻き込まれています。コミュニティバンクは会員支援こそが目的で、欠損を出さないで存続できさえすればよいので、貸し渋りとは無縁です。また、まちづくりでも企業経営でもかなり積極的な攻めの経営に転換でき、成長企業や新市場を育てることもできるはずです。そしてリスクを共有することで信頼と結束も高まり、コミュニティや地域づくりにもつながります。発展途上国やアメリカ、日本の事例を紹介します。
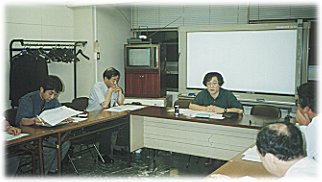
バングラデシュでの無担保融資の試み
発展途上国での開発政策が、内発的な経済成長につながらずことごとく失敗する中、バングラデシュで全世界を「アッ」と言わせる挑戦が行われました。「貧困層にお金を貸して返済できるわけがない」という常識をみごとに覆したのです。チッタゴン大学のユヌス教授が指導したグラミン(農村)銀行では、自発的な貯蓄活動をベースに、銀行や公的機関をじょうずに利用しつつ地域全体を活性して、年平均17%の所得を増やしました。
(1)貧困な農民層でまず5人のグループをつくる。
(2)どんなに小額でも働いたお金を定期的に貯蓄させる。
(3)3〜4ヵ月間、グループ運営のノウハウや簿記や日常管理を訓練し、「皆で頑張る」という経験と実績を積む。
(4)グループ中の優先順位一番の人にお金を貸す。
(5)借りたお金で荷車や機織りや牛などを買って、その稼いだ収益で返済する。
(6)そして次の人にお金を貸す。以上のような無担保融資のしくみをつくったのです。
銀行にとってもウマミあるマーケット
やってみると、市中金利と同じであるのに、98%の返済率でした。生活物価が安く、「道で惣菜を並べれば必ず売れ」、ほんの少しお金あるのとないのとでは、やれることがまったく違うのです。お金が借りれれば商売もでき、きちんと返済できるということが証明されました。一方、銀行からすれば、支店など経費や管理費がかからず、一件一件は小さくてもまとまれば結構な額になり、商売のウマミとなりました。つまり今まで先入観で除外されていたマーケットが、大きく広がったわけです。
アメリカではCRA法までに発展
タイのバンコクでも、200万人以上の出稼ぎ労働者が溢れるスラム街で同じような取組みが行われました。融資実績は81団体186件、総額1571万ドルで、回転融資、生業融資、住宅融資などにあてられました。また、アメリカでは都心地域の空洞化と老朽荒廃化によるレッドライニング問題(投資不適確地区に赤い線を引っ張り、資金が流れず悪循環するという問題)に対抗して、牧師さん達を中心とした非営利組織が地域改善を行いました。自分達でお金を集め、地域のイメージを変え、民間投資を呼び戻す活動です。この場合はCRA法(地域再投資法・銀行の社会性によるランクづけ)に発展し、さらに寄付による税金免除やその免除権の売買も認められるなど、社会的に非営利組織や市民にお金が集まるしくみが発展してきています。
未来を支援する日本の市民バンクも
日本では世界女性バンキングの日本支部である「市民バンク」と、環境保護やボランティア活動を支援する「未来バンク」などの活動が参考になります。前者は、信用組合の中に会員口座をつくり10万円づつ貯蓄し、それを市民バンクの融資原資とします。ただし金利を大きくしてもらう約束で、それを運営費などにあてがうという方法です。後者は組合活動の一種で、自分達の出資金の範囲内で行っていますが、主に、本来なら補助金がおりるべき事業に対して、実際に補助金が交付されるまでの「つなぎ融資」を行なうという点が注目されます。いずれも社会的な意義に賛同し、自分達の手で未来をつくることを支援する金融活動で、利子は「事業による未来づくり」への成果となります。例えば、廃油せっけん事業や、廃材を使った作家による家具インテリア事業、ソーラーシステム事業や、第三世界との公平な貿易をめざすフェアトレードなどです。
中小企業と地域が活性できるシステム
アメリカのCRA法は銀行にとって、結果的には「ウマミある新しいビジネスチャンス」となりました。しかし当初はアメとムチで言えば「ムチ」として受けとめられ、銀行側からは猛烈な反発と抵抗があり、なかなか実現されなかった歴史があります。日本の私たちの場合は既存の金融機関とうまくつきあいながらコミュニティバンクなどの実績を積み重ねていくことで、中小企業と地域が活性できる金融システムを創造していくこともできると思います。例えば、会員制の貯蓄クラブ活動をベースにしながら、お互いに保証しあい、市中金利と同じレベルで無担保融資を行う。包括的融資ではなく、ベンチャー型とか、街づくり型とか、目的と収支見通しのあるプロジェクト単位の融資活動が考えられます。仲間同士よく知っていれば仕事の仕方や状況判断などアンテナも高くなりますので、貸倒れの危険も少なくなります。さらに成功させるため、仕事まわしをしたり、ネットワーク化がすすんだり、事業自体がどんどん発展する可能性もできてきます。普通の銀行では、そこまでできません。ダイナミックにやれる資金がまとめられなくても、しくみを創って信金などと組んだりすると、あるいはもっと良いことができる関係を創っていけるかもしれません。そういうアイデアやイメージをいろいろと出し合いながら具体化できないかというのが、コミュニティバンク研究の出発点です。実際には、運用実務上の問題など金融専門家の協力も必要ですし、先行事例を掘り起こしたり、現地へ行って実際の話を聞いたり、というようなことを折り混ぜて活動する中で、実現の可能性ができてくると思います。
【文責事務局・加藤】
技術教育研究会第32回全国大会8月5日〜7日
青年はものづくりの中で育つ加藤共同求人委員長が冒頭の記念講演を
技術教育に取り組む教師120名が集う
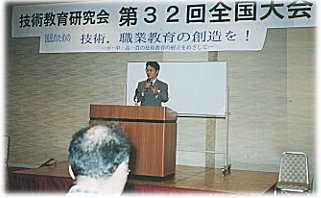
「荒れ」、いじめ、不登校や高校中途退学、はては子供達のひったくりや殺人事件まで、学校教育をめぐる問題が毎日のニュースを賑わさない日はありません。一方で、「教師の不登校が急増」「学級担任になりたがらない教師たち」など、ショッキングな見出しが週刊誌を飾りたてます。小・中・高校などで技術・職業教育に取り組む教師や大学の先生、教師をめざしている大学生や大学院生などが集まり、「技術教育研究会・第32回全国大会」が愛知県蒲郡市で開かれ、全国から百120名が参加しました。
自立型企業をめざすなかで
冒頭の記念講演には、愛知同友会の共同求人委員長の加藤明彦氏(エイベックス(株)社長)が招かれ、「青年は労働の現場でどのように育つか」と題して1時間半の講演を行いました。加藤社長は「私も愛知工業高校の出身、熱心な先生に支えられ、大学の経営工学科に進学したが、今では高校時代に進学を奨めてくれた先生に心から感謝している」と前置きし、話を始めました。まず、自社での「自立型企業づくり」の実践経験をあげ、社員との時代認識の共有化や経営指針づくりの意味、そして市場創造における得意技を生かした商品開発等が語られました。やりがいの持てる働きと生きがいを持てる人生をめざす、この育ちあいの風土づくりを通じて、「『ものづくり』の追求から、仕事のおもしろさが味わえる」との経験を語りました。
経営者にこんな人が!?
講演後の質問では、「リストラをどう考えておられるか?」「リストラをしなくて、会社はやって行けるのか?」「労使の信頼関係ということについてはどうお考えか?」「自社で研究された治工具の強度を増す技術について詳しく教えて欲しい」「中学高校や大学教育に何を期待されるか?」など数多くの率直な質問が出されました。「中小企業の経営者にはこんな人がいるんだ!?」と少々面食らった雰囲気が、会場全体を覆っていました。
(記事務局・福島)