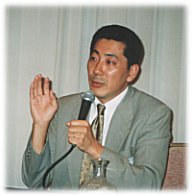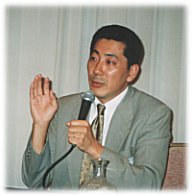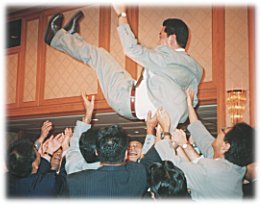第27回青年経営者全国交流会(9月9・10日愛媛)第4分科会より
自分の頭で考えて市場を創造する経営戦略−明確な経営戦略はありますか
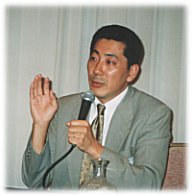
佐藤祐一氏(株)羽根田商会・社長(第4青同)
9月9日〜10日、愛媛県で開催された「第27回青年経営者全国交流会」の第4分科会での愛知同友会の佐藤社長の報告要旨を掲載します。
商社としての明確な存在価値を
私が社長になった当時は、「何のために羽根田商会がユーザーとメーカーの間に入っているのか」という、流通業の根幹を揺るがす問題を突きつけられていました。今までは、ユーザーに「いい物を安く、安定して」供給していれば良かったのですが、最近は、同じ条件ならば、世界のどこからでも買う「世界最適調達」という考え方が主流になってきています。流通経路でも、従来の「訪問して売る」タイプの他に、通販も入ってきました。「なぜ我々がここにいるのか」という疑問に真剣に答える必要が出てきました。逆にメーカーから私達を見た場合にも同じ疑問があります。新しい商品を売り込む場合は、私達のような、その相手の会社の人とシステムを知っている所を通した方が売りやすい。ところがコンスタントに売れるようになると、今度は「ユーザーのニーズに直接対応すればもっと売れるから、どいてくれ」という話になります。この問題は常に発生します。こういう現実を考え、基本戦略をつくりました。それが「技術的にユニークな、他にはない、新しい商品を常に開拓して、紹介し続けること」です。これによって「お客様のコストダウンを手伝う」という理念を実現し、当社の存在価値を出していこうと決めました。
社員の喜ぶ顔が見たい
私の父は創業者で、1番年長で、実績も経験もありましたから、社員も「あの社長についていけば何とかなる」と思っていました。しかし私が社長になった時には、それではやれません。「我々はどこへ向かうのか、何のために働いているのか」を明確にしないと、社員は不安になる」と思いました。そこでまず「社員がどういう時に嬉しそうな顔をしているか、どんな時に輝いて見えるか」を考えました。今年入った新卒の社員が、「A社でこの商品が売れました」とすごく嬉しそうに言うんです。それを見ている社員も、みんな嬉しそうな顔をしています。また、ベテランの社員も「社長、あの商品いいですよ。X社がとても喜んでくれました。今度はY社にこういうアプローチで持って行こうと思います」と目を輝かせて言うんです。そういう社員を見ていて、お客さんが喜んでくれたときに、社員が輝いているということに気付きました。こうして、我々の目的は「お客さんの喜ぶ顔を見る」に決まりました。
営業は社員自ら考えた戦略で
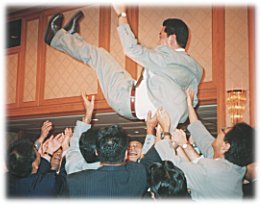
これで戦略と目的ができたので、今度はこれをベースにして、方針を出しました。「お客様を増やそう。徹底的に大企業を狙おう。大手を狙うには一朝一夕にはいかない、3年は辛抱しよう」。こう言ってスタートをしました。「ここまで決めたらなるべくみんなに任せよう」というのが、今日の『自分の頭で考えて』というタイトルの意味です。これは、「我々が生きていけるかどうかを決めるのは、商品を買うかどうかを決めるお客さんだから、そこに一番近い、営業の最前線にいる人の判断をなるべく尊重しよう」という発想でした。もう1つは、営業するにあたって、色々な仕掛けを自分で考えた方が、楽しいだろうし、成果も出るだろうということです。上司に言われたことをやるより、自分で考えてアプローチした結果でお客様が喜んで下さった方が、やりがいも成功率も高いのではないかと思いました。自分で先々のことを考えさせようということでは、「アクションプラン」を作り、これを見て上司がいろいろな指導やアドバイスをします。その上でお客様のところへ行くので、営業担当も動きやすく、上司のアドバイスも生きて、成功率も上がりました。ところが、これを使いこなしている人と、書けと言われたから書いている人と、2つに分かれてきました。ここが今後の課題でもあります。
良い商品を手間をかけて
今日のタイトルには、もう1つ『市場を創造する』という言葉があります。これは言葉とは裏腹に、実はすごく泥臭い話です。
当社では「手間を掛けなければ売れない商品」を重視して扱っています。普通なら手間を掛けずに売る方を好みますが、私は「カタログだけを持って行って注文もらえるような商品なら、『羽根田商会』が扱う意味はない」と考えています。付加価値の高い商品は当然値段も高いですから、説明の上、デモンストレーションやテストをして結果を出し、納得して頂かないと、買って頂けません。こういう「手間を掛けている」という面が当社の最大の強みであり、会社は「社員の自発的な活動を支援する」というのを基本に経営をしていこうと思っています。また「良い商品を見つけてくる」ことは、商社としては生命線だと思っています。商品が良くなければ、絶対にうまくいきません。当社では、どういう商品を見つけてくるかというポイントを整理しています。このおかげで、展示会へ行っても、どんな小さなブースであっても目に留まるようになります。これは当社にとっては、商品の「ふるい」です。数多くの商品をふるいにかけて「当社に合ったものを残し、確率の高い商品にしていこう」ということです。もう1つ重視しているのが、メーカー側の姿勢です。結局は人間関係なので、商品を導入するときは、たとえ海外であっても、必ず向こうのトップに会い、いろいろな話をしながら判断します。私としては、他にはない強い商品を見つけてきて、あとは社員の作戦に任せ、それを会社としてできる限りサポートするというスタイルで、この2年間やってきました。
働きやすい社風づくりを
社員をバックアップするために、いろいろな策を打っています。営業の武器として、カタログやプロモーションビデオを造りました。また、新規の顧客を増やすには、展示会には積極的に出すようにしたり、営業に専念できるようにと、物理的な配送や事務はパートにお願いしています。10年後の主力社員を育てようと思ったら、今から採用しないと間に合いません。女性の営業も採用し、男性社員とまったく変わらない仕事をしています。数年後には、新卒人口が減ってくることも見越して「今から若い人を採っておけば、後からも若い人が来てくれるだろう」という単純な発想で、経営的にはなかなか苦しいですけれど、無理をしてでも新卒採用を続けています。また当社は60歳が定年なんですが、ベテランの経験を活用したいと思い、嘱託契約をしています。1人1品体制で月に60万円の粗利を稼げれば、65歳までは嘱託で働いてもらえるシステムをつくりました。ベテランですから、月に60万の粗利を稼ぐのはそう難しくない。肩身の狭い思いをせずに、自分の経験を活かしながら、自分のペースで仕事ができます。国から補助も出ますので、充分メリットがあります。社内では「俺は残り何年だから」という愚痴がなくなり、55歳くらいの人もそわそわしなくなりました。さらに、新しい商品にも積極的に取組んでくれるようになりました。それから、会社の質を向上させる点では、「報・連・相」を徹底しています。将来、競合他社と比較されたときに、ISOを持っていた方が有利ですから、それを見越して、ISO9002を取得する計画もスタートしています。
〈会社概要〉
◆創業1947年
◆資本金9700万円
◆社員数53人
◆年商35億円
◆業種切削工具等の生産材商社
【文責事務局・井上】