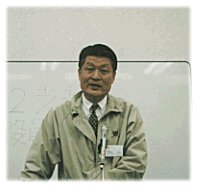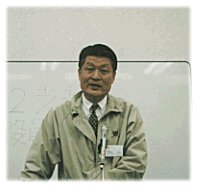同友会で学んで企業で即実践第2支部役員学習会
3月29日
役員になって“得”をしたこと
平沼 辰雄氏 (株)平沼建設工業 (第4支部・支部長)
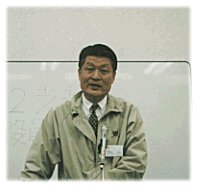
例会での体験報告に厳しいアドバイスが
私が同友会に入会したのは八六年、二九歳の時でした。最初は会のことがよくわからず休みがちでしたが、ある時地区会長から「地区例会で経営体験の報告をしてほしい」と頼まれました。
報告では「解体工事をやっているので、仕事をやればクレームの山、先が見えない。正直言ってやめたい。どうにかして欲しい」とありのままの気持ちをぶちまけました。
すると会員さんからいろいろな意見が返ってきたのです。「クレーム産業ならクレームをつぶせ。仕事を売るのではなく、買ってもらえ」などなど、厳しいアドバイスをいただきました。
この経験が、私を同友会にのめり込ませました。同友会の中で問題意識を持ったら、会社に持ち帰ろう。また会社での問題を会員に相談しよう。それができる人達に出会ったことが、大きかったのです。
自社の存在価値って?
十三年前に、わが社は個人から法人に変わりましたが、自分一人がトップ営業マンとして動きました。そうすると売上がどんどん上がるのです。おもしろかったですね。
しかし、経営指針セミナーなどに参加しますと「ちょっと待てよ。なにか違うぞ」と思うようになりました。「あなたの会社の存在価値は何ですか」と聞かれたときにはショックでした。質問の意味が全然理解できなかったのです。
「経営理念、指針とは何だろうか。どうしたら成文化できるのか」いろいろ話しているうちに、少しずつ理解できてきました。
会社の方針、戦略などを科学的に分析して、考えていくと明確になってきたのです。
同友会でも企業でもベクトルあわせが大切
私は第四支部の副支部長や本部の増強本部長をやらせていただきました。その時に経営指針をやっていて本当に良かったと思いました。
今まで、私たちは会社と同友会をあまり結び付けて考えていませんでした。しかし、役員をやって初めて気がついたのです。「方針をいかに伝えて、ベクトルを合わせ、それを具体的にどうするのか」という計画までやることは会社も同友会も同じです。
第二支部の行動指針が、しっかり役員さんに伝わっていけば、きっと一年間すばらしい活動ができると思います。しかしベクトルが合わないと、何をやっていたのだろうということになります。
リーダーは率先して経営指針づくりに
支部方針で「経営指針」を掲げても、支部行事のテーマがまったく別のものになってしまったり、地区活動で「これが同友会」といった活動になってしまう恐れがあります。
私達リーダーが、今年はこんなことをしたいということを会員にしっかり理解していただく。つまりベクトルを合わせながら、その方針をどう進めていくのか、腹に落としていかないと、一年間の活動はできません。
そこで一番大切なのは、役員自身が経営指針に取り組み、組織のあるべき姿を共通にとらえられるような感覚を身につけることです。これが役員像だと思います。
謙虚さが役員の資質
わが社は、社員が十二名の小さな会社です。そんな会社の人間が、会員三百名の支部を率いていくのですから、謙虚に人の話が聞けないと。それが経営者としての資質向上になってくると思います。
地区会長さんの中には「私の地区が正しい。支部や他の地区は知らない」という方もみえます。では会社の中でそのようなことを言ったらどうなるか、ということを理解していただきたいのです。
企業の運営(経営)も会の運営も同じ組織として取り組んでこそ、役員自身も成長し、会も前進することにつながると確信しています。
役員はボランティア?
よく、役員さんから「ボランティア精神」とか「役員は疲れる。もうたくさんだ」という言葉を耳にします。それは、役員をやる姿勢が理解できていないからだと思います。
「他の会員さんのために」とか「役員だから」という自己犠牲的考え方では疲れるのは当たり前です。「役員だから他の人よりも会からいろいろなことが学べる」「自分の会社を良くするためにやっている」と考えて実行すれば、必ず自分自身が得をします。
役員は基本を大切に
増強本部長の時「増強とは同友会理念の普及である」と成文化しました。一度皆さんに考えていただく材料となれば幸いです。
新入会員さんが初めて参加する例会で、会員がダラダラと遅刻してくる場面を見かけます。立派な増強や受入れの方針を掲げていても、こんな基本的なことができなくて、増強や受入れができるはずがありません。
今年度は良い地区例会をして、地区を活性化させ、新しい会員を迎えようと言っていますが、もっと簡単に考えれば、基本的なところを役員さんが率先して実行していくことが大切では。
日々の私達の姿が、同友会を引っ張っていく原動力になっていくと思います。
【文責 事務局・中村】