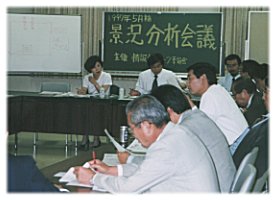チャレンジ経営指針成文化
理念成文化から二年
共育企業への一歩を踏み出して
新井 雅樹 太陽電設㈱
(第一青同)

九月十二日・十三日、福井で開かれる第二五回青年経営者全国交流会(青全交)の第四分科会(は経営指針)で、第一青同の新井社長が報告されます。
昨年六月の「同友Aichi」で経営指針の取り組みについて寄稿され、一年。新たな目標に向かって挑戦しています。(以下は昨年六月号での要旨)
一九九四年夏、社長である父親の辞任で突然社長に。同友会で学び、経営指針を成文化。銀行は経営計画書と社長の熱意に無担保融資を決定。全社員一泊合宿を開き、「夢を形に…」と徹夜討論で感動を分かち合い、共育企業をめざす。
退職者が出て 真剣に悩んだが
反面、悲しい事もありました。理念、計画を深く浸透させていく中で、退職者が三名も出たのです。人生観や価値感はそれぞれが違うので、やむを得ない部分もあるでしょうが…。昨年の一時期、「なぜだろう」と本当に悩みました。
しかし会社に残り、共に奮闘してくれている社員もいるわけですから、ある意味で踏んぎりをつけました。「当社はもう旗印が掲げられたのだから…」と。残念ですが、このように言い聞かせるしかありませんでした。
昨年末の忘年会でのことです。この席上で社員達がお金を出し合って、私に腕時計をプレゼントしてくれたのです。そして社員代表が「社長ありがとう」という旨のメッセージを全員の前で読み上げてくれたのです。
大変感動し、思わず涙があふれて、とまりませんでした。なんて幸せな社長なのだろうと。今までやってきたことが間違っていなかったのだと。
人に始まり 人に終わる
企業は人なり。仕事をするのは人間であり、人生においても人で始まり、人で終わる。すべては「人間力」に尽きると思います。
昨年より共同求人委員会に参加し、四名の新卒者を採用できました。彼らには合同入社式や新入社員実力養成講座にも参加させ、幹部社員は現在、共育委員会が主催する「リーダー研究会」にお世話になっています。
また、経営計画書に基き、初めて社内で新入社員研修も実施できるようになりました。 最近、来客の方々に起立して、全員で挨拶することができるようになり、お客様に「あの会社へ行くと社員が全員起立して挨拶してくれる」と驚かれもしました。
人間として当り前の事とは思うのですが、なかなかできなかったことです。経営手法だとすぐにでも真似できると思うのですが、「人間力」については蓄積していくしかありません。
学んできた新入社員が正しい挨拶の仕方を、逆に先輩社員に教えるとか、確実に活き活きとした風土が形成されつつあります。
夢への架け橋づくり
再び、社員を中心にスタートした事があります。中・長期ビジョンの見直しと、現在の企業理念をより深め、「私達はどう生きていくか」を成文化しようというプロジェクトです。会社を越えて「人間としての生き方」についての価値を共有化できたらと思っています。
社員も難しい課題に正面から向かってくれています。結果として文章にできたら、経営理念が本当に私達の腹に落ちると確信しています。
当社は二〇〇〇年に創立二十周年を迎え、新社屋の建設などがビジョンに盛り込まれました。理念、方針は生き物であり、絶えず具体的に発展させなければだめだと感じています。
まだまだ問題が多くありますが、現実とあるべき姿に架け橋をつくるのが社長の仕事だと思います。この困難に向かっていくことに、今、充実感さえ感じています。
◆創 業 一九八〇年
◆資本金 一千万円
◆年 商 三・八億円
◆社員数 十四名
◆業 種 情報ネットワークシステム、自動搬送設の設計・施工・監理
景況分析会議(6月16日)
足踏み続く中で、体力格差拡大
村上 秀樹 情報ネットワーク委員長
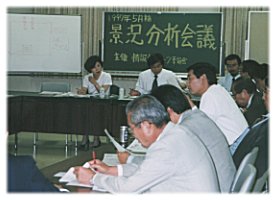
「五月末の景気動向を調べる分析会議は、二百四十六通のアンケート協力の方にも参加を呼びかけ、二十名の出席で開催されました。
今回注目されたのは、四月から実施された消費税率のアップにともなう各業界での影響でした。売上では建設業をのぞき、現時点ではそれほど目立った変化はなく、特別減税の廃止影響などを含め、今後の研究課題となりました。 また出席者全員から自社企業や業界の動向を発表していただきました。
各業界での状況
(1)機械設備
空洞化が問題となっている製造業では、海外に部品製造などがシフトしていますが、製造ラインとなると国内に戻り、部品調達や修理をするので、現在はわが社の業績は順調です。
(2)小売業
規制緩和で大規模小売店が東海地方にも激しく進出し、店舗展開が非常に難しい時代になってきました。小規模店と大規模店の格差が顕著に見え始めています。今後どの方向でどこと組むのかが、一番のポイントです。
(3)建設業
建設業では、消費税の駆け込み需要により三月末までは順調でした。四月以降は今回のアンケート結果にもあるように、DI値が二月のプラス一八からマイナス三五と極端な落ち込みを見せています。
まだら模様の景気動向
一部を紹介しましたが、新聞などの発表と異なり、中小企業の生産・収益・設備投資の回復テンポが大企業に比べ、大幅に遅れています。
そして同規模・同一事業者間でも業況判断が大きく開き、二極分化の傾向が進み「まだら模様」的な景気動向を生み出しています。
詳細は「調査・研究・提言」の項目をご覧ください。