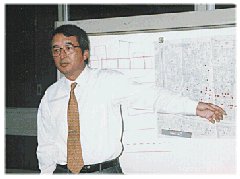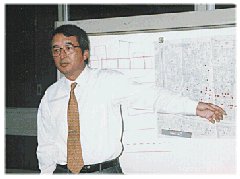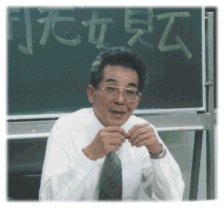■広報委員会8月28日■
街づくりに取り組んで
高岡正昭氏(株)連空間設計
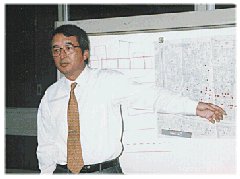
連空間設計では建築設計のほかに「街づくり部門」があって、区画整理事業や商店街の再開発など、地域活性化のお手伝いをしています。高岡氏はまず「地域づくりに同友会がなぜ取り組みのか」から話を始めました。
なぜ同友会が地域づくりに
戦後日本は、大量生産・大量消費の風潮を背景に、効率化や均一化に向かって一途に進んできました。近年、高齢化社会の進展などで地域への関心が高まっています。地域経済の担い手である中小企業の果たす役割は重要度を増すと同時に、私達中小企業が、今後生き延びていくための重要なキーワードが、そこに隠されているという視点でとらえています。そこから同友会が理念として掲げている「地域と共に」が明確になってき、地域でのネットワークとか、商店街の再開発などに、同友会が積極的に関わっていくことになるのです。
大曽根や大須の街づくりから
高岡氏は永年の実績より、大曽根の区画整理や大須商店での街づくりを例に挙げて、自社での取り組みについて話を進めました。商店街や街づくりの方法として現在、連空間設計で行っていることは、要約すると以下のとおりです。(1)まず具体的に現状を識る。これにはその街のタウンウオッチングや、地元の人達に集まってもらって意見を吸い上げる。(2)モデルケースなどの写真を大いに利用して、人達にイメージを掴んでもらう。(3)そこで生活する人々の視点で計画を立案する。街づくりには看板、広告塔、店舗、道路などといったハード面と、行政との関わり方や美的感覚、空店舗対策といったソフト面があり、両方が求められます。例えば「空店舗対策」と言っても、その店一軒だけの問題でなく、商店街全体に影響を及ぼし、トータル的にマネージメントができる組織づくりまで求められます。
生活者の匂いがするそんな街を創りたい
高岡氏の今後の街づくりの夢としては、「生活者の匂いのする、住工一体の街づくり」だと言います。また住宅地と工業地を分けるような街づくり政策には、「子供や老人のいない商店街や、人の住めない工業地から良い文化が育たないのではないのでは」と危惧されます。街づくりはひとつの取り組みにしても五年から十年が必要で、息の長い仕事です。また、緒々の思惑や個々人の事情がからむことなので、非常に辛抱強い取り組みになります。知立とか岡崎、安城、豊橋や田原といった三河地方の駅前の再開発等もずいぶん手掛けられていることを知り、三河在住の私は、新鮮な驚きを感じました。明日から地元への見る目が変わった委員会でした。
竹内襖材(株)竹内武司(広報副委員長)
技術開発委員会8月20日
新製品開発にかける情熱
中小企業創出支援事業の第一号認定
福田義久氏日進エレクトロニクス(株)
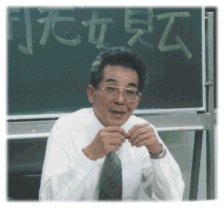
日進エレクトロニクス(株)では、今後インターネットを通じて広まるであろう「電子マネーシステム」に不可欠な「音声認識による身分照合システム」を開発しています。これに必要な資金を調達するため、ベンチャー育成をめざす県の中小企業創出支援事業の指定を申し込み、第一号として認められました。この認定により金融機関からも融資の申し出が相次ぐようになりました。融資額は二回分で一億円から二億円です。この融資を受けるための書類はそれほど難しくありません。むしろ融資を受けるための面談では、いろいろ細かく質問されました。開発したい製品がどう完成し、どの部分にどのような回路や部品を実現すればよいかなどなど。非常に計画性と実現性を問われる質問があい続いたそうです。そのための実験データの提出も行いました。「資金が足りないからこの融資を受ける」といった漠然とした考えでは、この融資を受けることはできません。新商品完成までの順序だてや他人をしっかり説得できる客観性がないと、この融資は受けられません。そして新商品の開発に対する企業としての情熱がないと難しく、こんなことも質問されたそうです。この融資を受けるためには高度な発明を要求されるものではなく、自分だけのオリジナル性があればよいのです。嗜好品、日用品でもよいようです。しかし、過去に同じようなものがないという斬新性は必要です。ただ、この融資の認められた企業は、制度が新しいということもあって、全国でまだ三十数社を数える程度です。技術開発委員会では他委員会とも協力し、「技術」への融資制度全体の検討も考えています。
若原国際特許事務所若原誠一(技術開発委員長)