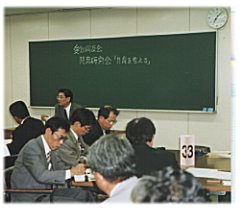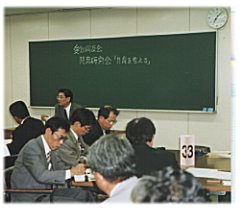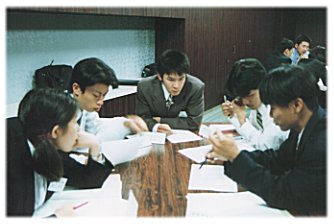共育委員会・第一支部共催9月29日
「共育」オリエンテーション
共育研究会の「オリエンテーション」が九月二九日、共育委員会と第一支部の共催で行なわれました。共育委員会はこれまで「共に育つ」という視点から、新人社員研修やリーダー研修、また今年二月には「共育フォーラム」で「共に育つ条件を考える」をテーマに、愛知県立大学山田正敏先生に講演をお願いしてきました。 しかし「共に育つ」では社内での日常的な取り組みこそが大切です。同友会では「社長が変われば社員が変わる。社員が変われば会社が変わる」と言いますが、それでは『社長が変わる』とはどういう意味なのか、また『どう変わればよいのか』など、経営者自身の課題を明確にしていかなければなりません。そのために、継続的な研究会である「共育研究会」を今回発足させました。オリエンテーションでは、鈴木副代表理事(㈱丸豊社長)から、自社での体験を導入部として、同友会の「労使見解」や中同協の赤石会長の講演要旨を引用し、「共育を考える」と題して報告いただきました。続いて,岩田共育委員長から「共育委員会の取り組み」について報告。後のグループ討論では、参加者三十六名が六グループに分かれ、それぞれに自社での経験を基に「共に育つとは」を話し合いました。
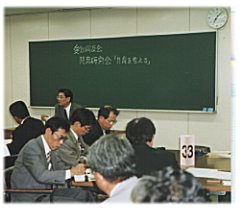
同友会の考えを整理し、語る鈴木氏
共育委員会9月17・18日できていない自分に愕然!
新入社員フォローアップ講座
新入社員実力養成講座」の修了生を対象に、①入社後六カ月、これからの自分達に期待されていることは何か、②学んだことが修得できているかを確認し、修正、補足を行なう、③よりよい人間関係をつくるための自分達の役割は何なのかを目的として,フォローアップ研修が行なわれました。三十三名が参加し、講師には共育委員会のメンバーが当りました。自己紹介から始まった研修会の第一講は「仕事を通して自らを高め、可能性にチャレンジ」をテーマにしたグループ討論と講義。その後、基本修得度チェックと題してビデオを使っての実習、続いて「よりよいコミュニケーションづくりのため」のゲームと講義で、最後は全員の自己宣言の発表という入社六カ月の人達に充実したスケジュールでした。しかし感想の多くは、「四月の研修で習ったことが自分ではできていると思っていたが、できていないことがわかった。基本を忘れず、半年後には先輩社員になるという自覚を持ちがんばる」という積極的な声でした。
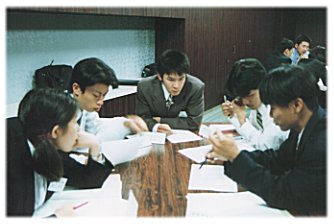
「今の自分にできているか?」真剣に討論
時短定着のための助成金加藤徳夫加藤労務事務所
(労務労働委員会・副委員長)
九七年四月から労働時間の四十時間制が始まり、時間短縮の助成金は廃止されましたが、代わって新しい助成金ができました。該当する会社は積極的にご利用下さい。利用できる範囲この制度を利用できるのは次の条件の方です。(1)常用従業員が百人以下の事業主で(2)九六年十月一日から九七年四月一日までに、就業規則で週四十時間以下にした事業主で(3)九七年四月一日以後に四十時間以下を維持するため、次のどれかを実施した事業主①百五十万円以上の省力化投資をしたこと(従業員三十人以下は五十万円以上)②新たに従業員を雇った事③社会保険労務士等専門家の助言、技術的援助を受けたただし、すでに「時間短縮助成金」を受けた場合は除きます。助成金の金額について支給される助成金は、それぞれ、右記①②③について、次の通りです。①であって従業員が三十人を越える場合は四十万円①であって従業員が三十人以下の場合は二十万円②の場合は二十万円
③の場合は十万円以内の実費なお、受給期限は、九九年三月末日までです。該当するケースは少ないかも知れませんが、もし該当する場合、詳しい手続きについては、労働基準監督署や時間短縮支援センターへご照会ください。
第七回全国女性部交流会(富山)に参加して
第4分科会 女性起業家としての挑戦
伊藤弘子氏㈱伊藤製作所(京都同友会)
手を引っぱってくださった方と、背中を押してくれた夫のお陰で、全国女性部交流会という場に縁を持てたことを深く感謝しております。私の参加した分科会のグループは北海道の方と鹿児島の方を含め、八名のメンバーでした。報告者の伊藤社長の話を聞いた後、各グループで論議をした訳ですが、抱える問題はどの会社でも同じであることを痛感しました。ただ、その時の発想の転換が会社の動向を左右しているのだと思い知らされました。会社にとってのピンチを飛躍する場ととらえ、大きく成長された例が伊藤製作所さんなのです。発想の転換という言葉には何度もふれておりますが、実際に生の話を聞いてまさに「これが発想の転換」とうなずくことばかり。またすばらしい女性経営者の方々に接して、新しい力を吹き込まれた二日間でした。
㈱高山電機青木佐枝子

懇親会で鋤柄代表理事と
第3分科 会地域からあてにされる企業めざして
鎗田貞子氏 ㈱タカサ(千葉同友会)
調剤薬局から介護用品の販売レンタルと事業拡大をしている鎗田社長は「障害とは体の問題ではなく社会とのかかわりあいの問題である」と力説された。介護用品を取り扱う会社としてスタンスを明確にし、同友会で学び、自社の経営指針を社員と共に作成し、奮闘しておられます。介護保険法が実施されれば、今までのように介護用品購入の補助金を役所に申請に行く必要はなくなり、自分の必要とする介護を必要とする時に受けることができるようになります。その時は「病める人の心のオアシスでありたい」と常にお客様の立場で経営しているタカサは地域ではなくてはならない企業として成長しておられるでしょう。しかし、企業としての経済性と社会的使命との狭間で悩みも大きいと素直に悩みも報告されました。「十年間で五十店舗をつくり地域の人の中にとけこみたい」と熱っぽく語る鎗田社長に女性のしたたかさで頑張ってほしいと心から思いました。
(有)高研丹羽スミ子