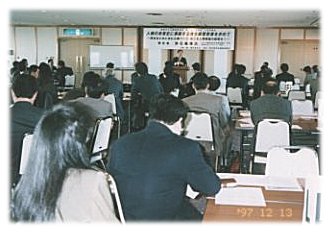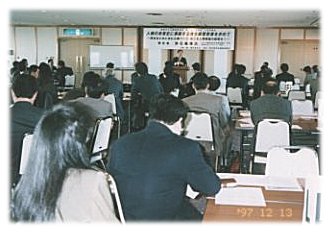第1青同12月13日年忘れ研究集会人類の未来史に貢献する青年経営者像を求めて
赤石義博氏(中同協会長)
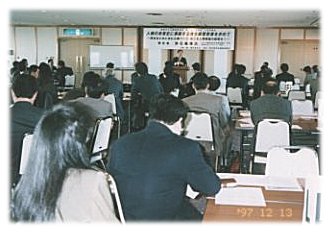
赤石義博氏プロフィール
一九三三年北海道で生まれる。北海道大学卒業後、東亜通信工業㈱に入社。一九六五年同社が月商の約二倍の不渡り被害を受けた時から、実質トップとして経営にあたる。一九七八年代表取締役社長に就任。同友会理念にもとづく自主的自己管理を基本に、同社を電磁鉄芯業界№1の企業に育てる。一九九二年同社社長退任一九九四年㈱森山塗工グループ(東京同友会会員)会長就任。一九六二年当時の日本中小企業家同友会(現在の東京同友会)に入会一九八五年より中同協幹事長一九九六年より中同協会長に就任。全国の同友会運動を推進するかたわら、「21世紀型企業」をめざす会員企業の経営指導にも力を注いでいる。
同友会との出会いから
偶然に経営者になって
私自身が経営者になるきっかけはまったくの偶然からです。入社当時(一九五九年)の東亜通信工業では幹部が全員技術者で、貸借対照表という言葉も知らない私に、「総務から経理から一切頼む」という依頼があり、入社しました。当時従業員数は七十名でしたが、お金なはなく、設備は劣悪、職人個人の技能に頼り切りの品質と生産性、そして「できれば一週間分の材料を積み上げて仕事をしてみたい」と、社長が言っているような状況でした。
従業員のやる気の特効薬を求めて
あらためて中小企業の実態を肌で感じました。これは「従業員がやる気をもって働くしかないんだ」と直感的に感じました。経理などの勉強をしながら、「従業員のやる気のもとになるのは何だろう」と一生懸命に考えました。当時、大隅鉄工所が社員持株制度で非常に活気がでているという話を聞きましたが、どうも自分としてはピンと来ない。「こんな事で人間がやる気になるのか」と思っていました。というのも、戦後のすさまじいインフレで、親父の退職金よりゴム長靴一足の方が高かったりした経験をしていたからです。そういった経験から、私はお金に対する信頼感がほとんどありません。また人間が生きるということと、それをお金という価値ではかるということが、始めからそぐわないと感じていたからです。
 先輩経営者から「経営者」を学ぶ
先輩経営者から「経営者」を学ぶ
そうこうしているうちに、一九六二年に愛知で「名古屋中小企業家同友会」(当時)というものが、創立されたことを知り、名古屋に手紙を出しました。初代事務局長であった仲野さんから親切丁寧なご紹介を頂いて、日本中小企業家同友会(現在の東京同友会)に入りました。入会してみて、先輩経営者の人間的な魅力にひかれました。また先輩達は経済政策についての分析評価能力や着眼点が非常に鋭く、これは大変な人達の集まりだと感じました。入会間もない頃、ある先輩経営者に、ボーナスの相談に行きました。その先輩経営者は「そういえば、今朝、組合が要求書出してきとったな」と言って、ゴミ箱を探し始めたのです。当時は十名規模の会社でも労働争議が頻発し、大変な時代です。ビックリしてしまいました。しかし、正月に福島にでかけ、たまたま、その先輩経営者の工場の看板を見つけたのです。突然寄ってみました。そこは古い学校の校舎を払い下げてもらい、工場にしていたのですが、その敷地内に真新しい建物がありました。「あれはなんですか」と工場長に尋ねたら、一階は社員食堂、二階はお茶やお花を勉強するための部屋になっているとの回答でした。そのニットの工場で働いている従業員は女の人がほとんどでした。そこは、お茶やお花の先生を呼んで教えたり、結婚式を挙げたりできる建物だったのです。この先輩社長は、企業展望のために必要な原資の確保では毅然とした態度を貫くとともに、一方では、お花やお茶の教室など、従業員も大切にしている。これが「人間を大切にするということだ」と言葉ではなく、肌で実感しました。
アメもムチも不要自覚した社員誕生
それから三カ月後、自社の誕生会である若者と言い争いになり、「一生懸命やることと、努力が効率的に成果に結びついているということは違う」と言ったら、この若者は「俺がどれくらい一生懸命やっているか見せてやる」と言い返しました。さっそく彼は自分の機械にカウンターを付け、仕事を始めました。しかし、機械の持つ生産能力の五分の一くらいしか実績が上がっていないということに、すぐに気がつきました。彼もみんなの前で啖呵をきってますので、翌日からいろいろと事前に仕事の段取りをたてるようになり、一週間も経たないうちに、以前の二倍以上の生産量をあげるようになりました。周りで見ていた他の従業員も、「自分も自分も」ということになり、みんなが機械にカウンターをつけて作業するようになりました。そして二~三カ月後、機械数も従業員数も変わっていないのに、以前の倍以上の生産量があがるようになりました。当時は、作れば作るだけ売れて儲かっていたので、設備が同じで、生産が倍になり、当然、非常に利益があがりました。アメでもない、ムチでもない、「自分が自分を管理するという大切さ」を一つの教訓として得たのです。翌年より人事考課や勤務評定に類するものは一切なくしました。一九六五年十一月、月商の二倍に近い七千五百万円の不渡り被害を受けてしまいました。この時、全社員から「いかに困難でも現業を継続し、がんばるぞ」という決意書が寄せられたりもしました。人間としての自覚に目覚めた人間の、その途方もないエネルギーの大きさを知らされたのです。
戦中、戦後の中小企業は
戦時中、国策で百万社が廃業に
一九三八年に「国家総動員法」ができ、それに絡んで同年に「物資統制令」ができました。そして皮革、木綿、ゴムなどの原料の輸入に関して「製品を輸出して外貨を稼ぐようなものをつくるようになっているか」「軍需用の物資になっているか」など以外は、これらの原料を輸入してはいけないという指導が行われました。これで全国で約五十万人の経営者が企業をやめざるをえませんでした。また戦中には「防空法」という法律もでき、「ここに防火帯を作るから、あなたの工場は壊しなさい」というような事を言われたり、「企業整備令」によって強制的に工場統合などをやらされ、やめざるを得なかった企業が七十万社くらい生まれました。したがって、この四~五年の間に、百万を越す中小企業家が、経営を閉じてしまいました。
復興に燃えた中小企業家だが
第二次世界大戦が終わり、全国の百十九都市が焼け野原になり、鉱工業生産能力が戦前の十分の一まで下がっていました。一九四六年には「金融緊急措置令」という法律ができます。この法律により銀行から自由に預金がおろせなくなり、信用に切り替えざるを得なくなります。また戦時の補償をしないという「戦時補償特別措置法」や臨時の増税策である「臨時増加所得税」なども行なわれました。そして、一九四六年の十二月に「傾斜生産方式」という経済政策が導入され、石炭と電力、鉄鋼の三つが、中小企業に廻ってこなくなります。これは徹底しており、重点産業だけに資金も資材も電気も供給していたので、当時私が居候をしていた鉄工所は、週に四回しか電気供給日がありませんでした。中小企業経営者は「日本の復興は、自分たちでやらなければ!」と意気込んだのですが、これらで大きな打撃を受けたのです。一九五〇年の六月に朝鮮動乱が勃発し、その時期に大企業はあっという間に戦前の生産能力を回復します。中小企業は、少ない資材で努力して軽工業品をつくり、輸出し、中小企業の稼いだドルで大企業の原料や機械を買い、日本経済を回帰させていきました。しかし、朝鮮動乱が終わるころには中小企業は大変な不況に入り、当時の中小企業の半分位が、五〇%以下の操業しかできませんでした。

全中協と中政連
このような時代、日産コンチェルンの総帥であった鮎川義介氏は「中小企業の自由競争は風土病だから、法律で守らなければ、中小企業は生きていけない。中小企業を守る法律を作る運動を起こそう」と、私財を投げ打って、中小企業政治連盟(中政連)を結成しました。一方、一九四八年から全日本中小企業協議会(全中協)という団体がありましたが、その多数は鮎川氏の主張に共鳴し、中政連運動に流れ込んでいきました。しかし、後に日本中小企業家同友会を創立した全中協の一部の役員は、「百者百様の中小企業を一つの法律で統制していくというのは、本当にできるのだろうか」という疑問を持ちました。それまでの経験から「企業が繁栄するのも駄目になるのも、自分の判断と努力次第では」ということで、法律によって中小企業を守ろうという中政連に反対をする形で、一九五七年に日本中小企業家同友会が創立されたのです。
同友会の誕生とその理念
「自助努力」の先進性
他の経営者団体と違い、同友会では「自助努力」という言葉をよく使います。この「自助努力」の中身は「自主・民主・連帯」という言葉に要約されます。この「自主・民主・連帯」という言葉は中小企業運動の長い歴史から同友会が学びとったものです。自主こそが本当に自由競争経済をつくるんだ、民主的なルールを守り、すべての中小企業家の声を集めないと、経済や社会に反映させることはできない。いかなる組織も民主的なルールを守ることが大切であるという考えです。このように「自助努力」という考え方を重要視したことは、極めて先進的でした。明治時代から中小企業は、国からは置き去りにされ、中小企業問題というのは「なぜあんなひどいことが」といった社会問題として、学問的にもそういう扱いでした。中小企業施策と言うと「弱者救済」と「不利是正」という二つの柱が基本でした。たとえば一九五七年の経済白書では、中小企業について「低生産性と低賃金の矛盾に陥っている問題がある存在」と表現されています。
中小企業は活力ある多数
しかし、一九九二年、「中小企業基本法」施行三十周の年、中小企業白書で戦後の中小企業問題を総括し、「一九五七年の経済白書では、あんなことを言って悪かった」「戦後に傾斜生産方式を取り入れて、中小企業には大変な苦労をかけた」という歴史的なまとめをしています。そして「中小企業は問題ある存在ではない」との評価を受けたのは、中同協ができてから十一年後の一九八〇年です。この年、中小企業庁の「八〇年代中小企業ビジョン」のなかで「バイタルマジリティー~活力ある多数」という評価を受けました。こういう評価を受け、中小企業には大変な力になったと思いますし、同友会がなかったら、まだこういう評価は受けられなかったと思います。
「自主・民主・連帯」を貫く「人間尊重」
では「自主・民主・連帯」とは何をさすのでしょうか。「自主」とは「個人の尊厳性」であり、「民主」は「平等な人間観」ということです。そして「連帯」とは「人間の信頼性」であり、「あてにしあてにされる関係」のことをさしています。三つの根底を貫いているのが人間尊重の考えであり、三つの側面を持っています。一つは「生命の尊厳性の尊重」、第二は「個人の尊厳性の尊重」、そして「人間の社会性の尊重」です。「生命の尊厳性」というのは「人間は人間である前に動物の一員である」「生態系の一員である」というところに基本を置いた考え方です。身近な例で言うと、「社員には健全な生命を再生産できる給料を払っていますか?」「安全な職場を作っていますか?」「そして環境の保全まで社長の義務だと思って取り組んでいますか?」ということにもなります。次は「個人の尊厳性」です。一人の人間の出現率というのは五十兆分の一で、一人一人は様々な可能性を持っています。だから、様々なことにチャレンジして、その人が持っている可能性を最大限に引き出さないといけないということです。「人間の社会性」ということになりますと、人間というのは人に誉められたり、喜ばれたりということ、「あてにしあてにする関係」をに誇りを持つというところにカギがあります。
近未来社会像と中小企業像
需要の本質の変化
さて、中同協で「二十一世紀型企業」を提案したのは、一九九三年の第二五回総会(札幌)です。「空洞化」と「バブルの崩壊」ということで、今までのような経営のやり方ではこれからの時代は、やっていけなくなるという認識から生まれました。さらに現在、これまでの日本の基本経済政策であった「キャッチアップ型経済政策」が無意味になってしまっています。つまり、日本の常識だとか、経済政策の重点だとか、すべてダメになってきています。そしてもう一つ。それが「金融ビッグバン」です。自由競争の一番悪い点が集約して出てきており、これは、ごく少数の勝利者を生み出すものでしかないのです。しかし、現在の激動というのは新しい変革へのシグナルだと私は思います。大量生産、大量販売の時代が終わり、日本の国民は「量の充足」を経過してきたことによって、需要の本質が変化してきています。この変化の内容は、①質の追求、②ニーズの多様化、③目的別選択基準の明確化、④サービスが安全・健康・老後にどのように影響するか、⑤自分の求める物を見出してくれる人の発見要求です。このような需要の本質的変化の中で、二つの経営課題を引き出していきたいと思います。一つは、五つの変化に丹念に対応することによって、小さな仕事を無数につくることです。もう一つ、質の追求だとかニーズの追求だとかは、個人としての「自我の覚醒、個人としての自我の明確な発生」だということです。
企業の有用性とは
ここから、求められるべき近未来社会像が出てきます。「有限資源節約型経済」と「地球環境保全型社会」です。現在の世界は石油を基本とした文化でなりたっていますが、この社会をなぜ変えなければいけないかというと、環境と両立しないものだからです。経済を急速に発展させようとすれば、多くの資源をつかわなければいけません。そういうことを続けていけば行き着く先は解っているわけですから、持続的に発展できるような経済に変えて行かなければいけません。また「企業の有用性」というものを考えますと、それは三つの側面を持っています。一つ目は、その企業が作っていたり、扱っている商品やサービスが、それ自体、有用性を持っているかどうかという点です。二つ目は、地域社会をどれだけ振興できるかです。地域振興というと経済的な面だけでなく、実際はそこで自然環境を破壊して地域振興が行われています。ですから企業の役割の中に「地域振興における環境保全」という視点が必要です。そして、明確にしておきたいのは、地域振興で雇用を守るということです。それで人々の暮らしが成り立っていくわけです。ですから、地域振興の具体的な企業の役割は環境保全と雇用維持です。三つ目は、働く人々が「自分の人生をどう充実させていくのか」を自覚的に取り組んでいけるようさせる役割を企業が果たすかです。
変革の時代は創造の時代
無数の小さな仕事づくり
では「人類の未来に貢献する青年経営者像はなにか」ということで大切なのは、今まで語ってきた「自我の覚醒」と「需要の本質の変化」という二つの側面から見ていくことです。例えば、十人の企業があったとして、その中の一人が自分だけで食える新しい仕事をつくる。「小さな仕事を無数につくる」ということです。その時に残った九人で十人分の仕事をこなすことができれば、一〇%の生産性と収益アップにつながります。その時、新しい仕事に取り組んだ人が「首切りの第一候補として、俺が指名された」と思うか、「俺はみんなから信頼されているんだ」と思うか。このことは自覚を持って仕事に取り組くむかどうかで、大きく変わります。
貪欲な学びと誠実な生きざまを
「同友会がどんな会か」といえば、科学的な経営戦略を立案する知識と能力を学び、磨きあう会です。そして、そのようにして立てられた科学的な経営戦略を一二〇%実践できる人材づくりを会で学びながら、実践していく。この二つを実践するのが同友会です。今、「有限資源節約型経済の確立」と「環境保全型社会」を一日も早くつくりあげることが人類の課題です。そのためには人間尊重の経営の中で育てられ、人間的な自我に目覚め、自ら学び、自ら世の中に役にたつことを自らの生き甲斐にするという人づくりが急務です。一方でそういう人だからこそ、「小さな仕事を無数につくる」という立場で仕事ができるようになり、そういう社員ができてはじめて、企業自体も発展していきます。創造には瞬発力と膨大なエネルギー、そして熟成のための時間が必要です。変革の時代というのは、過去の経験は生きません。その証拠に明治維新をやり遂げた志士は、みんな二十代から三十代前半でした。激動は「革待望のシグナル」です。この時代には皆さんのような若い力が、世の中をリードしていくのです。より深い同友会理念の理解と実践の中で精鋭は生まれ、より高い理論(戦略)のもとでこそ、より高い成果に結実していきます。若き同友会運動のリーダーには貪欲な学びと誠実な生きざまが求められているのです。
【文責事務局・内輪】