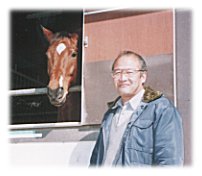地域に根ざす中小企業ネットワーク

福島敏司氏愛知同友会・事務局長
地域型中小企業共同体
難しそうな、それでいて何となく理解できそうな、そんなテーマが、福島事務局長の用意したレジュメにありました。規制緩和の進行やグローバル化の中で、「今、なぜ地域か」を枕に、サードイタリヤでの中小企業ネットワークの紹介や東京・大田区での経験など、「共同」とは何かを、同友会会員の実例で、分かりやすく、そして念入りに、軽妙に語ってくれました。「ネットワーク」のキーワードを紹介すると、まず「欲しい・したい」モノは何ですか。これがネットワークの第一歩で、①情報交流(仲間・相手探し)、②ものづくりの段階(得意技を生かした「共同作業」)、③販売段階(どんなルートがあるか自力でやる、外部力も借りる、支援機関もある)です。そのためには「幅広い交流のベース」が必要で、同友会は絶好の交流場所であることを強調されました。
ネットワークを成功させるには
取組の理念は「社会性・科学性・人間性」で運営は「自主・民主・連帯(ボス不在)」であり、各社の得意ワザが明確になっていることです。そして市民運動・大学の研究機関、教授・専門家等の公の機関もまきこみ、仲介者・コーディネーターが存在するかなどなど。特に「事務局がコーディネーターの役割を果たせるかどうか」だと福島氏は熱く語り、結びとしました。
あるグループ討論より
(A氏)私も大田に行ってきたが、ダメなところはドンドンつぶれているようだ。しかし報告にあるように「ネットワーク」をよく理解し、仲間づくりをして、コツコツと模索してきた企業は成功しているよ。しかし、愛知の企業は何でもかんでも自社で取り込んでしまう「自己完結型会社」が多く、ここをどうするかがこれからの課題ですね。
グループ発表より
同友会に、真面目に参加し活動することが、ネットワークづくりの第一歩。地区だけではなく、他地区へも出かけて、ネットワークを拡大しましょう。★このような経済状況では、自分一人の幸せよりも皆んなの幸せを考えていかなくてはいけないと思います。そのために、このネットワークという道具を使ってそれを実現できれば。★自分の業界では大変なことでも、ある業界から見れば大した問題でないことがある。また、ある業種の技術が他の分野で役に立つことがある。互いに自分の技術・商品をPRする場として、また、お互いに何かを学ぼうとする気持ちが自然にネットワークを構築する。参加者二十三名、学び多き例会であり、学んだ分だけ課題として、地区がどう取り組むかを、考えなければならないと痛感しました。
㈲ベスト測量設計稲葉晋介
地域と共に歩む中小企業②
ありのままを市民に開放して㈲愛知兄弟社(天白地区)
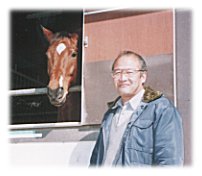
尾関社長
日進市にある㈲愛知兄弟社の尾関信一社長(天白地区会員)を訪問しました。愛知兄弟社と聞いてもピンとこない方も多いと思いますが、東名高速三好インター付近から見える「愛知牧場」はご存じの方も多いと思います。広報委員会で討議し、まとめてきた「地域と共に歩む中小企業とは」の取材視点に基づき、取材させて頂きました。
東名用地売却で牛乳工場をつくる
上海で織物会社を経営し、クリスチャンであった尾関社長の祖父が敗戦によって帰国します。戦後、日本が一番必要としていた食料を増産し、国民の食料不足のニーズに応えるべく日進の地に入植し、一九五四年にこの愛知牧場を拓きます。尾関社長が七歳の時です。土地がやせていたために家畜を入れて、酪農農家として周囲を開墾し、牧場を広げてきました。「最初に開墾した土地は、残念ながら人工池の下になってしまって」と、昔を思い出し、ちょっと残念そうに尾関社長は語ります。やがて時が過ぎ、大きな転機が訪れます。東名高速道路が敷地内に通るようになり、一部農地を売却せざる得なくなったのです。その資金を元に牛乳工場をつくり、生産量の拡大を図ることができました。二十年程前の話です。しかし、牛乳の出荷量が増えても、独自の販路を待たず、自分の手だけで牧場の牛乳を配売するには限界があり、また、新鮮なまま配達するには時間的な制約もあります。もともと地元住民の少ない土地だけに、商圏が遠くなればなる程、そして頑張れば頑張るほど、配達コストが高くつき、経営は苦しくなるばかりでした。
保育園児の農業体験がヒント
解決する方法がないかといろいろと思案します。当時、創業者の祖父が、近くの保育園児のため、無料奉仕で農業体験の「いも掘り」のために牧場を開放していました。これをヒントに幼稚園児や小学生に農作業や酪農体験の場として安い入場料で解放したのが、地域の人達と直接関わるきっかけになります。さらに地域の人達の憩いの場としての牧場開放へと、多角利用を計ります。尾関氏が十年前に社長になってから「小動物広場」「家庭菜園」「乗馬クラブ」「パターゴルフ」「バーベキューガーデン」など、牧場全体を活用します。自然の中で動物と触れ合い、駆け回り、おいしく牛乳を飲み、憩える場を一層増やしてきました。また今年より酪農補助事業として、敷地内に「ビジターハウス」の建設も進めています。このハウスは農業事業者が自作の農産物を直販し、産物PRをする目的でつくられています。地域の人達が集まり、文化的な体験教室を開催し、そこで人と人、地域と地域がコミットする場から文化が生まれます。十年先、二十年先にも喜んでもらえ、日進市と愛知牧場の繁栄の核になればと期待されています。

牛舎には180頭のホルスタインが。ずっと食事中です。
「牛がおしっこやうんこをする」
現在、乳牛一八〇頭、乗馬三〇頭がおり、年間来場者数は二十五万人を越します。ただ、春と秋の一時期に来場者が偏り、一万人もの人でにぎわう日もあるそうです。「来場者にはお金を払ってもらい、牛の世話をしてもらっています。みなさん喜んでやってくれますし、経営者としてはこんなにうれしい事はありません」と尾関社長は語ります。最近、畜産や酪農が自然環境保全と深い関わりを持っていることや、その生産の大切さ、従事している人々の工夫や努力が注目され、小学校の実地体験の教材ともなっています。「牛がおしっこやうんこをする」。子供達の驚きの声です。生き物である以上、当然なことですが、あまりにも自然に触れることが少なくなった子供達。「学校では工業見学やスーパー見学など体験学習をしていますが、ぜひ牧場を見学、『自然の営み』をもっともっと子供達に、生きるものの生理を学んでもらいたいのです」と熱く語ります。
牧場には発見と驚きがいっぱい
①風景として見よう、②牛舎の中の工夫を探そう、③仕事への想いや願いを聞こう、④生き物として牛を感じようを目的に、年間を通じて地域の人達に自然と触れあうイベントも開催しています。大人から子供まで、一日中楽しく遊べる愛知牧場。尾関社長の想いは広がります。「今、私がやらなければならない事は、何度か足を運んでもらえる場づくり、年間を通じて来ていただけるリピーターをいかに確保するかです」と話されます。今回の取材を通じ、一昨年の愛知全研での中京大学・野原教授のレクチャーが思い出されました。「基本的に中小企業の本拠地は、自分がくらす暮らしの場であり、そこから離れられない。地域経済の担い手は事業の中で利益を追求すると共に、地域の環境、あるいは資源を大事にする。そして地域の充実のためにさまざまな配慮を行う。自らのためにも行わざるを得ない。そのことが今、大いに求められているのです」と。このことを経営の中で実銭し、地域に根ざした企業として二十一世紀に向けて益々躍進される㈱愛知兄弟社である事を確信しました。
広報委員 近藤久修

道路に面した案内看板
〈問合先〉
㈱愛知兄弟社(愛知牧場)
日進市米野木町南山977
TEL 05617―2―1300