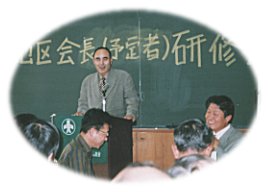新年度地区会長(予定者)研修会
同友会理念を学び、自社の発展に

鋤柄修氏㈱エステム(代表理事)
会員は愛知同友会に入会する
まず皆さんに押さえていただきたいのは、「会員は愛知同友会に入会する」という点です。ここがロータリクラブやライオンズクラブ、商工会議所とは異なる点です。つまり「オール愛知」に入会し、「地区に所属する」のです。これが大前提です。次に支部ですが、十五年前にブロック(現在の支部)ができ、五年前にその活動を総括し、五つの支部が誕生しました。まず地区があり、後で支部ができたものですから、古い会員の中には「地区中心主義」的考え方があり、「俺は支部を認めない」といったような頑固な人もいますが。では地区会長の役割は何でしょうか。まず第一に地区の中だけにいてはダメだということです。支部や愛知同友会、そして全国の行事に、参加することです。地区の活動に広がりを持たすには、この事が絶対に必要です。
理念をきちんと持ち情熱を持って語る
地区の活性化は地区会長に課せられた永遠のテーマです。地区は「人」が構成している「生きもの」です。これは企業も同友会も同じです。では活性化のポイントは何か。それはトップが「理念をきちんと持っていること」と「情熱を持って語る」ことです。トップの気持ちが組織に移ります。そしてトップが想ったように組織はなるのです。ですから「自らがどうしたいのか」、はっきりと持つことなのです。そして注意しないといけないのが、中小企業の経営者はすぐ自分で動くことです。これでは組織は大きくなれません。トップの仕事は自分の想いをわかり、行動してくれる人を創ることです。会長の役割はそういった役員づくりにあるのです。このように組織運営を二年程やると、絶対によかったなと思うようになります。
同友会と企業は両輪
私は二十年間専務をやり、五年前に社長になった人間です。本当に「社長」になったのは三年程前だと思います。ある人に「鋤柄さんは一人芝居をやっている」と言われてハットしました。専務時代のクセが抜けず、部下にポンポン言っていたのです。トップは人の意見を聞いて、最後に一言、判断なり、決断するのが仕事です。先に「ああだ」「こうだ」言ってはいけないのです。会社では誰も表だって社長に文句は言いません(陰では言われますが)。そして我流に陥っていきます。同友会では耳に痛い事も言われますが、学んだことを自社に持ち返って実践することが、同友会役員の役割です。
組織は生きものだから指針が必要
組織は生きもので、新しい細胞ができ、古い細胞があかになって落ちていきます。新陳代謝は必ず起きます。会も新しい細胞である新会員を補強しないとおかしくなります。企業と同様、十年間同じメンバーでやっていると、どこかおかしくなるものです。そこには「経営指針」が必要になるのです。愛知では「『指針』『教育』『求人』は三位一体」と言っています。柱となるものがないと十年先、必ずダメになります。ダメにならないまでも発展はしません。同友会の真髄は経営指針づくりにあると確信しています。
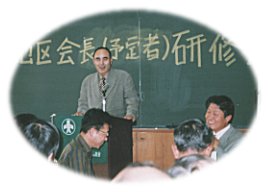
先輩経営者に知恵を借りよう
各企業で困った事を同友会の仲間に相談してみる。一人で考えているだけではダメで、一歩踏み込んで相手の会社に押しかけていって、教えを乞うことです。昔、自社を「職人集団」から脱却したいと考え、ある先輩経営者に相談したところ、「人を入れ替えないとダメ」と言われました。さっそく経営能力のある人間をスカウトし、ある部所内に入れ、脱皮できたことがあります。ここでも「自社をこんな企業にする」という明確な経営指針があったからこそですが。同友会にもう一歩踏み込んで、相手の会社に押しかけて耳と目で学び、自社で実践する、これが会活動の原点ではないでしょうか。
実行なくして説得力はない
同友会の会員はみんな毎日毎日、血の出るような想いをして経営をしている人達です。生じっか理屈を振りかざしても、納得してくれません。ですからリーダーたるものは実行しないと。これがないと説得力を持ちません。私は「経営指針をつくりなさい」と人とあっては言っていますが、最初につくった経営計画書はたった四ページのものでした。その後、随分厚いものとなっていますが、最初は誰でもこんなものではないでしょうか。ただ「つくってみる」という実行が大切で、これも社長の仕事なのです。
強靭な経営体質は人の採用、教育から
同友会の「三つの目的」を正確に覚えているでしょうか。まず一番目の目的の中に「強靭な経営体質をつくることをめざす」とあります。では「強靭な経営体質」とは。まず人です。どんな会社でも最初からいい人材がいるはずはありません。採用から教育に至るまで、すぐれた人材をつくることが強靭な経営体質づくりなのです。それと新しいお客様をつくること。同友会でいう増強です。そして役員の人達が「同友会の考えをどう自社に適用できるか」を常に考えていることが、会の人づくりの中心にあります。
経営者としての総合能力を
二番目の目的は、「いい経営者になろう」ですが、正確には「自主的な努力によって」「総合的な能力を身につける」とあるように、経営者に総合的な能力を求めています。つまりバランス感覚がないといけない、ということです。私は会社を黒字にできる人間が経営者だと思っています。黒字がでないというのは、社会から「お前の会社は必要なし」という無言の圧力をかけられていることだと思います。三番目の目的である「経営環境の改善」について、残念ながら、一番目、二番目の目的と比べ、愛知同友会での具体的な取り組みは遅れています。他の団体とも提携し、会員を増やし、中小企業の経営努力がむくわれる経営環境をめざすことは、行政やマスコミなどから同友会が注目されるような時代だからこそ、一層求められています。

プレッシャーあり!心の中では燃えて
現在、私は同友会理念と企業理念が一体化し、どっちがどっちだかわからなくなっています。持ち歩く「カバン」で「ああ、今日は同友会だ」というくらい会にも入れこんでいます。皆さんにもそれくらい同友会理念と企業理念を同化して欲しいのです。リーダーはとかくプレッシャーを受け、やっている間は苦しさも感じるものです。ただ心の中では燃えていて欲しいのです。リーダーの役割は「同友会理念を学び、自社の発展に生かす」ことです。この点を常に念頭において地区会長の重責を任っていただければ幸いです。
地区会長予定者より
(西地区-藤原氏)私も偶然「同友会カバン」を買ったばかり。代表理事も同じで嬉しかった。(三河東地区-寺田氏)右脚は出ていたが、左脚も同友会に踏み出したい。(緑地区-石川氏)同友会理念を企業経営に生かせば、疲れることはない。(瀬戸地区-伊藤氏)同友会では「知れる喜び」がある。【文責事務局・内輪】
【文責事務局・上田】