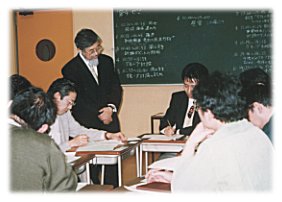第①ゼミ
企業家精神論学生とディベート
小栗崇先生とゼミの皆さん


青同からの働きかけと学生から生の声を聴くことに主眼をおき、前半は三名の経営者が「感性、迫力、魔力」を持ち味として、チャレンジ精神と夢を報告しました。学生の方には事前にこの三社を取材していただき、「個性・挑戦・人脈の大切さ」「コミュニケーションの存在が魅力的な会社の条件」「経営者らしくない」等の素直な意見をいただきました。午後からは三つのグループに分かれ討論。「趣味のようでも情熱一杯」「経営者は三蔵法師より桃太郎になりたい」「労働条件はやっぱり大切」「経営者はよくしゃべる」など学生の本音が吹き出し、価値ある時間を過ごすことができました。中部労務管理センター國井祥行
青同の発表者自身に大変熱が入り、ついつい時間オーバーとなりましたが、何よりも学生の素直で新鮮な発言には、失笑するやら驚かされるやらで、参加者にとってとても良い刺激になりました。やはり学生がイメージする経営者と実際ではギャップがあり、彼等も新鮮な刺激を受けたようです。先生も普段と違う学生の姿に驚かれたようで、正に「産学」が共にに学ぶことができたゼミになったのでは。
近藤運送㈱近藤和彦
第②ゼミ
知多半島・酒と酢の産業史
青木美智男先生

地域の歴史をひも解きながら、産業の始まりから大きく成長していく過程、そして一つの業態がその地域で縮小せざるええない理由などなど。 歴史を学び、醸造という産業の大きな流れを経営的な視野で考えることができた貴重な経験でした。私達は日々の事業経営に追われがちなのですが、歴史を学び、経営を考えることの大切さを改めて感じました。初めて参加し、多くを考えるチャンスとなりました。素晴らしい講義をありがとうございました。
ベイビーズブレス平川直秀
第③ゼミ
環境経済論
薮谷あや子先生

環境経済をテーマに,吹田市役所の課長代理で、地域経済論の専門家の藪谷あや子氏の講義でした。午前中は環境問題、経済の全体とそれに対する日本や世界の意識と関心、世界の規制の現状について説明していただき、昼食時にも先生を囲んで討論は続きました。午後からは、それぞれの立場での環境問題の悩みや質問、これからの規制について限られた時間の中、真剣に先生に質問していました。イサジ興業㈱伊佐治義行
ディスカッションでは、特に建築・建設、そして造園関連、廃棄物にかかわる業種の方々の間で話が展開しました。特に昼食の時間には話がいろいろと進み、盛り上がりました。ただ残念なのは話の展開が講師との関係のみで進んでゆき、そこの場に居合わせた全体のものへと展開していかなかったことです。また別の観点から見れば、参加者の多くが「環境によい」あるいは「環境にやさしい」といった「ことば」に対して好意的すぎるのではないかとも感じました。
中越精機㈱中越英児
第④ゼミ
中小企業の経営戦略会員企業のケースより
関口和雄先生
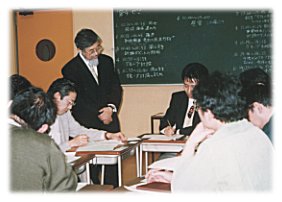
身近な会員企業の実例を題材に、「事業継承を契機に経営革新を行えないか」というテーマでケーススタディーを行い、事業継承する上での問題点をまずグループ討論で抽出しあいました。関口先生からは、事業継承に関わる問題と「製版」という事業そのものが持つ問題、そしてその二つを同時進行で解決していかなければならないと指摘されました。これを受けて後半の討議では、問題点をいかに克服していくかが議論され、「後継者が方針を明確に示すべき」「最終ユーザーに密着し、脱下請けを目指すべきだ」「他の製版分野に進出してはどうか」などの意見が出され、熱の入った議論となりました。最後に関口先生より、「企業の中にある目に見えない固有の技術や方式(暗黙値)をいかに次世代に伝えていくかが注目されている」との解説をいただきました。事業の継承と展開を考える上で、一つの切り口を示せたのではないかと思います。
藤原電機産業㈱藤原聡之