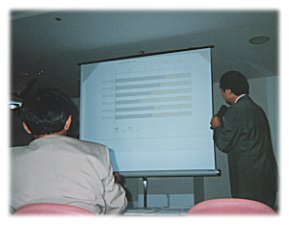三河支部7月24日
「夢」を「かたち」に理念は魂そのもの
理念成文化は指針確立の第一歩

竹内 武司氏(竹内襖材(株))
経営理念は経営指針の一番根底にくるものであり、樹木でいえば根にあたります。幹や葉は目で見る事ができますが、根は地中に埋もれ見えません。しかし、しっかりとした根があってこそ、豊かな幹や葉が育つのです。一般に「経営計画」と呼ばれているものを同友会では、(1)経営理念、(2)経営方針(経営戦略)、(3)経営計画の三つを包括させて「経営指針」と呼んでいます。同友会では経営計画の数字の部分だけを重視するのではなく、経営理念や経営方針(経営戦略)を同じように重要視しています。この考え方に私は強い共感を覚え、素晴らしいと思っております。
企業経営には「物差し」が必要
数字はあくまで目標であり、あるべき姿への「物差し」と考えて考えられます。その物差しと現実とのくい違いがなぜ生まれるのか、しっかり勉強していくことに意味があり、「物差し」という基準がないと、良きにつけ、悪しきにつけ、流されてしまいます。その差が大きければ大きい程、経営者は一層自らのモチベーションも高めていきます。「計画を立てても計画通りに行かないから作ってもしょうがない」という考えに陥らないようにして頂きたいと思います。それでも思った以上に成文化が難しいのも事実です。しかし、ギブアップせず、頑張ってクリアする事こそが、経営者の本当の勉強だと思って、チャレンジして欲しいと思います。
経営者には未来を描く義務が
やれ構造転換だとか、やれ規制緩和だとかいわれ、めまぐるしく経営環境が変化する現在、会社を維持・発展させていく中で一番重要になるのは、「我が社の将来をどうするか」「どういう会社にするか」という経営方針(経営戦略)ではないでしょうか。このためには自社を取り巻く社会情勢の変化度合いを熟慮し、自社の強み・弱みを分析し、あるべき姿への道筋を描く責任を経営者は持っているのです。ここが一番重要で、この大方針が間違うと会社は大変な事になります。戦術レベルの間違いは取り返せますが、戦略レベルの間違いは取り返せせず、会社の命運を左右するからです。
成文化してこそ理念の意味が
この会社の命運を分ける重要な方針を決定する時、大きな役割を果たすのが経営者の物の見方や考え方、つまり哲学です。「自分は会社をどうしたいのか」「自分は何の為に経営するのか」。その人の熱き想いが大きく反映されます。これが経営理念なのです。その熱き想いをまず整理し、社員や周りの人々に知ってもらい、理解を得ることが大切で、文章にして堂々と旗を掲げる事に意味があり、「書く」と「書かない」では大きな違いが生まれます。経営理念は経営者の精神的なバックボーンであり、企業風土の根源になります。経営理念の成文化作業の中から社長と社員の想いが整理・整頓され、社内コンセンサスがとれ易くなる風土が培われてくる、これこそ企業のあるべき姿ではないでしょうか。理念は根底的なものですから、あまり社会環境の変化や事業内容の変化で変えるものではありません。しかし、企業や人間の成長による企業観や人間観の発展に伴い理念が成長していく,これは素晴らしいことです。

「経」とはお経の経「営」とは営々と
経営の「経」とはお経の経、「営」とは営々と続けることではないでしょうか。すなわち、人の道に沿った行いを営々と続けていくということが、世の中のお役にたつということです。それを続けていると、見合ったものが結果的に戻って来るというのが、世の教えではないでしょうか。従って経営という行為は、人様がいないと成り立たないし、経営は社会の中にあって、人と人との繋がりの中にあります。そこで経営理念や経営方針の中に含まれる社会性に大きな意味があるのです。理念といえば、私は同友会理念はとても素晴らしいと常々思っておりますが、素晴らしいゆえに、現実がうまく進まないという側面が見受けられます。同友会は人間尊重を謳い上げ、自主性を尊重し、決して規則で会員を縛り付けるような事はしません。会議は満場一致を旨として少数意見も尊重されますから時間がかかります。その結果は例会参加が五〇%にも満たない現実なのです。ある三河の会員さんがよく言う言葉は、「同友会は行ったり来たりだ」と。残念です。
『売上マイナス仕入イコール利益』に感動
経営指針はやっぱりあった方が良いです。「念ずれば花開く」と申しますが、まずは強く想わないことには何ごとも始まらないからです。私の場合、経営計画との出会いは、十五年前に同友会に入会して間もない頃でした。ある会合で、「『売上マイナス仕入イコール利益』という考え方はやめて、『利益イコール売上マイナス仕入』という考え方をするのだ」という話を聞いて非常に感動しました。早速、同友会の仲間と三河支部の「経営計画研究会」に参加しましたが、なかなか成文化できませんでした。そのような中で、経営者セミナーの実行委員をやった縁で、ある方の私塾に参加し、強い指導を得て、始めて経営指針書を完成する事ができました。決意してから成文化までに一年半かかりましたが、これが六年前のことです。
社長は指針実践の最高責任者に
経営指針の必要性をまとめてみると、(1)自社の将来の展望を思索する絶好のチャンスとなる、(2)自社のあるべき姿を明確にする事ができる、(3)社内・社外のコンセンサスが得られる、(4)民主的な経営ができる、以上の四点にまとめられると思います。経営指針を成文化して一番縛られるのは社長自身だと言われますし、一番破るのも社長だと言われます。経営指針を成文化するということは、「社長中心の経営」から「経営指針中心の経営」へ移行するということです。社長は「君主」の立場から経営指針実践の「最高責任者」へと変身することなのです。
●創立一九七七年
●資本金一千万円
●年商四億五千万円
●社員数四十五人
●事業内容襖(ふすま)下地、完成品の製造販売
【文責 事務局・上田】
三河支部「経営指針に関するアンケート」より
9割以上が理念、方針は必要
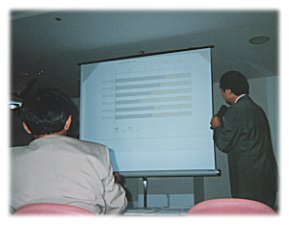
OHPを使った結果発表
七月二十四日に行なわれた三河支部例会の内容を充実させるために、支部会員全員(約四百名)を対象とした「経営指針に関するアンケート」(回答百三社)が行なわれ、当日資料として参加者に配布されました。このアンケートでは経営指針(経営理念、経営方針、経営計画)の有無や社員への浸透度、そして就業規則・賃金規定の有無が企業規模別に分析され、興味深いデータとなっています。特徴として(1)企業規模が大きくなるにしたがって経営指針や緒規定が整備される、(2)「経営理念がない」と回答した三十三社の内九七%が、また「経営方針がない」と回答した三十五社中九四%が「必要である」と回答するなどの点が挙げられています。
(編集部)