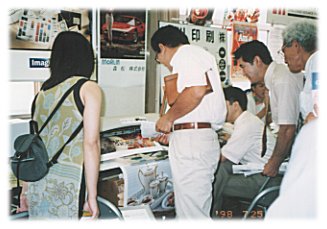中川地区(7月16日)
未来型の受注!横請けって?ネットワークって?
入院体験を人生のプラスに

豊田弘氏 知立機工(株)
豊田氏は学校を卒業後、名古屋の機械屋に就職し、二十四歳で番頭格となるが、二十七歳で結核を患い、入院を余儀なくされる。しかし、持ち前の精神力により、八カ月で退院。この経験が後の人生にプラスとなる。退院後、会社に復帰するが、既に自分の席はない。「社長になってやる」。すべてに前向きに考える豊田氏は、五十万円の資金で会社を創り、七万のトラックと中古機械を使ってがむしゃらに働く。
「社員を首にせよ」
やがてこの地域でトップクラスの企業から仕事の話がきたが、「他社の口座を借りてくれ」との申し出。一度口座を借りれば二度と直接取引のできない世界であり、いったんは断ってしまう。ところがこの企業の方から『仮口座』という手もあるとのことで、直接取引が始まり取引額も月四百万に。仮口座から本口座となる。この間わずか一カ月である。売上比率はこの企業が九〇%であり、バブルの崩壊とともに売上が急降下し、二年で資金もなくなる。この親会社へ行くと、「売り上げが少ないなら社員を首にせよ」とまで言われる。社員にもこのことを伝え、首切りなしで行ける所まで行く決意をする。社員も全員ついて来てくれた。
「特化する」とは
親会社にぶら下がっていてはダメだ。これが横請けのきっかけとなった。何度も会議を行い、自社の強いところ、弱いところを分析し、営業に生かしていく。新規取引には、短納期・高品質・低コスト要求には定評のあるD社との取引実績が強みとなった。D社と取引しているというだけで、説明せずとも信用してもらえた。「特化とは『これだけは』という事ではなく、図面をもらったらすべてこなせる、その中で特にこの部分が得意、それが特化である」と豊田氏は語る。
横請けネットワーク三河支部で展開中
自社でオーバーフローしていても同業者の中にはそれぞれ得意な加工分野があり、そこへ仕事を廻す。また同業者にも呼びかけ、互いに仕事を廻し合い、横請けし、どんな仕事でも請けていく。この「横請けネットワーク」には現在十九社が参加している。つまり各社の営業鞄には十九社の機械設備や能力が入っていることになる。同友会の中でも「横請けネットワーク」の活動として、三河支部の会員十五社で「金属部会」を四月から発足。何ができるか研究中である。
まず技術を磨け
「自分より小さな会社の仕事なんかできるか」といった考えから一転し、自社の技術と価格を必要としてもらえるならば、小さな会社の仕事でもやらせて頂く。それが、信頼と協力で結ばれる強力なネットワークであるということに気づき、年一回のお客様でも大切にしている。過去の競争相手とも手を組み、相手の営業力の方が勝っていれば、素直にお願いして協力してもらう、決して自社だけ良ければいいと言った考えでは続かない。「大切なことは、ネットワークを築く為には、まず自社の技術を磨かなければならない。技術があれば仕事は逃げない」という言葉に豊田氏は力をこめた。
ピラミッド型は崩れている
現在、従来の親会社の仕事の比率を五〇%以下に保っているが、仕事量は減ってはいない。残りのエネルギーは新規開拓に注がれている。インターネットの利用も非常に効果があったと言う。ゴルフで同じ組になった人、呑み屋で隣りにすわった人、工具屋、保険屋さんなど、知り合った人すべての人に声をかけ、仕事に結びつけている。今後、取引先を百社にするのが目標である。昨年十一月の愛知同友会の大田視察にも参加し、名古屋は東京と比べ、危機感が十年遅れているとも語る。「愛知には超巨大企業があり、ピラミッド型の受注で今までやっていけた。しかし、今後もそれでよいとは言えないし、既に崩れている」という豊田氏の経営者としての体験を踏まえた意見は傾聴に値した。
(有)ワイ・テック義積泰典
第4支部(7月25日)
「我が社は『これ』で21世紀に挑戦する」会員66社がPR


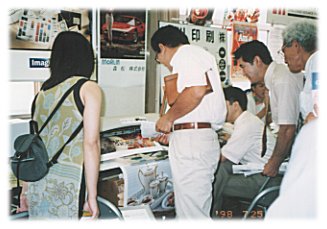

七月の支部例会は「型通りの勉強会ではなく、会員同士がもっと知り合う機会にできないか」という実行委員長の一言がきっかけに開催。「単なる商品展示会ではない。技術でも、理念でも、戦略でも、何でもいいから、二十一世紀に立ち向かう会員企業の『これ』を会員同士PRし、そこから、新しい何かを発見し合おう」という主旨で行なわれました。当日は、第四支部の全地区から六十六社の会員が出展。業種も呉服屋、テレマーケティング、協同組合、砂糖屋、電話屋、コンサルタント、瓦屋、ペンキ屋など挙げれば限がなく、ブースの装飾一切を各社に任せた結果、同友会らしい手作りのブースが並びました。中には「ブースそのものが展示品です」という企業もありました。「出入り自由で、来てすぐに帰ってしまう内容では意味がない」と、開会式の後に各地区一社づつ、五分のPRタイムが設けられました。来場者をあわせて百三十名が仮設ステージの周りに集まり、冷房が効かなくなるくらいの熱気に包まれました。二時間半のフリータイムには、会員間の積極的な交流が行なわれました。目的を販売ではなく、「知り合うこと」においた結果、ブースを訪れた一人一人に時間をかけて説明することができ、来場者には好評で、「次年度以降もぜひ継続を」という声も多数出されていました。
(事務局・井上)