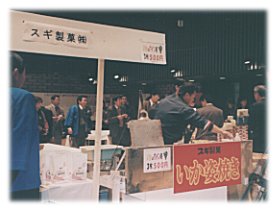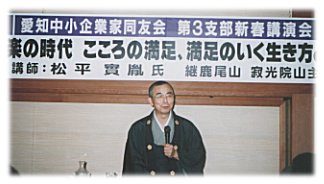第3支部
支部研究会の発足に向け
「経済交流」「ネットワークづくり」に関するアンケートを実施98年12月
第三支部では、昨年十月に「異業種交流シンポジウム」(支部例会)を開催し、ネットワークを組み、市場創造や新製品開発を行っている愛知同友会の会員企業の実践例を学んできました。これを受け、支部で「異業種交流グループ」や「異業種交流の事例研究を行う研究会」づくりのために、昨年末、支部会員を対象としたアンケートを行いました。
七割以上が参加を希望
アンケート項目と結果は以下です。なお、回答数は百八社(回答率二○%)です。(1)異業種交流で新しい商品開発を行うグループ活動に参加してみたいですか?(2)会員企業間で、商品の売買や、仕事の受発注等の顧客開拓に参加してみたいですか?(3)関連同業種で、仕事や技術、設備などの相互利用(横受け)を行うグループに参加してみたいですか?(4)行政の中小企業支援施策等、外部資源活用の勉強会に参加してみたいですか?結果としていずれの質問にも七割以上が「参加してみたい」という回答が寄せられています。
研究会づくりで事前勉強会を開催
また「その他、貴方がお考えになる『異業種・同業種交流活動』は?」の質問には、下記のような文書回答が寄せられています。・交流グループでは、参加者の業態を分け、各業態ごとの勉強会を学習することが必要。・交流グループの相手を最初から特定するのは難しい。広くたくさんの経営者と情報交流する過程で、パートナーを探すというプロセスが必要。・まず会員企業の事業内容(得意分野、苦手分野)の情報交流できる場が必要。相手がよく分かってからの新商品開発だと思う。この結果から、「具体的な会員相互のネットワークづくり」を支部の会員は強く求めいることがはっきりしてきました。「ネットワークを具体的にどう進めるか」をアドバイスできるような研究会をづくりをめざした勉強会が二月九日、十二日の両日開催され,新年度の「支部研究会」づくりにむけた準備が,着々とすすんでいます。
第4支部新会員オリエンテーション1月22日
「同友会で学んでわが社はどう変わったか」山田裕司氏山田ハトメ(株)(第4青同)
商売人として生きたい

二十五歳のとき、大学を出て三年間勤めた会社を辞め、親の経営する会社の後継者として戻ってきました。高校生の頃から「サラリーマンとしてではなく、商売人として生きていきたい。努力しがいのある生き方をしたい」と感じていました。同友会には、会社のお客様から「良い会だから」と言われ、何も分からず入会しました。会社は身内経営で、世間との関わりも少なかったので、人の集まりに参加すること自体が楽しみでした。経営者の会に参加する以上は、後継者としてではなく、「良い経営者になりたい」と思って参加しました。
待ってては何も得られない
入会して思ったことは「同友会は、待っていては何も得ることができない会だ」ということでした。自分から進んで参加し、多くの経営者の方と知り合うことが、自分の変化と自社の成長へとつながっていきます。会社の中では自分ではやらない苦手なことも、同友会では自分でやらなければなりませんので、これも良い訓練になりました。
社長業を楽しみながらやりたい
昨年の十一月に、代表取締役に就任しました。わが社は単価の低い、市場の小さい業界で勝負しています。そこで、わが社は「売れるものは売れ、利益の出るものは何でも売れ」の精神で、売上の増加にこだわっています。経営環境はますます厳しくなっています。販売先の業界全体の縮少に加え、お客様の会社を後継する人が少なくなっています。先行きが不透明な時代ですが、社長が愚痴ばかり言っていては、後継者は育ちません。実際に私は、こんな商売でも、カレンダー通りの休日で、地域活動にも参加し、楽しそうにやっている自分の親を見て、後継を決意しました。私の信条ですが、社長業は楽しみながらやりたいと思っています。生きているうちは頭を使い、会社の方針・計画を作っていきたいと思います。
【文責事務局・井上】
第2支部新春大講演会

「今、社長がやるべき顧客を増やす戦略」牟田学氏の経営講演1月14日
会場の三百席がうまり、補助椅子まで用意されました。売上減・利益減などで赤字経営が多くなった現状のなかで、「自社を見直し、時代に適合して変えよう、変えなきゃ」という危機意識の強さが、参加者の多さにあらわれました。「売上増が利益の根元。売上増とは顧客を増やすこと。顧客を増やすには自分の企業の基本を大切にし、行動すること。売ろうとするものが何なのか。売ろうとする相手を分析しているのか。顧客の分析に基づいての行動を取っているのか」。そして「後はあなた方経営者の実行ですよ」と言外に言われました。牟田氏の明快で、実践に裏付けられた三時間にわたる講演は、あっという間に終わりました。経営者は迷うことはありません。時代のせいではなく、経営者の人間としての生命力(主体性・積極性・行動力・具体性)の弱さが、ジリ貧経営や倒産の原因となります。原因がわかればあとは対策と実行。弱肉強食ではなく、基本のしっかりとした生命力のある企業ほど存続できるという時代なのです。
(有)牧牧克俊(瑞穂北地区)
三河支部新春のつどい
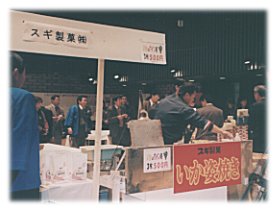
語りあうなかに福きたる会員企業58社が出展1月22日
三河支部の九九年新春のつどいは、従来の会員相互の名刺交換から一歩踏み込んで、「どんなものをつくっているのか」「どんなものを売っているのか」を互いに知り、「ふれあい、学びあい、励ましあい」の具体化としての企業展を行いました。岡崎商工会議所大ホールで行なわれた今回の企業展では、九十四ブース・五十八社が出展し、普段の交流とは一味違う「互いの企業が見える」交流が行われました。
第3支部1月21日新春大講演会
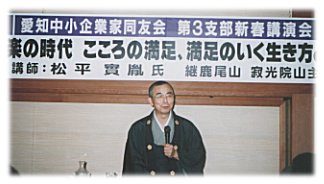
大楽の時代こころの満足満足のいく生き方とは 松平實胤氏寂光院山主