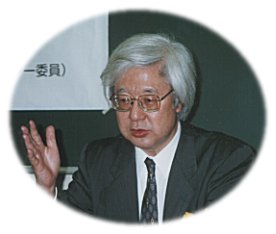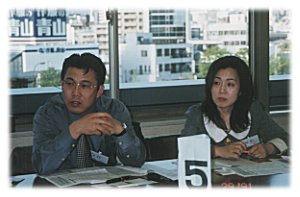愛知同友会第38回定時総会(99年4月24日)−第1分科会
同友会運動の歴史を学び新たな時代を切り拓こう
「99同友会ビジョン」をめぐって
大林弘道氏神奈川大学・経済学部教授中同協・企業環境研究センター委員
(1)はじめに名古屋同友会(当時)が全国で果たした先進的役割を実感して

(A)会員の要求に基づいた実証的な同友会として
現在、私は「中同協30年史」の編纂作業にかかわっていますが、「99同友会ビジョン」(以下「ビジョン」)を読みながら、愛知同友会(当時名古屋同友会)結成時の活動、あるいは、中同協結成に向かう過程での貢献を思い起こしました。名古屋同友会は、その創立当初から、他の同友会に先駆けて、会員の要求をアンケートによって集約し、それを金融機関や地域行政機関に提示し、理解を求め、改善を促がすという活動をしました。そして、そうした行動について成果と反省を細かく点検しておりました。また、会員の減少が生じた時にもその原因を率直に検討し、新たな方針を確立し、実践し、会員の回復を遂げてきたという経験をもっています。
(B)1人ひとりの会員にどんな意味があるのか
さらに、中同協という全国組織を結成する過程で各同友会ごとにさまざまな対応がありましたが、名古屋同友会においては「全国組織が同友会の1人ひとりの会員にどういう意味があるのか」という、重要な問題提起をして、名古屋同友会の全国組織の結成への対応を構築して行きました。加えて指摘しておきたいことは、そうした運動・活動を大切に記録してきたということです。当時、中同協の結成に働いた5つの同友会は、それぞれかなりの個性を持っていました。それらの個性を生かす形で、全国組織を、連合会や単一組織でなく協議会にしたのですが、その中で名古屋同友会は実に慎重な、着実な、粘り強い、創意に満ちた運動を追及したと私は当時の記録を読むたびに感じております。
(2)ビジョンとは「99同友会ビジョン」の特徴とその意義
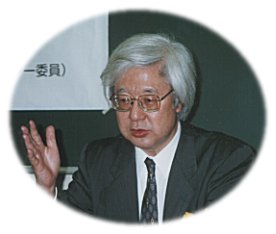
(A)中小企業の時代経営戦略の転換
「ビジョン」の特徴を私なりに読み取りますと、第1の特徴は、中小企業にとっての時代と経営戦略の転換を明白にしていることです。「現在の展開は大量生産・大量消費・大量廃棄という大企業中心の経済構造そのものが変化しているという前提に立って、大企業にリードされる時代ではなく、『自立型の中小企業』が国民や地域社会とともに歩む時代として、人間尊重の企業経営で中小企業自身が新しい企業体質を身につける経営戦略の転換を早急に行うことが求められている」と述べられています。このような把握を前提に、2つの旗印、「自立型の企業をめざす」と「地域社会とともに歩む中小企業」を明確に掲げていることです。そして、第3に、「地域社会とともに歩む中小企業」であるために、「地域の課題」で議論できる「研究会」を編成し、同時に、「地域の課題」を取り上げて活動できる組織として支部を再編成し、「行政地域に対応した新しい支部」を確立するという方針を提起していることです。さらに、第4に、「人口10万人以上の地域」に「1つの拠点」、「100名の組織」をつくり、5年後には3000名の愛知同友会をめざすという具体的な数値目標を提示していることです。
(B)同友会理念の中核「自主」の考え方
ここでまず、注目したいことは、「自立型企業」ということばです。同友会運動においては「自主」ということばが同友会理念の中核を示す概念であることは,改めて紹介する必要はないと思います。私は1997年の中同協第29回総会第1分科会における報告で同友会運動における「自主」の概念に含まれる意味を,7点に整理しました。(資料1)「自立」ということばも事実的には同友会運動の当初から使われていたのですが、より自覚的に使われたのはそれほど以前のことでなく、「自主的努力による自立型企業」ということばで、1997年の中同協第29回総会の総会宣言に登場しました。それゆえ、愛知同友会の今回の「自立型企業」の提案はいわば「ものづくりの拠点」であり、強固に「大企業がリードする」地域において追求しようという意味で,きわめて大きな意義があると考えられます。ちなみに、中小企業庁も昨年の「中小企業白書」で「独立中小企業」を改めて提起しています。愛知同友会の提唱する「自立型企業」と中小企業庁の提起する「独立中小企業」との違いを検討してみることは意義深いことと思います。また、そうした「独立中小企業」が今後どのような意味で展開されるのか、あるいは逆にされないのか興味がもたれるところです。もうひとつ、地域的な「研究会」の編成と「行政地域に対応した新しい支部」の確立が提起されていることが注目されます。そして、それらの成功によって上記の第4の数値目標の実現が期待されるわけです。このような運動の目標を掲げたことは全国各地の同友会においても新しい運動形態ではないかと思います。
(3)諸論点の検討企業の「自立」について考える

(A)「自立型企業」とは
「ビジョン」での「自立型企業」とは、(1)同友会精神の実現を目指していることを前提に、(2)独自の技術的能力、(3)独自のマーケティング能力を持っている企業であると要約することができると思います。その際、私は上記の「ビジョン」から引用した文章の中の「大企業にリードされる時代ではなく」という言葉に注意したいのです。つまり、ここでの「自立」とは「大企業にリードされない」ということになります。下請中小企業や流通系列店は「大企業にリードされた」企業形態の代表でしょうから、「自立型企業」とはそうした企業形態からの脱却と考えてよいのです。そうした脱却は、大企業のグローバル化にともなう国内中小企業との取引関係の後退によって余儀なくされたという側面もありますが、同時に、21世紀を睨んだ大企業でない中小企業をはじめとするさまざまな企業形態へのあらたな注目もあるのです。しかも、そもそも企業というのは「自立」しているのが当り前なのですが、それがそうでなくてもよいと考えられてきたところに、戦後、日本経済の特異な性格があったというのが私の考えです。改めて指摘するまでもないことですが、今後、「自立型企業」だからといって、大企業との取引を消極的にするという必然性はありません。21世紀においても大企業はなくなりませんし、そことの取引もますます大事になります。
(B)価格決定権とは?
ただし、大企業が「価格決定権」を行使するようなことは取引の現実においても、制度的にも許してはならないということです。そのために、「自立的企業」をめざすことが肝腎だということです。なお、中小企業が「価格決定権」をもつことをめざすということは必ずしも正しくありません。競争が自由に、公正に行なわれていれば、いかなる企業も「価格決定権」を持つことができないし、持ってはいけないというのが正しい考え方です。ただし、企業は「どのような水準に価格を設定するか」という経営的課題はあります。この場合、品質の向上やコストの低下の努力を踏まえて、どこまで価格を低くできるかが企業行動の一般的な論理です。
(4)諸論点の検討「地域社会とともに歩む」とは
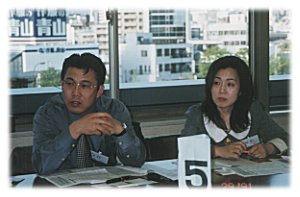
(A)「地域の時代とは中小企業の時代」(82年中同協総会より)
「地域」という概念も同友会運動では、一般に注目される以前から提起してきています。とくに、80年代前半に同友会運動を地域経済振興の中に位置付けたと思います。1982年の第14回中同協総会では、「地方の時代とは中小企業の時代のことであり、地方の時代を切り拓く主体は中小企業である」と定義され、同友会運動において地域経済に根を張る方向の活動が進んだと評価しました。とくに、「工場等制限三法」の見直しと運用、大型店の進出問題、街づくりなどに,「同友会らしい」対応を展開しました。さらに、翌年の第15回総会では中小企業は地域に働く人々とともに、地域に密着し地域とともに生きており、「歴史、文化を含め地域社会に奉仕し、地域社会の担い手」であることを確認し、地域経済振興のための政策について、自治体や専門家ともよく相談し、勉強し、積極的に発言することを呼びかけています。さらに、85年の第17回総会では、地域経済の振興と地域の教育・文化・福祉の向上とがともにあることを強調しています。そして、その後を1997年の第29回総会で中小企業が地域に密着し、根ざした経営を行うことの意義を以下の3点において確認しています。(資料2)
(B)「地域」とは国家で統括できない概念
ところで、「ビジョン」の中で、「地域」とは一体どこを指すのか、全国あるいは世界と取引しているのに「地域」というのはなぜなのかなどの疑問が紹介されています。大事な疑問です。「地域」という言葉は一般にある特定の国の中の一地域を意味する場合(たとえは、愛知県、名古屋市、中川区などの行政区域あるいは木曽川流域、知多半島などの非行政区域など)と、性格の共通する諸国家を統合して世界を分割する名称(たとえば、NICS、EUなど)を意味する場合とがあります。いずれの場合も国家と対置し、国家では総括できない概念であるということが共通の特徴です。それが「地域」の基本的な意味です。「ビジョン」で問題にしている「地域」は最初の場合を指しているわけで,実は中小企業はこれまでもそうした「地域」に依拠してきました。
(C)戦後、地域経済の振興をめぐって
戦後の地域経済振興は2つの課題がありました。1つは輸出型地場産業の振興の問題で,いわゆるドッジライン以降輸出振興は日本の通商産業政策の主柱でありました。しかも、1963年まで、直接輸出の半分以上は中小企業製品で,その中心を占めたのは輸出型地場産業製品でした。したがって、輸出型地場産業は輸出振興政策において重視されていました。しかし、その後輸出製品の大半が大企業製品になり、1970年代以降円高が進行し、発展途上国の追い上げが強まると,輸出型地場産業は困難に直面するようになりました。通商政策においても輸出型地場産業に対して輸出振興の対象から,内需転換のそれに転位しました。もう1つは地域開発です。地域開発とは、政府・地方自治体の一定の地域政策の計画に従って、主として公共投資によって実施される、産業基盤あるいは生活基盤整備のための各種の開発事業を総体と表現する概念です。戦後の日本では1950年の国土総合開発法に基づく特定地域総合開発計画に始まり、その後、数次にわたる全国総合開発計画となって登場しました。これらは一般的には「地域格差の是正」、「過密過疎の解消」を標榜しながら、実際には特定産業の立地展開の公共投資による助長、大企業の地方進出の効率化のための地域整備、交通整備に終始したといってよいのです。大企業の誘致に失敗した場合は開発負担だけが住民に残され,近年はムダな公共投資を誘発するものとしての批判されています。この2つに共通するのはいずれも国策あるいは国家行政の観点から地域経済振興が位置付けられてきたということです。しかもそれらに中小企業は深い関係を持っていたといえます。
(D)東京・墨田区にみる地場産業の育成
また、地場産業のうち、いわゆる伝統的地場産業に対しては「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」が制定され(1974年)、東京を中心に「地域振興条例」が制定されています。最初に制定された墨田区の「中小企業振興基本条例」はその典型例ではないでしょうか。(資料3)「地域論」の隆盛は、結局は人間生活における「消費」・「雇用」・「教育」・「住宅」など、さまざまな意味あいがありますが、共通して「地域」的性格を持ちます。そして、それらが国策あるいは国家行政の主導ではなく、本来意味するところのものが重要だという認識が広まり、深まりつつあります。
(E)「自立」と「地域」
以上の検討からすれば、中小企業における「自立」と「地域」が並び立つあるいは深い関連があることが理解されてくると思います。全国の地域で経営を行なってきた中小企業は、今、戦後を貫いてきた国策あるいは国家行政の主導の、それゆえに「大企業にリードされる」地域経済振興が歴史的役割を終えようとしている事態に直面しているのです。そうして事態が経済変動のきわめて厳しい局面で急激に出現したということであり,「ビジョン」における2つの旗印は、2つ合わせて実現に向かうべき内容だと考えます。
(F)「学び合う」から「研究すること」へ(研究会づくり)
同友会運動は「学ぶ合うこと」を柱にしてきましたが、敢えて「学び合うこと」と「研究すること」とを対比して考えてみたいと思います。私は例会などにおいて、会員自らが「会員講師」となって自己の経営上の問題や経験を率直に話し合うということに優れた特徴があると考えています。ただ、「学び合う」ことが会員の問題の提示や経験の披露だけに止まっているとしたら、それは惜しいことだと思います。提起された問題をさらに深く考察し、経験を整理し、分析することができたら、いわば「学び合う」ことから「研究すること」へ発展させることができたらと、私は常々考えてきました。その際、多様で切実な要望を自ら政策体系にするということが大切で、その意味で「ビジョン」における「地域の課題で議論できる研究会」の編成をめざすことはすばらしいことです。
(5)まとめにかえて
中同協・第3回総会(1971年)方針より地域政治・社会と中小企業の関係
1971年の中同協第3回総会の運動方針の7つの課題の第2番目で「地方政治の中小企業施策の量と質を高める」をあげています。それは、地域社会・地域政策と中小企業との関係を実践的に捉えた最初の文章かと思います。少し長いですが、引用します。(資料4)30年近い以前の課題が、なお中小企業運動に残されているように思います。「ビジョン」にみられる地域への取り組みは、上のような方針の新たな実践段階を意味していると考えます。
【文責事務局・多田】