採用・共育の目的を考える
磯村 太郎氏 サン樹脂(株)

第25期社員と学ぶ共育講座・第3講座での磯村太郎氏の報告を紹介します。
労使見解との出合い
弊社は工業用プラスチック製品の製造、少量多品種のものを切削加工で生産しております。私は2代目で、入社時の社員数は社長含めて8名で平均年齢は46.3歳でした。
私が会社を継ぎたいと思ったのは、腕を磨けば磨くほどお客さんが喜んでくれ、もっと喜ぶ姿が見たいと思ったからでした。そんな自分の気持ちとは反対に、社員を雇用しても簡単に辞めていく姿に、一緒に働く理由が分からなくなった時もありました。しかし、社員が辞めていくのは「頑張った先にあるもの」を社員に見せていない自分の責任だと考え直し、経営指針書を作成しました。
その後リーマンショックがあり、初めて『労使見解』を読みました。労使関係の創造的発展こそ企業成長の原動力であるとまえがきに書かれており、最初に作成した独りよがりな経営理念とビジョンを刷新しました。
心機一転で挑戦した初めての合同企業説明会では苦い経験をしましたが、翌年には採用チームを編成。「どのような人が入社しても育てることができる会社にしたい」と社員から発言があったのは、社員の成長を感じた1幕です。
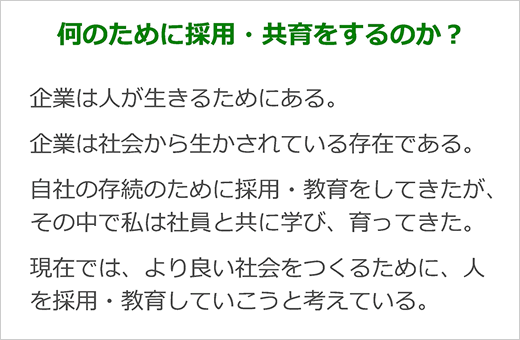
地域目線での採用と共育
採用と共育の目的は企業の維持存続だけにとどまりません。地域から若者がいなくなる原因の1つに、働く場所が地域にないことがあります。全事業所の99.7%を占める中小企業には、仕事をつくり出し、働く場をつくることを責任として求められていると考えています。
また、合同企業説明会では死んだ魚のような目をして来場する学生もいます。そうした表情を明るくできない経営理念では、期待が持てる将来を示せていないことになり、そんな会社に誰が働きに来てくれるでしょうか。
会社は社会から生かされ、人が生きるための器です。私も当初は自社存続のために採用と教育をしていましたが、採用活動を通じて成長する社員から気づかされ、自分自身育ってきたつもりです。その結果、より良い社会をつくるために、採用と共育をしていこうと考えるようになりました。自社都合の社員を育てるのではなく、さまざまな人が輝ける場を会社でつくり、次代を担う若者を育て、企業としての役割、地域の存続を一緒に考えていきませんか。









