同友会の政策提言の真骨頂とは
~中同協50年史より「21世紀の同友会運動、新たな挑戦と飛躍」を深める
和田 勝氏 トータル・サポート 瀬戸
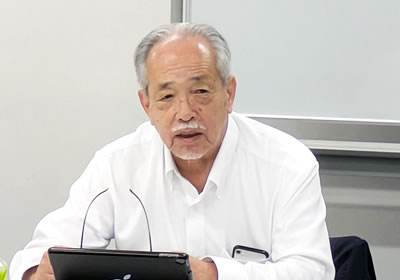
第2期経営者大学では中同協50年史を基に同友会運動の歴史を辿り、その到達点を学び、今後の企業経営、望ましい経済社会のあり様を討議しています。今回は金融アセスメント法制定、中小企業憲章の運動から同友会の政策活動を深める機会として開催。愛知同友会相談役の和田勝氏より、愛知の政策活動史を報告いただきました。
政策運動の要点を確立
「外部環境に無関心な経営者もいるかもしれないが、誰もが無関係ではいられない。中小企業経営は常に外部環境変化に影響を受けており、政策運動は特別なものではない」。和田氏は、同友会の政策運動は「労使見解」の精神に基づき経営者自らが主体的に見解を述べる点、また自らが新しい提案をすることが、他の経営者団体と一線を画する点であると述べます。
1990年代終盤に起こった金融機関による中小企業への貸し渋り、貸し剥がし問題に愛知同友会はいち早く着目し、会員の経営実態を調査。新たな法制度を提案する金融アセスメント法制定運動に取り組み、この運動の意義を5点にまとめました。
第1に仲間の苦しみを共有し、皆で助け合う。第2に、単なる反対運動でなく新たな提案を行う。第3に課題に対し学習し、議論を繰り返す。第4に会内だけでなく広く世論に訴え、共感を得る。最後に自らの経営と経営者自らの姿勢を正す。以上が愛知の政策運動の要点として確立。その後の中小企業憲章制定運動へと引き継がれ、政策運動の大きな転換点となりました。

憲章を自社に生かす
金融アセスメント法制定運動に取り組むことで、中小企業が抱える問題は金融だけでなく、税制、教育など多岐にわたることを改めて認識。日本経済の持続可能な発展を模索する中、EUの小企業憲章に着目し、日本にも中小企業憲章を制定しようと全国運動に取り組みます。
まず学習運動を展開し、憲章とは何か、望ましい日本経済の発展方向を議論。併せて景況調査での会員企業の経営課題も踏まえ、めざす中小企業像を描いていきました。これらが結実したものが、同友会が提唱した「中小企業憲章草案」です。そして、この全国運動を経て2010年に中小企業憲章が閣議決定されることとなります。
和田氏は、私たちが提唱した中小企業憲章草案の実践に会員各社が取り組んでいるかと問いかけます。
草案の前文は「国民一人ひとりを大切にする豊かな国づくりのために、日本の経済・社会・文化及び国民生活における中小企業の役割を高く評価し」と始まり、その期待に応える存在になるための10の指針が提起されています。この10の指針を会員各社が自社の経営課題として経営指針に盛り込み実践すること。すなわち「地域未来創造企業」へと変革していくことが、より良い日本社会をつくり上げていく主体者となることです。「改めて全地区で憲章草案を学ぶ例会を展開し、会員各社が草案の精神を自社実践することを呼び掛けていこう」と報告を締めくくりました。
近年の主な政策運動と成果
| 1999年~ | 「金融アセスメント法」制定運動 → 「金融検査マニュアル中小企業版」の発行等 |
| 2003年~ | 「中小企業憲章・中小企業振興基本条例」制定運動 → 憲章閣議決定、各地で条例制定、中同協「憲章草案」策定等 |
| 2014年 | 不公正な課税強化に反対する運動 → 中小企業への外形標準課税適用等を阻止 |









