中小企業憲章・地域振興基本条例運動のこれまでの流れとこれから(後編)
大林 弘道氏 神奈川大学・名誉教授
中小企業憲章の閣議決定から14年、愛知県中小企業振興基本条例の施行から12年を迎えました。他方で、憲章、条例ができて以後の入会者も増えた中、同友会が全国的運動課題として取り組んできた憲章と条例について、今一度振り返り、捉え直す学習会を、講師に大林弘道氏(神奈川大学・名誉教授)を招き開催しました。3回に分けてご紹介してきた講演要旨の最終回、後編として、憲章・条例運動と労使見解・憲章草案の関係性、今後の運動の展望を考えます。
(全編 ・ 中編)

労使見解・憲章草案の関係の理解
今後の課題として述べたことに加えて憲章・条例運動は、より広い視野を持つ運動にすることが重要です。そのための重要な課題は、憲章・条例運動と労使見解・憲章草案との関係の理解の深化の必要性が提起されているということであります。
『労使見解』は周知のように同友会運動の1970年代の飛躍の起点とも言うべき文書で、多くの会員の同友会運動への信頼の基盤になっています。また、労使見解の策定過程はひとつの物語(策定に関わった会員自身が自社の労働争議に直面した苦しみを乗り越えようとした苦闘の経験を土台にしていたこと)でもあります。そして、策定された労使見解自体は中小企業という存在の根幹、中小企業経営の真髄に触れる問題ですから、同友会以外の中小企業団体では、労使関係の重要性は百も承知でありながらも、到底「手を出せない」課題なのです。そのためかもしれませんが、幅広い支持を求める憲章・条例運動のこれまでの過程では、労使見解に言及されることもほとんどありませんでした。
労使見解なくして中小企業の出番なし
憲章・条例運動の課題を考えるとき、今後の同運動において、方法への慎重な考慮が必要ですが、現在の状況を踏まえるとき、労使見解へのさまざまな言及が必要と考えます。
現在、論壇や学会では「中小企業再編論・生産性論」(日本経済の低迷は中小企業の生産性の低さにあるから中小企業の規模拡大・再編によって生産性を上昇させることができるという見解)とともに、かつての「総資本対総労働」という「二項対決」論(社会における階級対立は資本家と労働者との対決にあり、資本、労働それぞれの内部の編成を無視ないし軽視しても問題ないという見解)が再浮上し、増大しているからです。
それらの見解は全く現実を無視しており、しかも、説明が必要ですが、結局は専ら大企業利益に寄与するという役割を果たしています。それゆえ、これら2つの見解が浸透しつつある現時点においてこそ、労使見解の重要性が強調されなければなりません。
労使見解なくしては、中小企業経営者の立場からも、中小企業労働者の立場からも、中小企業という希望の出番はありません。“労使の激突”か“企業と家族との同一視”かしかないからです。
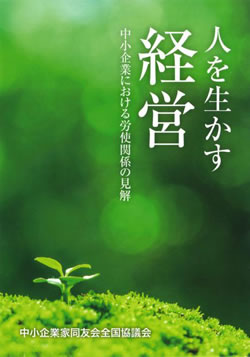
成果と課題を残した憲章「閣議決定」
憲章草案と憲章・条例運動の関係については、すでに主として「主語」の問題として述べられてきました。ここでは、別の観点での解明が必要です。憲章草案そのものの策定は、中小企業憲章の文案作成が政府機関においていよいよ取り上げられる時点で、同友会運動として「対案」を提起することは重要であると考えてのことでした。その「対案」策定の努力の成果が憲章草案でした。
ところが、それが憲章・条例運動の側で本格的に議論される前に現行の中小企業憲章が「閣議決定」として制定されてしまったのです。ですから、中小企業憲章の制定自体は既述のとおり、中小企業全体、中小企業運動、同友会運動にとってたいへんな成果でしたが、課題を抱えることになったわけです。それゆえ、憲章草案を制定後の中小企業憲章推進運動にとって改めて取り上げ、現行中小企業憲章の前進を図るべく有効な文書として位置付けているのです。
目指す姿にならないとどうなるのか
「目指す姿にならないと、どうなるか」を「憲章・条例運動の目標未達から生まれる状況」と解釈したとき、「目指す姿にならない」を「社会運動の目標未達」の問題と解釈して、まずその一般的な意味を理解しておくことが必要だと思います。そもそも一般に議会制民主主義を採用している社会では、議会にその社会の全員が参加する直接民主主義を採用しない場合には代議員を選挙で選びます。とはいえ、選挙で選ぶということは、首長あるいは議会の多数派に全権を委任しているわけでなく、それゆえ、選挙時には論戦で残された、あるいは、新たに浮上した問題の解決を求めて社会運動が登場することになります。
しかし、このような社会運動の諸提案・諸要求はあまり実現しないのが歴史上に多く見られた現象です。その要求が普遍的な真実でない場合はもちろん、また、議会多数派の見解と異なり、それと対立するものである場合は、多くの場合、社会運動は頓挫することになります。しかし、だからと言って、普遍的真実であってもすぐに目標達成するわけではありません。また、逆に少数派であっても目標を達成することがあります。
以上から言えることは、憲章・条例運動は、普遍的真実であるとの確信を基礎に、最初は少数派の運動から出発して、その後約7年をもって少なくとも部分的成功を果たした、日本の社会運動の歴史の上では稀有な事例なのです。

憲章・条例運動の目標未達から生まれる状況
「目指す姿にならないと、どうなるのか」という問題は、憲章・条例運動の目標未達から生まれる状況ということになります。そのためには、(1)憲章・条例運動が課題として取り上げた諸問題が実現しないままの現状の延長線上でどのようになってしまうのか、(2)今後の憲章・条例運動によって「部分的な達成」の結果として、現状がどうなるのかという、2つのシミュレーション的な想像が必要になります。
それぞれたいへん難しい問題ですが、(1)に関しては、憲章・条例運動における、とりわけ同友会運動における会員の現在の日々の経営体験の実感からの多数の発言の収集と、それらの整理から出発すべきでしょう。(2)については、日々の憲章・条例運動のどんな小さい成果でも、それらの収集と総括が重要になります。

2つのシミュレーション
まず、(1)について私の危惧する基本的な状況は、憲章・条例運動が消極的になれば、現在流布しつつある中小企業再編論などの種々の中小企業無用論がさらに活発化して、政策の重点も専ら中小企業のM&Aが対象となって推進されてしまうということです。とはいえ、すべての中小企業が対象となることは不可能ですから、その対象にならない少なくない中小企業は政策的に放置され、経営上も困難となり、労使とも困窮に陥ることになるでしょう。そうした中小企業は不本意な事業(低利潤な分野や期待しない分野等)に政策的配慮なしに誘導されることになるでしょう。
(2)の場合は、「部分的な達成」が継続されなければ、(1)と変わらない状況になるでしょうが、「部分的な達成」が継続された場合には、範囲はさまざまでしょうが、「目指す姿」に近づくことになります。そして、そうした過程そのものから得難い学びや教訓があるはずであり、憲章・条例運動や自社経営に役立つことが少なくないでしょう。
大事なことは、「目指す姿にならない」としても、戦争さえなければ、決して「デストピア」にはならないということです。
そもそも資本主義経済(あるいは社会主義市場経済)においては、どのような発展段階の過程でも、一方で企業間の吸収・合併が進みますが、他方で中小企業は存続・新生することが法則的に機能します。それゆえ、どんな独裁的な権力の元においても、いくら中小企業を無くせと言っても、中小企業は無くならないのです。あるいは、特定なタイプの中小企業だけを残せと言っても多様な中小企業が生誕するのです。
おわりに ―今後も繰り返し議論を
今回の学習会に先立って提示された論題に関わる諸項目(下記)は、同友会運動、憲章・条例運動上の切実な思いから生まれたものであり、いずれも大事な論点です。今後も繰り返し議論されることを期待します。憲章・条例運動の実践を踏まえた、そのような論点の議論こそ、個々の諸成果に、やがては基本から細部に関わる成果につながると考えます。
そして、こうした努力こそが、中小企業の発展の基礎・基盤となります。愛知同友会の奮闘努力を期待しています。
【文責:事務局 池内】
今回の学習会に先立って提示された論題に関わる諸項目(抄)および、各項目についての講演要旨を紹介した本記事の回
[1]憲章・条例運動の原点~なぜ憲章運動を始め、何を目指した(新たな日本の姿)のか
⇒前編(同友Aichi 2025年1月1日号)
- 経営環境改善部門(11月18日)前編
中小企業憲章・地域振興基本条例運動のこれまでの流れとこれから(前編)
[2]この運動の到達点~これまでの成果とその相互関係(通過点である認識)
⇒中編(同友Aichi 2025年2月1日号)
- 経営環境改善部門(11月18日)中編
中小企業憲章・地域振興基本条例運動のこれまでの流れとこれから(中編)
[3]目指す原点に向けてこれから何をしていくのか
~同友会が続く限り追求していく
(労使見解と憲章草案)
[4]目指す姿にならないとどうなるのか
⇒後編(同友Aichi 2025年3月1日号)









